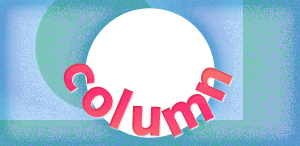
人生の指針となるようなインタビューや、スキマ時間にお楽しみいただけるコラムを紹介します。
2026.01.29
建築設計と働く喜び──第6回 沼田祐子
.jpg)
建築人を豊かにすることを目指すA-magazineが、建築設計に携わる人びとが建築設計のどのような点に働く喜びを見出しているのかをシリーズで紹介する”建築設計と働く喜び”。第6回は、130年以上の歴史を誇る組織設計事務所、三菱地所設計でニコン本社などの設計を手掛ける一方で、2025年にはYNASにて自邸の設計も行った沼田祐子さんに寄稿していただきました。
======
建築のきっかけとクライアントと旅
建築家という仕事は、特異な職業だと思う。
人の暮らし、仕事、個性を読み取り、歴史、環境、構造を組み込み、美しく成り立たせる。 街を少しだけ変える。 風景を切り取る。 そして、人の生活が変わる。
建築学生から始まり、設計の仕事に携わって計18年。 私と建築とのかかわりは、クライアントへの意識の変化と、旅によって補填した日常を中心に、思考の堂々巡りを繰り返してきた。そうして今ようやく、設計を通して少しずつ現実へ、精細な形へと落とし込めるようになってきた「初期段階」にいると感じている。
根本的な部分は何も変わっていないなか、微妙に変化してきたそれぞれの思考の段階について、ここに思い返してみたい。
自分が創造するクライアント
「建築」とは何か。「建築家」とは何か。 漠然とした建築への興味と、ものづくりを仕事にしたいという思いだけで、私は東京藝術大学美術学部建築科に入学した。知識としての建築はひとつもないまま、入学式の日に最初の一課題が手渡されたその瞬間から、建築を考え続ける日々が幕を開けた。
学生時代の課題における「クライアント」は、あくまで架空の存在だった。土地と用途は大まかに与えられるものの、使い手を自分なりに想像し、好みの人物像を自ら演じながら、コンセプトとストーリーを成立させていたのだ。
実務と学生課題の決定的な違いは、顔の見える生身のクライアントの存在の有無にある。要望も予算も、計画のGOサインも、すべては彼らが握っている。その重みを明確に理解したのは実務に出てからだが、学生時代から肌で感じていたと思う。
周囲には絵画や彫刻、工芸を志す、すでに作家である学生がいたからだ。彼らは自分のなかで完結した世界を創り上げ、それが完成して初めて世に問い、評価を受ける。対して建築は、誰かの依頼が必然であり、誰かのために創るものだ。アトリエで髪を振り乱し、創作に没頭する他科の作家たちを見つめながら、「建築は芸術になりうるが、建築家は芸術家にはなれない」──そんな感覚を抱いていた。
一方で、教授陣は「建築には社会に対する使命がある」と説く。当時の私はその本質を深く理解せぬまま、素直に自分がその担い手の一員になることを当然のこととして受け入れていた。
その頃に始めた一人旅もまた、今思えば浅いものだった。 世界の名建築を訪れ、スケッチして回る。それだけで自分の世界が広がった気になっていたが、本来ならその建築が生まれた経緯やクライアントとの関係、歴史的背景といった「目に見えない情報」こそ、深く学ぶべきだったのだ。 けれど、自分だけでストーリーを完結させる設計手法に浸っていた私には、そこまで考えが及ばなかった。「かっこいい」「きれい」「風景に溶け込んでいる」。そんな感覚的な感想を抱くだけで、精一杯だったのだ。
社会がクライアント
卒業設計の思案中、神田川と三本の線路が交差する風景をぼんやりと眺めていたときのことだ。突然、「あ、そういうことかもしれない」と、建築が社会に与える影響の意味に、触れられたような気がした。入学から4年を経て、ようやく建築家の言葉が理解できるようになり、建築のもつ力に気づき始めたのかもしれない。
卒業設計のタイトルは「風景の転換」。東京都心の遺構を舞台に、都市の廃棄物問題と河川インフラを結び付け、歴史に眠る機能を蘇らせて現代の人びとを取り込む提案だ。当時、まだ日本社会でコンバージョンという概念が表に出てきていなかったなか、設計テーマを決めてからは新築することは全く考えなかった。単なる建物の用途変更ではなく、街や社会のシステム自体のリノベーションを志向し、「風景の転換」と名付けたことからも、その意図が窺える。初めて、都合よく設定した架空のクライアントではなく、「社会」そのものを相手に提案を行った。その時の思いは今も変わらず、建築の最適解は「壊して建てる」ことだけではないと信じている。
大学院に進むと、オルヴィエートというイタリアの小都市の研究に没頭した。この頃から、観光地化されていない小都市に魅せられるようになった。ガイドブックに印が付いている場所には行きたくないという、謎の意地もあったように思う。ホテルでも民泊でもなく、宿泊を生業としていない現地で出会ったファミリーの家に滞在し始めたのもこの頃だ。
イタリア在住時は、行き先も決めずに鈍行列車やバスに乗り、一駅ごとに降りては一日中歩き回り、地元の人と言葉を交わす。そんな小さな旅が日常にあった。どんなに小さな町にも旧市街があり、観光客がいなくとも、そこには生活の匂いと人びとの活気がある。それは、中世の街並みや建築を受け継ぎながら、都市単位で常にリノベーションし続けているからだろう。そこでのクライアントは住人たちであり、提案者も実行者もまた、住人本人たちである。「社会をクライアントとする」。それは、自分自身がより良い社会を考え、動き続けるということなのかもしれない。自分で創造し演じるクライアントとは全く別の存在である。
顔の見えるクライアント
組織設計事務所に入所して間もなく設計スキームに参加し、数年の実務を経た頃、ふたつの本社ビルプロジェクトをプロポーザルから現場竣工まで通しで担当する機会を得た。「本社ビル」という顔の見えるクライアントと直接対話し、共に設計を進める環境。それは、実務を担うことの喜びそのものを実感させてくれるものだった。
本社ならではの新しいプランニング、企業を象徴する環境装置や構造体を一から考案し、その思考を直接クライアントに提案できる。このプロセスにより、今までどこか漠然としていた「クライアント」という存在が、ぐっと身近なものになった。彼らの要望や解決すべき課題は、いつの間にか自分自身の課題となり、「建築で解決したい」という私自身の熱意へと変わっていった。「クライアントと同じ思いを共有する建築家」へと、私自身が変化していたのだ。
クライアントの存在が明確になり、設計の仕事の幅広さを体感する日々。検討を重ねても終わりのない毎日は充実しており、時間はあっという間に過ぎていく。だが、理論的で合理的な設計思想を展開すればするほど、逆に感覚的な造形を提示することに恐怖を感じるようになった。説明の付かない「かっこよさ」や「美しさ」が、何なのかわからなくなってしまったのだ。
知識などなかった学生時代に感じた、理屈抜きの「ただかっこいい」という感覚が恋しい。設計する上での土地や歴史の分析ではなく、もっと感覚的にその街や土地を感じたい。そう思い立ち、忙しい日々の隙間を見つけて、ネット環境を断ち切りイランへと向かった。
地理的に水が集まる場所に形成された街。その土地で育つ木の実で染められたペルシャ絨毯。強烈な日射をしのぐための小さな窓と屋外のカーテン。その土地の土の色で積まれた日干し煉瓦の街並み。ピンク色。そこで見たものは、作為的に「かっこいい」ものはひとつもなく、すべてが環境的に合理的で、土地の色がそのまま反映されていた。それなのに、一番初めに心に響くのは、説明の付かない圧倒的な美しさだった。
これまでは旅を通じて自分の知識や設計思想を補ってきたつもりだった。だが、この経験と実務の充実が重なり合うことで、自分のなかに足りない「何か」への不安が、静かに膨らみ始めていた。
自分がクライアント
そんな折、プライベートで自邸兼仕事場となる「神宮前スタジオ」を設計することになった。場所は、偶然見つけた「ビラ・セレーナ」(設計:坂倉建築研究所)の一室。私が日本で一番好きな集合住宅だ。都心にありながら開発の手が及んでいない、古くくねった路地の先に現れるその建物は、まるでその土地がそのまま隆起し、入り込んだかのような佇まいを見せている。自宅と仕事場、それぞれのエリアの特性。周辺に古くから根付く人びとの生活。そして、高低差のある敷地形状。それらすべてをリンクさせるように設計を進めた。ほんの小さな一室が、確かに街の一部であることを感じた。大型の新築建築であれ、一室のリノベーションであれ、設計において求められる思考の密度や精度は、ほとんど変わらないということは大きな発見であった。ここでもすべてのデザインに合理的な意味をもたせたが、同時に、日々の暮らし、居心地の良い動作、夫婦の距離感をじっくりと考え抜いた。その結果、完成した後には「デザインを一生懸命説明しよう」と思わなかった。抱えていた不安が、なくなったのだ。自分自身がクライアントでありながら、社会の一員でもあるという意識。そして、一歩引いて俯瞰するこれまでの経験。それらが重なり合い、10年前とも18年前とも違う、新たな建築家としての視座を少しは獲得できたのだと思いたい。
そうしてこの空間で暮らし始め、一年。今は日本の何でもない街角や、古くも新しくもないありふれた道。そうした、旅とも呼べない小さな風景を巡ることに、新たな興味が湧いてきたのである。
これまでの各段階における設計スタンスと、クライアントの捉え方を振り返ってきた。改めて感じるのは、どの段階においても、クライアントの要望は最終的に自分自身の考えの一部となり、不可分なものとして存在していたということ。
かつて学生時代に引いた「芸術家」と「建築家」の境界線。分けて考える必要など、本来はなかったのかもしれない。重要なのは、多角的な視点をもち、その時々の様々な「クライアント」の方を向いて、真摯に設計を行うこと。ただそれだけなのだと思う。
私の建築家としての「初期段階」をそろそろ終えて、次の段階へ足を踏み入れたい。
(企画・編集:ロンロ・ボナペティ)
沼田祐子
1988年 東京都生まれ
2011年 東京藝術大学美術学部建築学科卒業
2012年 Sapienza Univerusitá di ROMA特別課程修了
2015年 東京藝術大学大学院修士課程修了
2015年~ 三菱地所設計
2024年~ YNAS/沼田祐子建築設計スタジオ
代表作品に、ニコン本社/イノベーションセンター、北海道新聞社本社、神宮のスタジオ。

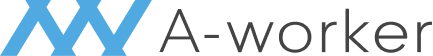

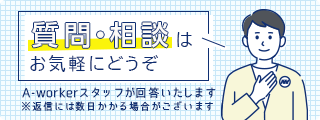





.jpg)
が設計した金沢21世紀美術館-21st-Century-Museum-of-Contemporary-Art-Kanazawa-DesignSANAA.jpg)





.jpg)