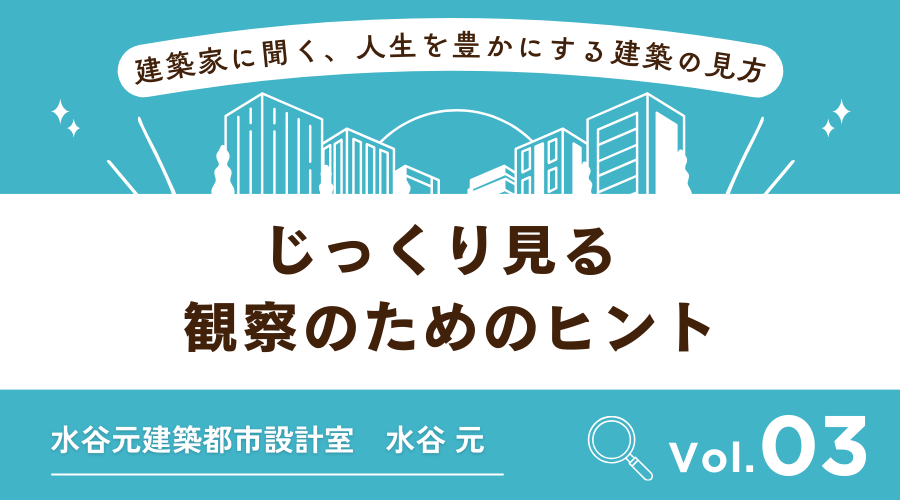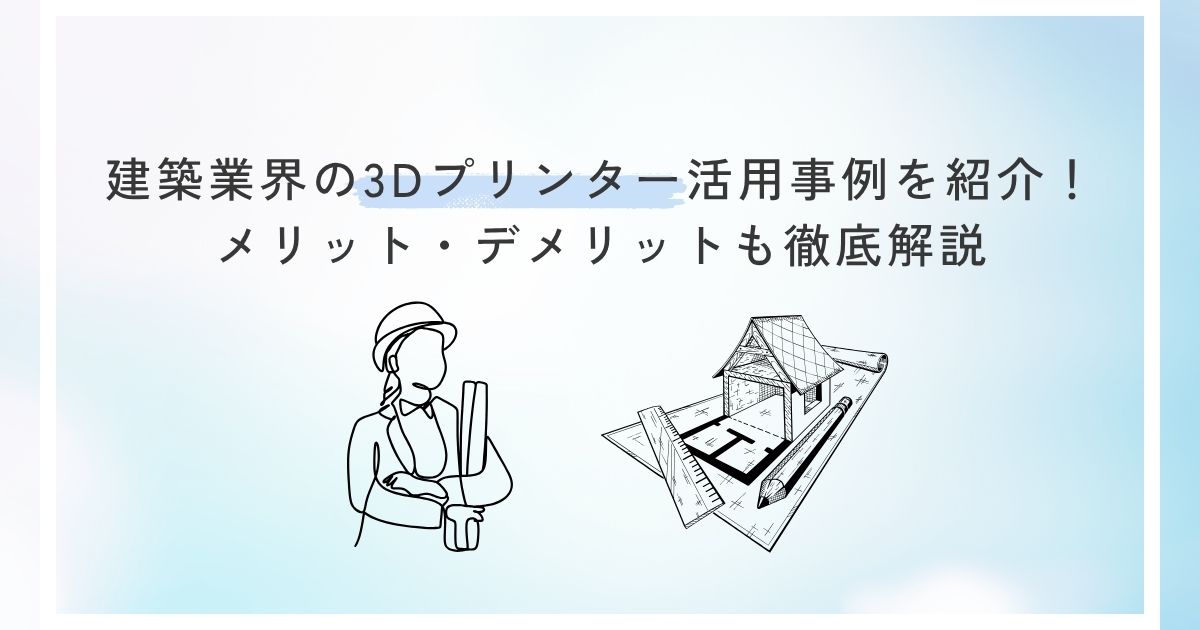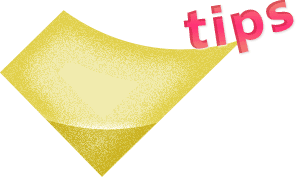
建築業界のリアルな情報や就職・転職活動で役立つ情報を紹介します。
2025.10.18
建築家が海外就職する方法とは?海外で活躍するために持っておくべき資格も紹介
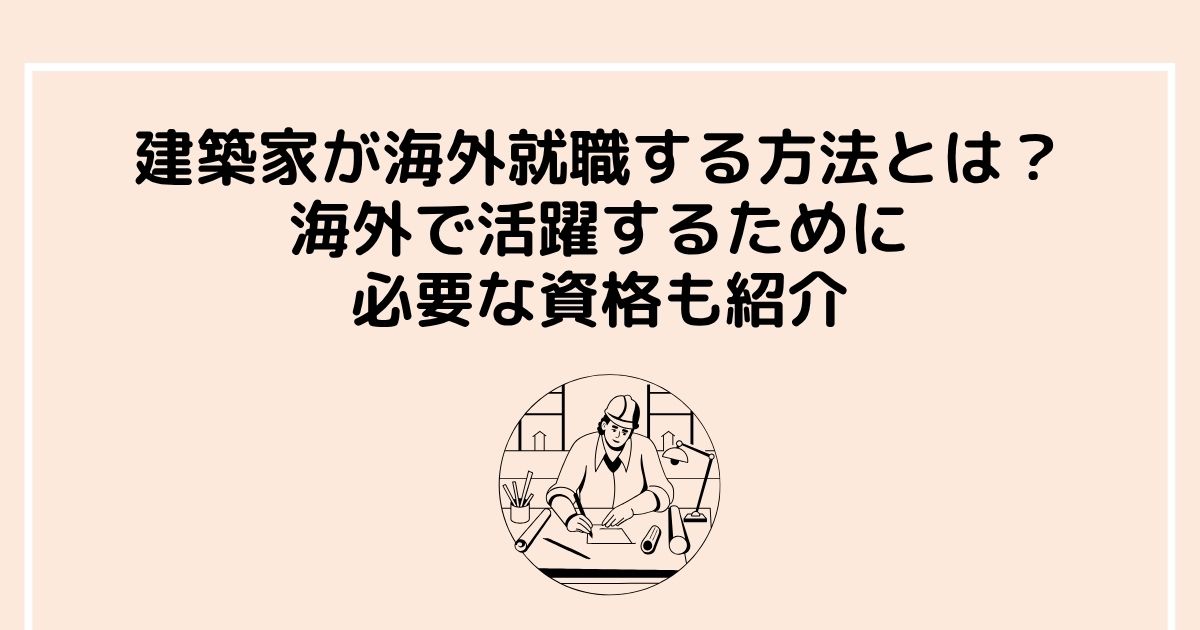
グローバル化が進む現代において、建築家にとって海外での活躍の場は大きく広がっています。
日本の高い建築技術は、世界各国から高く評価されており、海外での就職機会は決して少なくありません。
しかし、海外就職を成功させるためには、適切な方法で求人を探し、各国の制度を理解し、必要な資格や準備を整えることが重要です。
本記事では、建築家が海外就職を実現するための具体的な方法から、国別の建築試験制度、必要な資格、注意点まで包括的に解説します。
海外での挑戦を考えている建築家の方は、ぜひ本記事を最後までご覧ください。

海外の就職先を探す方法
海外での建築家としての就職先を見つけるには、複数のアプローチを組み合わせることが効果的です。
ここでは、実際に多くの建築家が活用している主要な3つの方法を紹介します。
LinkedInは世界最大級のビジネスSNSとして、海外就職において極めて重要なツールです。
まずは充実したプロフィールを英語で作成しましょう。
これまでの経験、携わったプロジェクト、保有資格を詳細に記載することで、海外の採用担当者の目に留まりやすくなります。
また、建築関連のスキルや専門知識をキーワードとして適切に配置することで、検索されやすくなるのです。
設計事務所や建設会社がLinkedInで求人情報を掲載しているため、定期的にチェックしましょう。
Google Map
Google Mapを活用した求人探しもしてみましょう。
この方法の最大のメリットは、特定の地域に絞って設計事務所を探すことができる点です。
検索したい都市のGoogle Mapで「Architectural firm」や「Architecture studio」などのキーワードで検索すると、その地域の設計事務所が一覧表示されます。
各事務所の公式サイトにアクセスし、採用情報ページやお問い合わせフォームから直接応募することが可能です。
この方法では、大手の求人サイトには掲載されていない中小規模の設計事務所とも出会えるため、競争率が比較的低い可能性があります。
また、実際の立地を確認できるため、住環境や通勤の利便性も同時に検討可能です。
Indeed
Indeedは世界各国で利用されている求人検索エンジンで、海外の建築関連求人を探す際の定番ツールです。
国や地域を指定して検索できるため、希望する勤務地での求人情報を効率的に収集できます。
検索の際は「Architect」「Architectural Designer」「Building Designer」などの職種名と、希望する国名や都市名を組み合わせて検索するのがおすすめです。
定期的に新着求人をチェックし、条件に合致する案件が見つかったら迅速に応募しましょう。
出典:Indeed公式サイト
国ごとに建築試験制度は異なる
海外で建築家として活動するためには、各国の建築試験制度や資格要件を理解することが大切です。
国によって試験制度、受験資格、合格率などが大きく異なるため、目標とする国の制度を事前に把握しておきましょう。
アメリカ
アメリカでは「建築家登録試験(ARE:Architect Registration Examination)」に合格することで、建築家として活動する資格を得られます。
アメリカの建築家は「Architect」と呼ばれ、社会的地位も高い職業として認知されています。
受験資格を得るためには、NAAB(全米建築認定委員会)により認定された大学で建築教育を5年または6年間受け、学士または修士の学位を取得する必要があります。
さらに、州ごとに定められた実務経験(基本的には3年間、一部州では2年間)を積むことが求められます。
受験の競争率は激しいですが、日本の建築技術力は高く評価されているため、適切な準備をすれば合格の可能性は十分にあります。
出典:公益財団法人建築技術教育普及センター公式サイト「海外諸国の建築家試験制度について」
オーストラリア
オーストラリアでは「建築実務試験(APE:Architectural Practice Examination)」が実施されており、合格者は「Architect」として登録されます。
試験は小論文と面接という実践的な内容で構成されています。
受験資格は、認定を受けた大学での建築学位(5年間)の取得と、2年間以上の実務経験が必要です。
ただし、実務経験のうち1年間は学位取得後のものでなければなりません。
オーストラリアの建築試験は合格率が約85%と比較的高く、適切な準備をすれば合格の見込みは高いと言えます。
英語での面接が含まれるため、技術的な知識だけでなく、英語でのコミュニケーション能力も重要な要素です。
イギリス
イギリスでは「専門実務試験」に合格することで、「Architect」としての資格を取得できます。
試験は記述式の問題と面接で構成され、実務に即した内容が重視されます。
受験資格を得るためには、3年間の教育課程(Part Ⅰ)と2年間の教育課程(Part Ⅱ)の計5年間の建築教育、さらに2年以上の実務経験が必要です。
もしくは、RIBA(王立英国建築家協会)のPart ⅠおよびPart Ⅱレベル試験の合格と2年間の実務経験でも受験資格を得られます。
資格の登録は建築家登録委員会(ARB)で行い、1年ごとの更新が必要です。
ドイツ
ドイツの建築家資格制度は他国とは大きく異なり、試験がない場合があります。
資格名称は「建築家」「内装建築家」「景観建築家」などと専門分野によって区分されています。
基本的には登録申請による資格取得となり、ドイツの大学で建築学等を3~5年間履修した後、2~3年間の実務経験を積むことで資格を得られます。
ただし、学歴がない場合には実務経験のみで筆記試験と面接試験が実施される州(バイエルン州など)もあります。
フィンランド
フィンランドでは資格試験そのものが実施されておらず、学歴と経験によって資格が認定されます。
「建築家」または「建築技士」という名称で呼ばれています。
建築家になるためには、ヘルシンキ工科大学、オウル大学、タンペレ工科大学、または海外の同等大学で建築専攻を卒業することが条件となります。
一方、建築技士は高等職業専門学校での建築学位取得者に付与されます。
中国
中国では「一級注冊建築師試験」が実施され、合格者は「注冊建築師」として登録されます。
試験は多枝選択式と製図で構成されています。
受験資格は以下のいずれかを満たす必要があります。
・大学等(5年)建築学士号取得と実務3年
・大学等(5年)建築修士号取得と実務2年
・高級工程師技術職と実務3年
・工程師技術職と実務5年
・設計上の優れた実績による認定
中国の建築試験は合格率が概ね5%前後と非常に厳しく、十分な準備と高い専門知識が求められます。
台湾
台湾では「建築師高等考試」が実施され、合格者は「建築師」として認定されます。
試験は記述式で行われ、深い理解と表現力が問われます。
受験資格は、以下のいずれかを満たす必要があります。
・専門科以上の学校卒業または教育部承認の海外同等学校卒業
・公立・登録私立大学等卒業で建築設計科目18単位以上履修
・建築工事科試験合格と建築工事実務4年以上
台湾の合格率は約8.7%程度と中国同様に非常に厳しいですが、日本と文化的な共通点も多く、日本の建築家にとって比較的親しみやすい国だと言えるでしょう。
韓国
韓国では「建築士資格試験」が実施され、資格名称は日本と同じ「建築士」です。
試験は多枝選択式と製図で構成されています。
受験資格は、下記のいずれかを満たす必要があります。
・建築士予備試験合格と7年間の実務
・建築分野技士1級取得と7年の実務
・建築分野技術士資格者
・建築士予備試験または技士1級取得と建築士補5年の実務
・外国での免許等と5年の実務(科目免除有)
・高校か3年制高等技術学校卒と4年の実務学歴なしの場合は9年の実務
韓国の建築市場は技術革新に積極的で、特にスマートビルディングやIoT技術の導入において先進的な取り組みを行っています。
海外で活躍するために持っておくべき資格
海外での建築家としての活動を成功させるためには、日本で取得できる特定の資格を取得することが重要です。
一級建築士
一級建築士は日本の建築士資格の最高位にあたり、海外での就職活動において最も重視される資格です。
国土交通省管轄の国家資格であり、規模や用途に制限なくあらゆる建物の設計・監理を行えます。
海外の設計事務所やゼネコンでは、この資格を持っていることが日本の高度な建築教育と実務経験の証明と見なされます。
特に設計職を希望する場合、一級建築士の資格は採用の可否に直結するほど重要で、他の応募者との明確な差別化要因となります。
一級建築施工管理技士
一級建築施工管理技士は、建築工事現場における主任技術者および監理技術者として活動できる資格です。
設計だけでなく施工管理の専門知識を持つことを証明し、海外でのプロジェクトマネジメント業務において強力な武器となります。
施工管理やプロジェクトマネージャーのポジションでは、この資格を持つことで採用の可能性が格段に上がります。
一級土木施工管理技士
一級土木施工管理技士は、橋やトンネル、ダム、道路などの大規模インフラ工事における最高責任者として活動できる資格です。
日本の土木技術は世界屈指の水準にあり、この資格保有者への需要は非常に高いです。
特に発展途上国でのインフラ開発プロジェクトなど、日本の技術力が求められる現場では、資格保有者は即戦力として高く評価されます。
電気工事施工管理技士
電気工事施工管理技士は、建築物の電気設備工事における専門的な施工管理能力を証明する資格です。
現代建築において電気設備は建物の機能性と安全性を左右する重要な要素であり、この専門知識は海外でも高く評価されています。
近年、スマートビルやデータセンターなど、高度な電気設備を要する建築物が世界的に増加しているため、この分野のスペシャリストは引く手あまたです。
ニッチな分野だからこそ、資格を持っていることで他の建築士との差別化を図れ、専門職として採用されやすくなります。
出典:Fortune Business Insights「スマートビル市場規模、シェア及び業界分析」
認定コンストラクション・マネジャー
認定コンストラクション・マネジャーは、建築・土木プロジェクトの総合的なマネジメント能力を証明する資格です。
計画、設計、コスト管理、工程管理、品質管理、リスク管理など、プロジェクト全体を統括する高度な専門性を持っていることを示します。
外資系の建設コンサルティング会社や大規模なプロジェクトでは、コストやリスクを管理するコンストラクション・マネジメントの手法が一般的です。
この資格は、プロジェクト全体を把握し、事業主の利益を最大化できる能力の証明となり、特にマネジメント層やコンサルタント職への就職・転職で極めて有利に働きます。
出典:国語交通省「米国におけるCM方式活用状況 調査報告書」
英検
英検は、海外就職で重要な資格の1つです。
建築の専門知識がいくら優れていても、現地でのコミュニケーション能力がなければその価値を十分に発揮できません。
英検準1級以上の取得を目標とし、建築専門用語についても学んでおきましょう。
技術力が同程度の候補者が複数いる場合、語学力の高さが採用の決め手となることが多いです。
海外就職する際のポイント・注意点
海外就職を成功させるためには、戦略的なアプローチと入念な準備が不可欠です。
重要なポイントを押さえることで、海外就職の可能性を大幅に高められます。
事前に上司へ海外就職の希望を伝えておく
現在勤務している会社で海外勤務の機会がある場合、早めに上司へ海外での勤務希望を伝えましょう。
多くの建設会社や設計事務所では、海外勤務を希望する社員は限られており、会社側も適切な人材を探しています。
海外勤務の競争は激しいものの、実際には国内勤務を希望する社員の方が多数派です。
そのため、明確に希望を伝えることで選ばれる可能性が高まります。
グローバル展開している建設会社へ転職する
海外勤務を実現するための最も確実な方法の1つが、グローバル展開を積極的に行っている建設会社への転職です。
スーパーゼネコンや大手ゼネコンの多くは海外支店を持ち、継続的に海外プロジェクトを手がけています。
これらの企業では海外勤務のためのキャリアパスが明確に決められており、語学研修や異文化研修などの充実したサポート体制が整っています。
現場監督としての経験を積む
海外の建築プロジェクトでは、現場監督としての実務経験が非常に高く評価されます。
図面を描くだけでなく、実際の建設現場における品質管理、安全管理、工程管理、予算管理などの総合的なマネジメント経験は海外でも通用するスキルです。
そのため、現場監督としての経験を日本で積んでおきましょう。
語学を習得しておく
語学を習得しておくことも重要です。
建築業界では専門用語が多く、構造、設備、材料、工法、法規など各分野の専門用語を英語で理解し正確に使用できる能力が求められます。
建築専門書の英語版を読むなど専門分野に特化した学習をしましょう。
まとめ
建築家が海外で活躍するには、計画的な準備が不可欠です。
本記事では、LinkedInなどを使った求人探しの具体的な方法から、アメリカやイギリス、アジア各国の建築試験制度の違い、有利になる日本の資格などを解説しました。
海外就職を成功させたい方は、ぜひ参考にしてください。




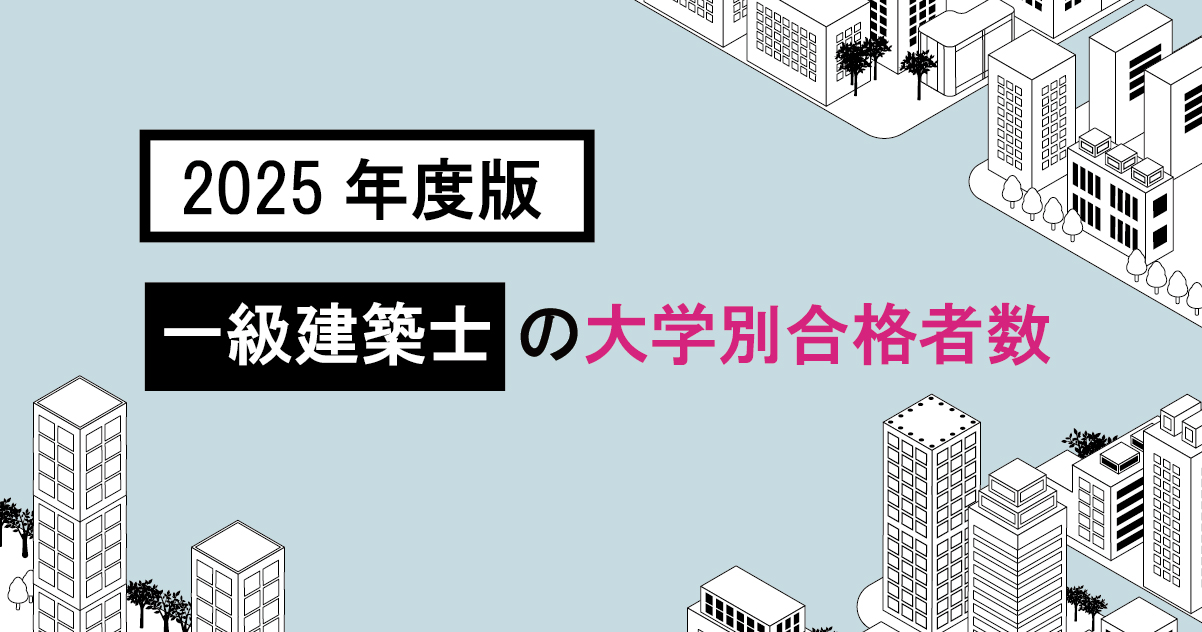


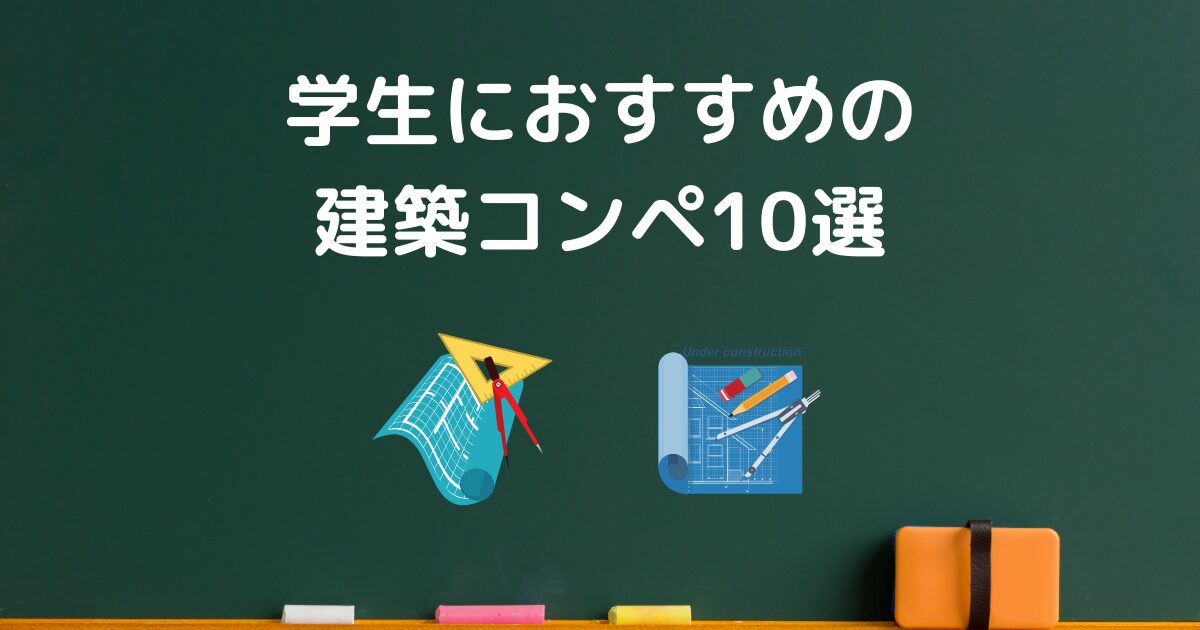


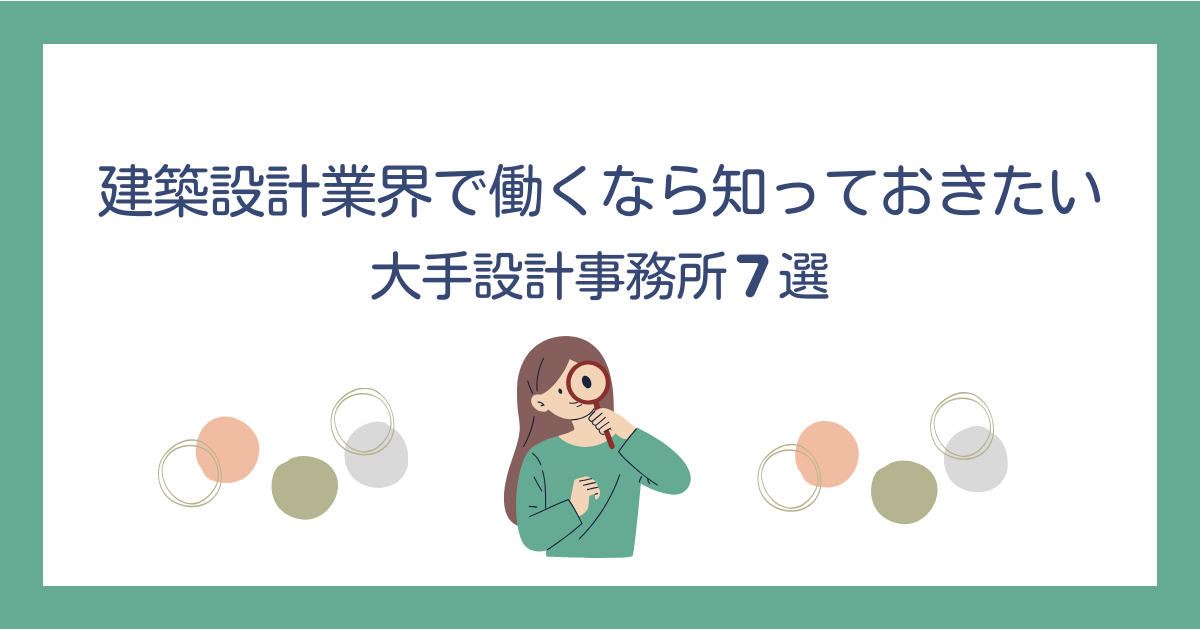



.jpg)