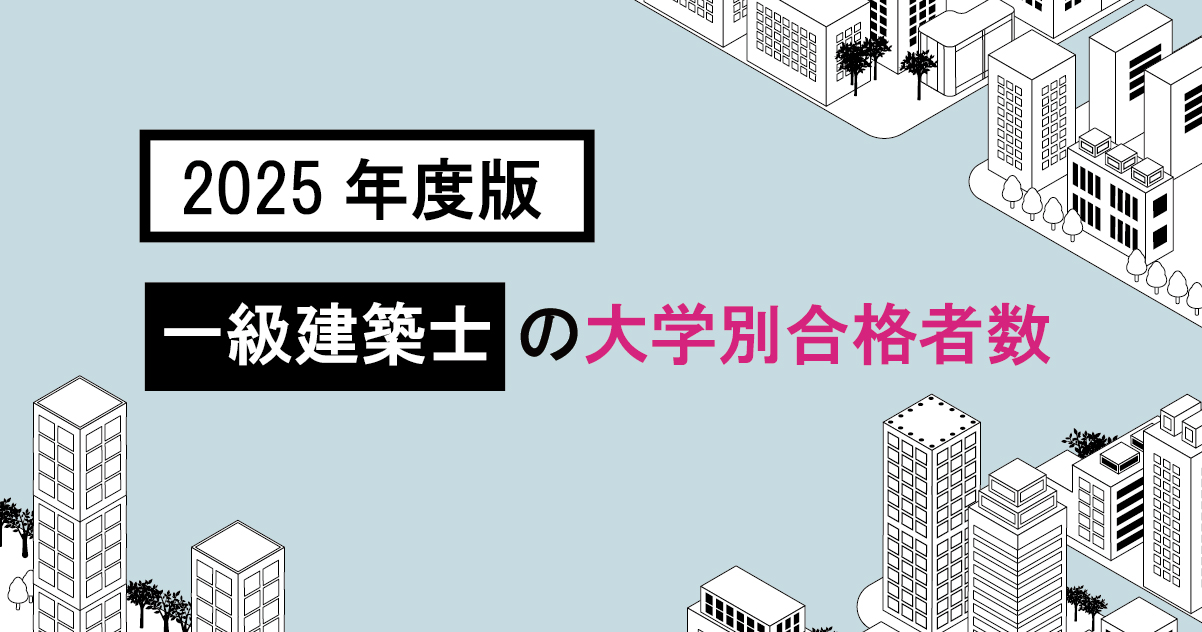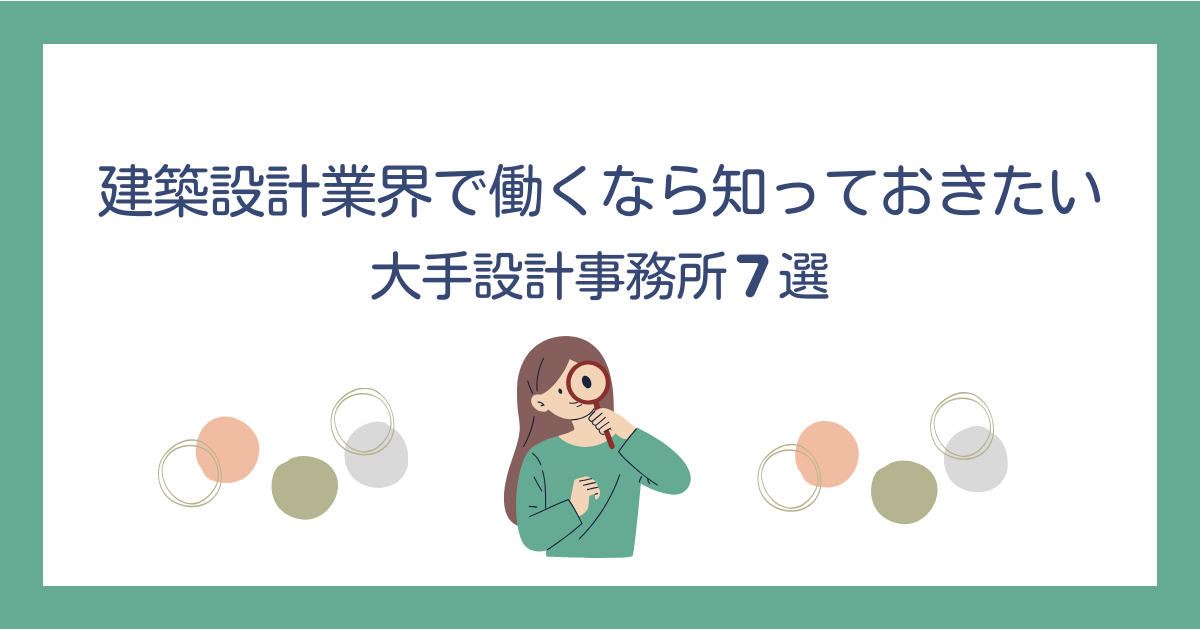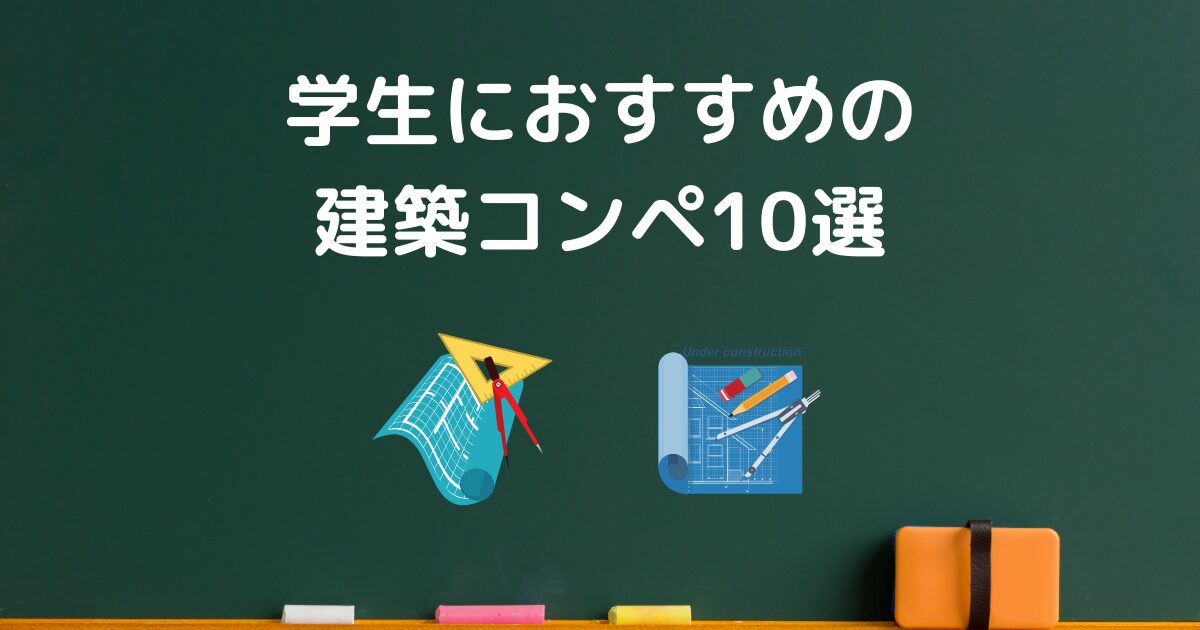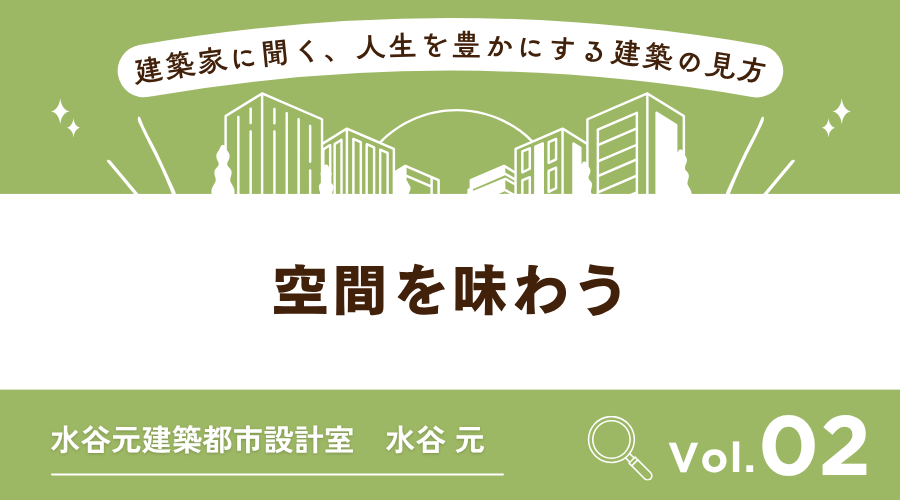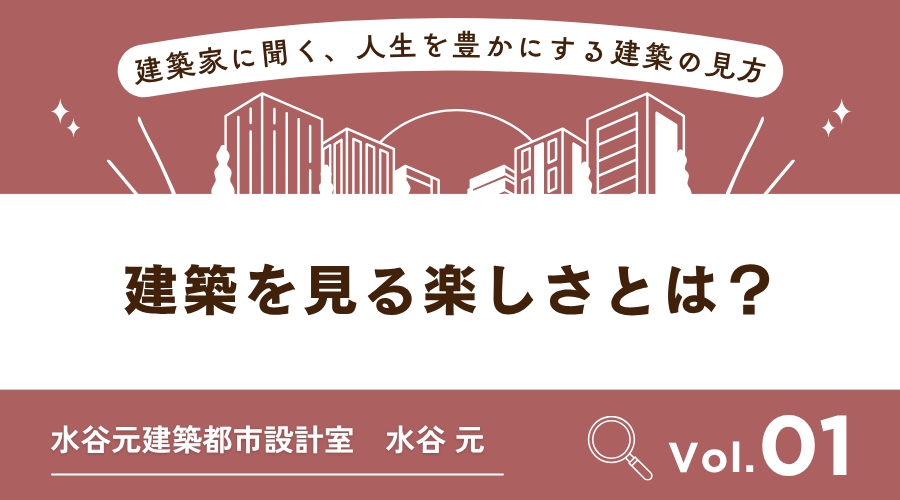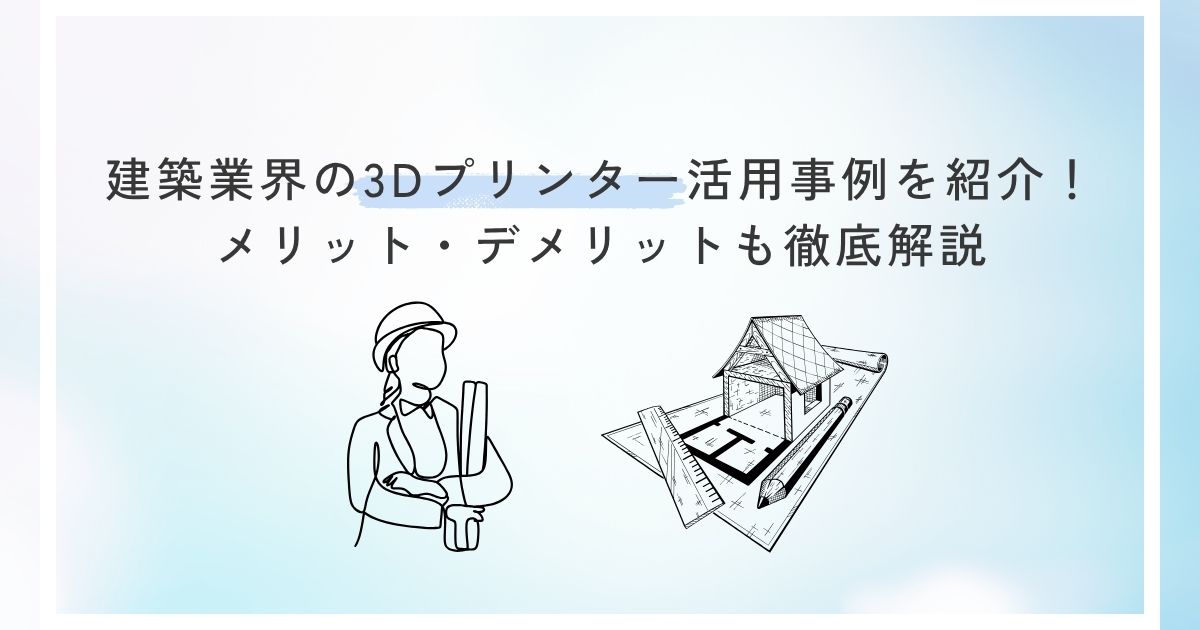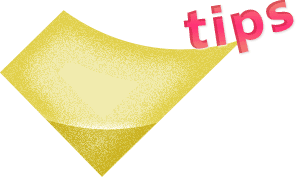
建築業界のリアルな情報や就職・転職活動で役立つ情報を紹介します。
2025.09.06
建築VE提案の事例集 コストの削減方法とポイントを解説

建設業界において、品質を維持しながらコストを削減する手法として注目されているのが「VE提案」です。
近年、入札競争の激化や資材価格の高騰により、従来の施工方法だけでは競争力を保つことが困難になってきています。
そこで重要になるのが、受注側から発注者に対して積極的に価値向上の提案を行うVE提案です。
本記事では、建築VE提案の基本的な考え方から具体的な事例、実施のポイントまでを詳しく解説します。
建設業界でより競争力のある提案を目指している方は、ぜひ参考にしてください。

建築VE提案とは
VE提案とは、Value Engineering(バリューエンジニアリング)の略で、日本語では「価値工学」と呼ばれます。
これは、製品やサービスの機能・品質を維持または向上させながら、コストを削減することで総合的な価値を高める手法です。
建築業界におけるVE提案は、受注側が発注者に対して、品質とコストの両面を意識した改善案を提示することを指します。
従来の建設工事では、受注者は発注者から指定された通りに施工することが一般的でした。
しかし、VE提案を導入することで、受注者が積極的により良い提案を行い、必要な品質を維持しつつコストパフォーマンスの高い建設工事を実現できるようになります。
VE提案は、建設プロジェクトの「企画・計画」「設計」「施工」「維持管理」のどの段階でも実施可能です。
具体的には、施工方法の変更、使用材料の見直し、作業工程の最適化などを通じて、コストダウンを図りながら品質の向上を目指します。
この手法により、発注者は品質を維持しつつコスト削減を実現でき、受注者は自社の技術力をアピールできるとともに、受注機会の拡大に繋げることができます。
VE提案とVA提案の違いとは
VE提案と混同されやすい概念として「VA提案」があります。
VA(Value Analysis:バリューアナリシス)は「価値分析」と訳され、既存の製品やサービスに対して品質を維持したままコストダウンを図る手法です。
両者の主な違いは、対象となるタイミングにあります。
VE提案は新しい企画やプロジェクトの開発段階で実施される活動で、同じコストで品質を高める、または品質を維持してコストを抑えることを目的とします。
一方、VA提案は既存の製品やサービスに対して改善を行う活動です。
建設業界では、VE提案は設計段階や工事入札段階で実施されることが多く、VA提案は既に完成した建物の維持管理段階で活用されることが一般的です。
しかし、どちらも「必要な品質は維持し、コストパフォーマンスを向上させる」という目的は同じため、実際には「VA/VE提案」として一体的に扱われることもあります。
VEに関わる資格とは
VE提案を効果的に実施するためには、専門的な知識と技術が必要です。
日本では、社団法人日本バリュー・エンジニアリング協会が中心となって、VEに関する資格制度が整備されています。
VEリーダー
VEリーダーは、企業や団体においてVE活動のリーダーを務めるために必要な基礎知識を有していることを日本VE協会が認定する資格です。
現場監督や責任者などが対象となり、VEの考え方に基づくスキルアップや人材育成に貢献する役割を担います。
この資格を取得することで、チーム内でのVE活動を適切に指導し、効果的な提案を作成するためのスキルを身につけることができます。
VEスペシャリスト
VEスペシャリストは、VE活動の中心的存在として、高度な専門技術と豊富な実務経験を有する専門家を認定する資格です。
複雑なプロジェクトにおいてVE手法を適切に適用し、組織全体のVE能力向上をリードする責任を担います。
この資格取得者は、VE理論の深い理解に加えて、実際のプロジェクトでの成功体験を積み重ねており、他のメンバーへの指導や教育も行える高い指導力を持っています。
企業におけるVE活動の戦略立案や推進において、なくてはならない存在です。
CVS(Certified Value Specialist)
CVSは、アメリカのVE協会との連携により認定される国際的な専門資格です。
世界水準のVE知識と卓越した実務能力を持つ専門家として、日米両国のVE協会に正式登録されます。
この資格は、グローバルスタンダードに対応したVE専門家としての地位を確立するもので、国際的なプロジェクトや海外企業との協働において、その専門性が高く評価されます。
建設業界のグローバル化が進む中で、ますます重要性が高まっている資格と言えます。
建築VE提案の事例
理論だけでなく、実際の建設現場でどのような成果が得られているのか、具体的な事例を通じて理解を深めましょう。
工期を短縮しコスト削減した事例
建築資材の価格高騰に悩んでいた建設会社において、工期短縮を通じたコスト圧縮を目標としたVE提案が実施されました。
この取り組みでは、現場で実際に作業に従事している職人や作業員からの意見を重視し、既存の施工手順について詳細な聞き取り調査を行います。
その結果、従来の作業工程には効率を阻害する要因が複数存在することが明らかになりました。
VE提案では、これらの非効率な部分を改善するため、施工手順の見直しと作業工程の最適化を図ります。
改善された工法により作業の効率性が向上し、結果として工期短縮を達成することができました。
この成果により、直接的な人件費削減効果に加え、作業従事者の負担軽減も実現できます。
また、現場スタッフの提案が実際に採用されたことで、職場の改善活動に対する積極性が高まり、労働災害の予防やミスの削減といった副次的な効果も生まれています。
入札不調を回避した事例
公共工事の入札参加において、提示価格の高さが原因で受注に至らないケースが続いていた建設業者の事例です。
従来の見積手法では競合他社との価格競争において優位性を確保することが困難でした。
そこで、機能や品質基準を満たしながらも経済性を向上させるVE提案の導入を決定します。
具体的な取り組みとして、使用材料の代替品検討や施工手法の変更、作業工程の見直しなどを総合的に実施しました。
これらの改善により、要求される性能や品質を維持したままでコストダウンを実現することができます。
この結果、入札での価格競争力が向上し、受注機会の拡大に繋がります。
民間工事においても同様のアプローチにより、複数社による競争入札において優位性を確保できるようになり、事業拡大の基盤を築くことができました。
VE提案の6つの手順
体系的で効果的なVE提案を実現するためには、明確な手順に従って進めることが重要です。
以下の6段階のプロセスを踏むことで、質の高い提案を作成できます。
①情報収集
成功するVE提案の基盤となるのが、包括的な情報収集です。
プロジェクトの要求仕様、予算制約、スケジュール要件、立地条件など、あらゆる関連情報を系統的に収集します。
この段階では、表面的な情報だけでなく、発注者の真の目的や潜在的なニーズの把握が重要です。
類似プロジェクトの実績、利用可能な技術や材料、法規制の制約なども詳細に調査し、提案の可能性を広く探ります。
情報の質と量が後の分析精度を決定するため、多方面からの情報収集が不可欠です。
②定義付け
収集した情報を基に、プロジェクトが真に求める機能と性能を明確に定義します。
表面的な要求だけでなく、その背景にある本質的な目的を理解し、達成すべき目標を具体化します。
この工程では、必要不可欠な機能と付加的な機能を明確に分類し、コスト削減の対象となり得る領域を特定します。
機能の定義が不十分だと適切な代替案を考案できないため、関係者との十分な議論を通じて共通認識を形成することが重要です。
③情報分析
定義された機能要件と収集情報を詳細に分析し、現状の課題と改善機会を特定します。
既存の設計や施工計画における非効率な部分を洗い出し、改善効果の大きさと実現可能性を総合的に評価しましょう。
分析過程では、品質への影響度、経済効果、技術的実現性、スケジュールへの影響などを多角的に検討し、最も効果的な改善領域を優先順位付けします。
定量的な分析手法を活用し、客観的な判断基準を設定することが重要です。
④クライアントへ提案
分析結果を基に、説得力のある提案書を作成します。
改善案の具体的内容、期待される効果、実現方法、リスク要因などを明確に整理し、発注者が適切な判断を下せるよう配慮しましょう。
提案書の作成では、公共工事等で定められた書式要件への準拠はもちろん、視覚的な分かりやすさや論理的な構成にも留意します。
技術的な説明だけでなく、経営的な観点からのメリットも明確に示すことが重要です。
⑤継続して検証
提案が採用され実際の施工が開始された後も、継続的な監視と検証が必要です。
提案した改善策が期待通りの効果を発揮しているか定期的に確認し、必要に応じて軌道修正を行います。
この段階では、現場からの報告や実測データを基に客観的な評価を実施し、当初の想定と異なる状況が発生した場合は迅速に対応策を検討します。
⑥最終評価
プロジェクト完了時には、VE提案の総合的な効果を評価し、次回の改善点を整理します。
コスト削減効果や品質への影響、工期短縮効果、副次的効果などを定量的に分析し、成功要因と改善点を明確化します。
評価結果は組織の知識資産として蓄積し、将来のプロジェクトでのVE活動の精度向上に活用します。
失敗事例も含めて率直に評価することで、組織全体のVE能力向上に繋げることが重要です。
VE提案のポイント
VE提案を成功に導くためには、戦略的な視点と実践的なアプローチの両方が必要です。
初期段階で導入する
VE提案の効果を最大限に引き出すためには、プロジェクトの早期段階での導入が重要です。
設計が固まってからでは変更の余地が限られるため、企画段階や基本設計段階での導入が理想的です。
早期導入により、根本的な設計変更や工法選択の自由度が確保され、より大きな改善効果を期待できます。
また、発注者との信頼関係構築の観点からも、プロジェクト初期からの積極的な提案姿勢は高く評価されます。
早期導入により、競合他社との差別化を図り、受注確率を向上させることも可能です。
現場の声を取り入れる
実効性の高いVE提案を作成するためには、設計者や管理者の視点だけでなく、実際の施工を担当する現場作業者の知見を積極的に活用することが不可欠です。
現場の職人や技能者は、日常的な作業を通じて既存工法の問題点や改善の余地を最も深く理解しています。
彼らの実務経験に基づいた提案は、実現可能性が高く、実際の効果も期待できます。
現場の声を効果的に収集するためには、定期的な意見交換会の開催、改善提案制度の整備、現場巡回による直接対話などの仕組みづくりが重要です。
また、提案が採用された場合の適切な評価により、現場からの積極的な協力を促すことも大切です。
まとめ
建築VE提案は、建設会社が厳しい競争を勝ち抜くための重要な武器となります。
ただコストを削るだけではなく、建物の品質や性能を保ちながら経済性を追求することで、お客様にも自社にもメリットをもたらす方法です。
プロジェクトの早い段階から取り組み、現場の声を大切にすることが、VE提案で成果を上げるための鍵となります。
また、VEリーダーやVEスペシャリストなどの資格を取得して専門知識を身につけ、決められた手順に沿って地道に改善を続けることが大切です。
建設業界の環境は今後も厳しくなることが予想されますが、VE提案を上手に活用すれば新しいビジネスチャンスを見つけられます。
会社全体でVEの考え方を共有し、常に改善を心がける文化を作ることが、長期的な成長に繋がるでしょう。