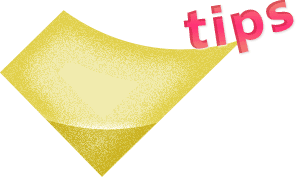
建築業界のリアルな情報や就職・転職活動で役立つ情報を紹介します。
2025.05.15
【2025年度版】一級建築士の大学別合格者数一覧!合格者発表までの流れも徹底解説
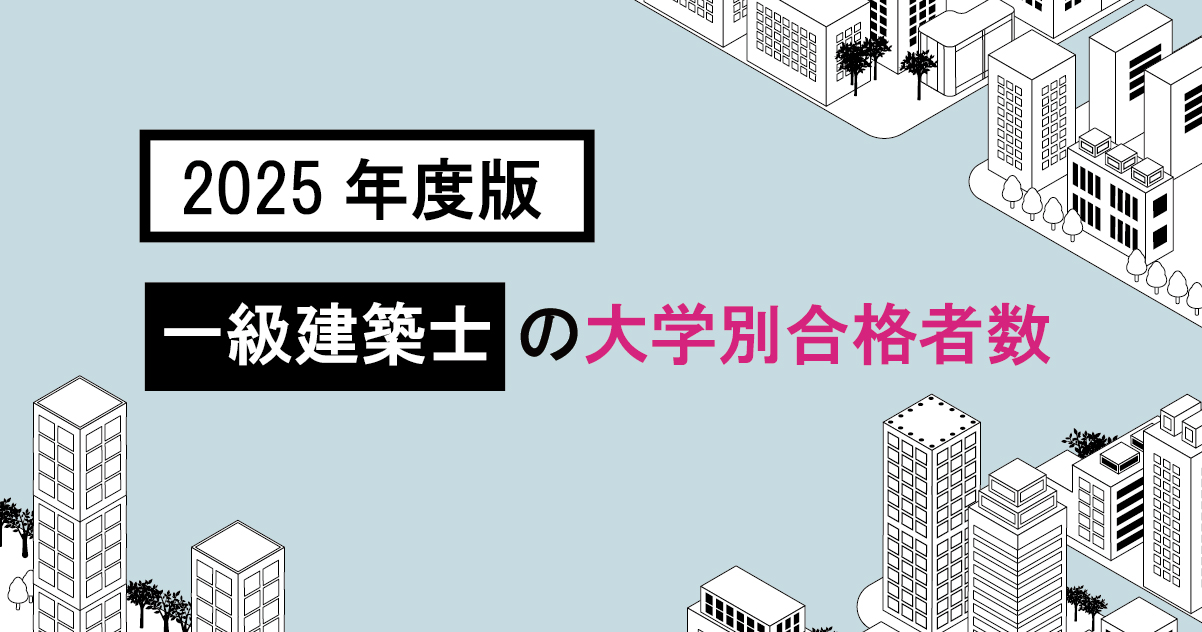
一級建築士は、建築業界で最も権威のある資格です。
一級建築士資格の取得は、建築キャリアにおける大きな転機となります。
本記事では、2025年度の一級建築士試験における大学別合格者数や合格者発表までの流れを徹底解説します。
これから受験を考えている方や、建築業界の動向に興味がある方にとって、貴重な情報源となるでしょう。

一級建築士になるための試験
一級建築士になるためには、「学科の試験」と「設計製図の試験」の両方に合格する必要があります。
この二段階方式は、建築の理論的知識と実践的なスキルの両方を評価するためのものです。
学科の試験
学科試験は例年7月に実施され、建築に関する幅広い知識を問う内容となっています。
試験は、学科Ⅰ「計画」、学科Ⅱ「環境・設備」、学科Ⅲ「法規」、学科Ⅳ「構造」、学科Ⅴ「施工」の5科目です。
試験形式は4択のマークシート方式で、合計125問が出題されます。
合格基準は各科目の得点が一定以上であることに加え、総得点も基準点を超える必要があります。
試験時間は計6時間30分で、朝から夕方までかかる長丁場の試験です。
学科試験の難易度は非常に高く、建築学を専門的に学んだ方でも、十分な準備期間と効率的な学習計画が必要とされます。
特に、実務経験が少ない方は、法規や施工など実務に直結する分野で苦戦することが多いでしょう。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「令和7年一級建築士試験案内」
設計製図の試験
学科試験に合格した後、10月に実施される設計製図試験に進むことができます。
この試験では、与えられた条件に基づいて建築物の設計図を作成します。
試験時間は6時間30分と長時間に及び、制限時間内に要求される全ての設計要素を含む図面を完成させる必要があるのです。
設計製図試験の特徴として、単に美しい建築を設計するだけではなく、法規制への準拠、構造的な安全性、機能性、そして経済性などを総合的に考慮した設計が求められます。
直近5年間の一級建築士試験結果
一級建築士試験の傾向を理解するためには、過去のデータを分析することが不可欠です。
直近5年間の試験結果を詳しく見ていきましょう。
受験者数・合格者数・合格率について
過去5年間の一級建築士試験の受験者数、合格者数、そして合格率の推移は以下の通りです。
| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 総合合格率 | ||
| 学科の試験 | 設計製図の試験 | 学科の試験 | 設計製図の試験 | ||
| 2024年 | 28,067人 | 11,306人 | 6,531人 | 3,010人 | 8.8% |
| 2023年 | 28,118人 | 10,238人 | 4,562人 | 3,401人 | 9.9% |
| 2022年 | 30,007人 | 10,509人 | 6,289人 | 3,473人 | 9.9% |
| 2021年 | 31,696人 | 10,499人 | 4,832人 | 3,765人 | 9.9% |
| 2020年 | 30,409人 | 11,035人 | 6,295人 | 3,796人 | 10.6% |
一級建築士試験の総合合格率は例年10%前後で推移しており、試験の難易度の高さが分かります。
出典:国土交通省「令和6年一級建築士試験「設計製図の試験」の合格者を決定」
学科の試験科目
学科の試験科目と出題数を見ていきましょう。
| 試験科目 | 出題数 |
| 学科Ⅰ「計画」 | 20問 |
| 学科Ⅱ「環境・設備」 | 20問 |
| 学科Ⅲ「法規」 | 30問 |
| 学科Ⅳ「構造」 | 30問 |
| 学科Ⅴ「施工」 | 25問 |
近年の出題傾向としては、単純な知識を問う問題だけでなく、実務での判断力や応用力を試す問題が増えています。
特に、建築基準法の改正点や最新の環境技術、建築設備の効率化など、時代の変化に対応した内容が重視されるようになっています。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「出題科目、出題数等」
設計製図の試験の課題について
設計製図試験の課題は毎年変わりますが、基本的には公共性の高い建築物や複合施設の設計が求められることが多いです。
過去5年間の課題を以下にまとめました。
| 年度 | 課題 |
| 2024年 | 大学 |
| 2023年 | 図書館 |
| 2022年 | 事務所ビル |
| 2021年 | 集合住宅 |
| 2020年 | 高齢者介護施設 |
設計製図の試験では、限られた時間内で効率的に作業を進める能力が試されています。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「(2)設計製図の試験の課題」
一級建築士「学科の試験」合格者の内訳
学科の試験の合格者内訳を様々な角度から分析することで、どのような人が合格しているのか、また自分の立ち位置を知る参考になります。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「試験合格者の主な属性」
学歴・資格別
学歴・資格別の合格者内訳は以下の通りです。
| 区分 | 割合 |
| 大学 | 67.4% |
| 二級建築士 | 20.7% |
| 専修学校 | 6.6% |
| 建築設備士 | 1.3% |
| その他 | 4.0% |
職務内容別
職務内容別の合格者内訳は、以下の通りです。
| 区分 | 割合 |
| 建築設計 | 39.3% |
| 施工管理・現場管理 | 21.3% |
| 構造設計 | 6.0% |
| 工事監理 | 5.0% |
| 学生・研究生 | 5.0% |
| その他 | 23.4% |
職域別
職域別の合格者内訳は、以下の通りです。
| 区分 | 割合 |
| 建築士事務所 | 26.9% |
| 建設業 | 35.4% |
| 官公庁等 | 6.1% |
| 住宅メーカー | 14.7% |
| 学生・研究生 | 5.3% |
| その他 | 11.6% |
男女別
男女別の合格者内訳は、以下の通りです。
| 区分 | 割合 |
| 男性 | 70.2% |
| 女性 | 29.8% |
年齢別
年齢別の合格者内訳は、以下の通りです。
| 区分 | 割合 |
| 23歳以下 | 16.0% |
| 24~26歳 | 29.0% |
| 27~29歳 | 16.2% |
| 30~34歳 | 15.2% |
| 35~39歳 | 8.7% |
| 40歳以上 | 14.9% |
一級建築士「設計製図の試験」合格者の内訳
設計製図の試験の合格者内訳についても詳しく見ていきましょう。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「試験合格者の主な属性」
学歴・資格別
学歴・資格別の合格者内訳は以下の通りです。
| 区分 | 割合 |
| 大学 | 74.6% |
| 二級建築士 | 15.8% |
| 専修学校 | 5.0% |
| 建築設備士 | 1.1% |
| その他 | 3.5% |
職務内容別
職務内容別の合格者内訳は、以下の通りです。
| 区分 | 割合 |
| 建築設計 | 38.0% |
| 施工管理・現場管理 | 20.4% |
| 構造設計 | 8.8% |
| 工事監理 | 4.9% |
| 行政 | 4.7% |
| その他 | 23.2% |
職域別
職域別の合格者内訳は、以下の通りです。
| 区分 | 割合 |
| 建築士事務所 | 26.9% |
| 建設業 | 37.5% |
| 官公庁等 | 6.2% |
| 住宅メーカー | 14.1% |
| 不動産業 | 4.4% |
| その他 | 10.9% |
男女別
男女別の合格者内訳は、以下の通りです。
| 区分 | 割合 |
| 男性 | 69.3% |
| 女性 | 30.7% |
年齢別
年齢別の合格者内訳は、以下の通りです。
| 区分 | 割合 |
| 23歳以下 | 12.1% |
| 24~26歳 | 33.9% |
| 27~29歳 | 21.7% |
| 30~34歳 | 16.9% |
| 35~39歳 | 7.4% |
| 40歳以上 | 8.1% |
大学別
大学別の合格者内訳は、以下の通りです。
| 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 | 学校名 | 合格者数 |
| 日本大学 | 142人 | 京都建築大学校 | 27人 | 日本女子大学 | 15人 |
| 東京理科大学 | 103人 | 金沢工業大学 | 27人 | 北海道科学大学 | 14人 |
| 近畿大学 | 92人 | 三重大学 | 27人 | 北九州市立大学 | 14人 |
| 芝浦工業大学 | 84人 | 東京都立大学(首都大学東京) | 27人 | 愛知産業大学 | 13人 |
| 早稲田大学 | 66人 | 横浜国立大学 | 26人 | 佐賀大学 | 13人 |
| 工学院大学 | 61人 | 大阪大学 | 26人 | 東北工業大学 | 13人 |
| 神戸大学 | 54人 | 東北大学 | 25人 | 福井大学 | 13人 |
| 明治大学 | 52人 | 立命館大学 | 25人 | 宇都宮大学 | 12人 |
| 名古屋工業大学 | 45人 | 広島大学 | 23人 | 前橋工科大学 | 12人 |
| 法政大学 | 43人 | 愛知工業大学 | 22人 | 大阪工業技術専門学校 | 12人 |
| 京都大学 | 42人 | 北海道大学 | 22人 | 中央工学校 | 12人 |
| 名城大学 | 41人 | 神奈川大学 | 20人 | 東海工業専門学校金山校 | 12人 |
| 関西大学 | 40人 | 広島工業大学 | 19人 | 武庫川女子大学 | 12人 |
| 九州大学(九州芸術工科大学) | 39人 | 青山製図専門学校 | 19人 | 山口大学 | 11人 |
| 東京都市大学(武蔵工業大学) | 38人 | 名古屋大学 | 19人 | 修成建設専門学校 | 11人 |
| 京都工芸繊維大学 | 37人 | 大分大学 | 18人 | 仙台高等専門学校 | 11人 |
| 東海大学 | 37人 | 福岡大学 | 18人 | 関東学院大学 | 10人 |
| 大阪工業大学 | 34人 | 摂南大学 | 17人 | 岐阜工業高等専門学校 | 10人 |
| 東京大学 | 32人 | 慶應義塾大学 | 16人 | 九州工業大学 | 10人 |
| 千葉大学 | 31人 | 鹿児島大学 | 16人 | 公立大学法人名古屋市立大学 | 10人 |
| 東京科学大学(東京工業大学) | 31人 | 新潟大学 | 16人 | 秋田県立大学 | 10人 |
| 東洋大学 | 31人 | 日本工業大学 | 16人 | 奈良女子大学 | 10人 |
| 東京電機大学 | 30人 | 熊本大学 | 15人 | 豊橋技術科学大学 | 10人 |
| 信州大学 | 29人 | 室蘭工業大学 | 15人 | 琉球大学 | 10人 |
| 大阪市立大学 | 28人 | 千葉工業大学 | 15人 |
合格者発表までの流れ
一級建築士試験の合格までには、一定の流れがあります。
この章では、学科の試験から受験する場合と、すでに学科の試験に合格して設計製図の試験から受験する場合の両方について説明します。
「学科の試験」から受験する場合
「学科の試験」から受験する場合の合格者発表までの流れは、以下の通りです。
①受験申し込み
一級建築士試験の受験申し込みは、例年4月頃に行われます。
申し込みには受験資格を証明する書類(卒業証明書や二級建築士免許証明書など)の提出が必要です。
申し込みはオンラインで行うことが可能で、受験手数料は17,000円となっています。
出典:公益財団法人 建築技術教育普及センター「初めて受験申込する方が準備するもの」
②受験資格の判定・受験資格者の確定
提出された書類を基に、受験資格の有無が判定されます。
資格審査の結果は6月上旬頃に通知され、合わせて受験票が送付されます。
③「学科の試験」を実施
学科の試験は、7月の第4日曜日に全国の試験会場で一斉に実施されます。
④「学科の試験」の合格者を発表
学科の試験の結果は、9月上旬に発表されます。
合格者には設計製図試験の受験票が送付されます。
不合格者には成績通知書が送付され、次年度の参考にすることができます。
⑤「設計製図の試験」を実施
学科試験に合格した受験者は、10月の第2日曜日に設計製図の試験を受験します。
試験時間は6時間30分で、試験では専用の用紙に手書きで設計図を作成することが求められます。
⑥合格者発表
最終的な合格者発表は12月下旬に行われます。
合格者には合格証書が送付され、一級建築士として登録する権利を得ることができます。
登録は合格後の任意の時期に行うことができますが、登録しなければ一級建築士を名乗ることはできません。
「設計製図の試験」から受験する場合
過去に学科の試験に合格しているが設計製図の試験に不合格だった場合、または、学科試験の合格が有効な期間内(合格した年を含めて5年間)である場合は、設計製図の試験からの受験が可能です。
①受験申し込み
設計製図の試験のみを受験する場合も、申し込みは4月頃に行います。
②「設計製図の試験」を実施
設計製図の試験は、10月の第2日曜日に実施されます。
試験内容や時間は、学科試験から受験する場合と同様です。
③合格者発表
合格者発表は12月下旬に行われます。
結果通知や登録手続きも、学科試験から受験する場合と同様です。
まとめ
一級建築士試験は合格率が10%前後で難易度が非常に高いです。
しかし、適切な準備と効率的な学習計画を立てることで、合格の可能性は十分にあります。
一級建築士試験は、建築系大学出身で設計業務に従事している20代の受験者が最も高い合格率を示しています。
一方で、様々な学歴や職業背景を持つ受験者も合格していることから、自分の強みを活かした対策を立てることが重要です。
また、大学別の合格者数内訳を見ると、旧帝大や有名私立大学の建築学科が上位を占めていますが、それ以外の大学からも多くの合格者が輩出されています。
大学のカリキュラムや先輩からのアドバイスを活用することも、合格への近道となるでしょう。






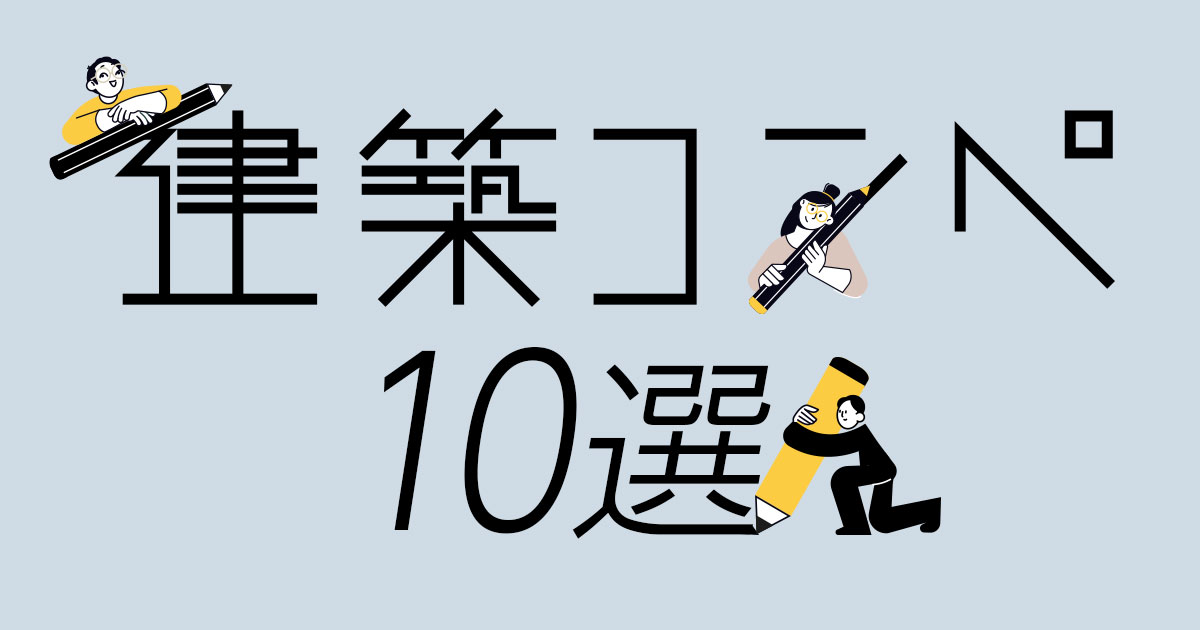




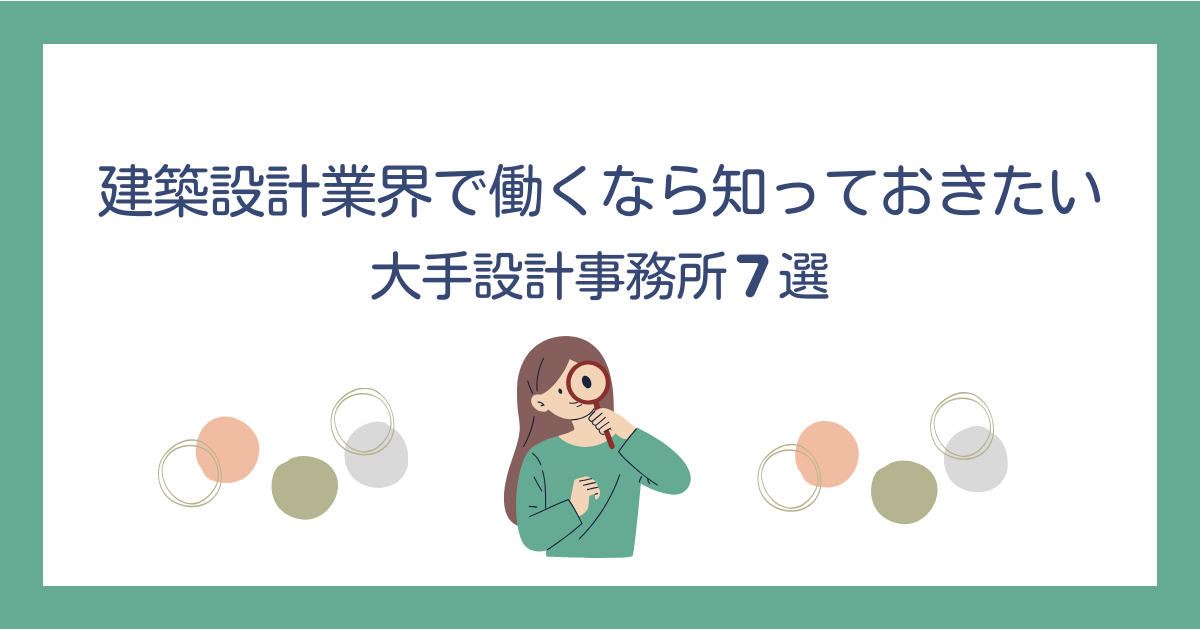
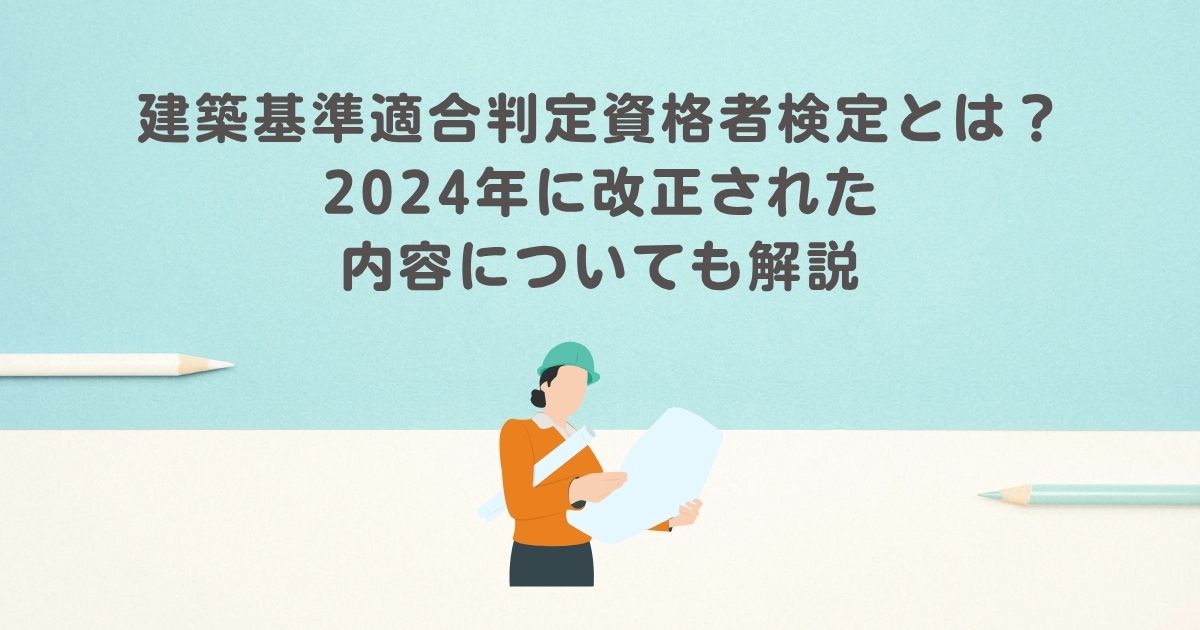
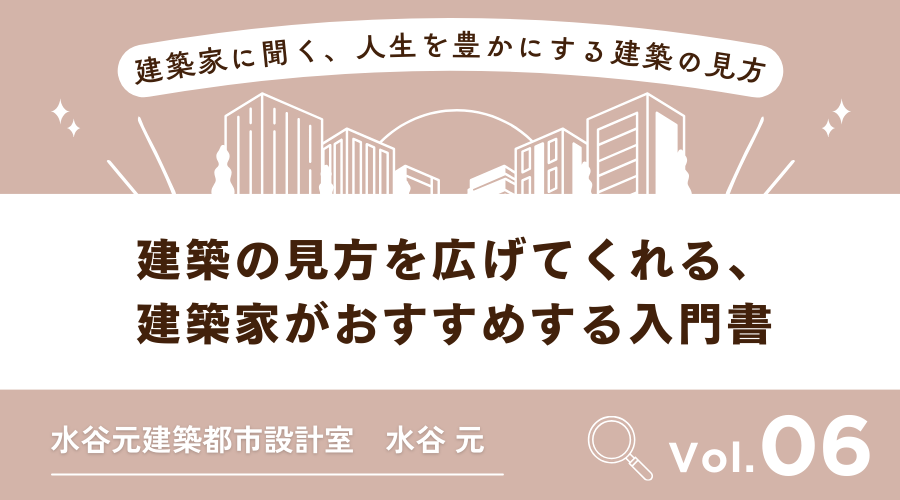
.jpg)
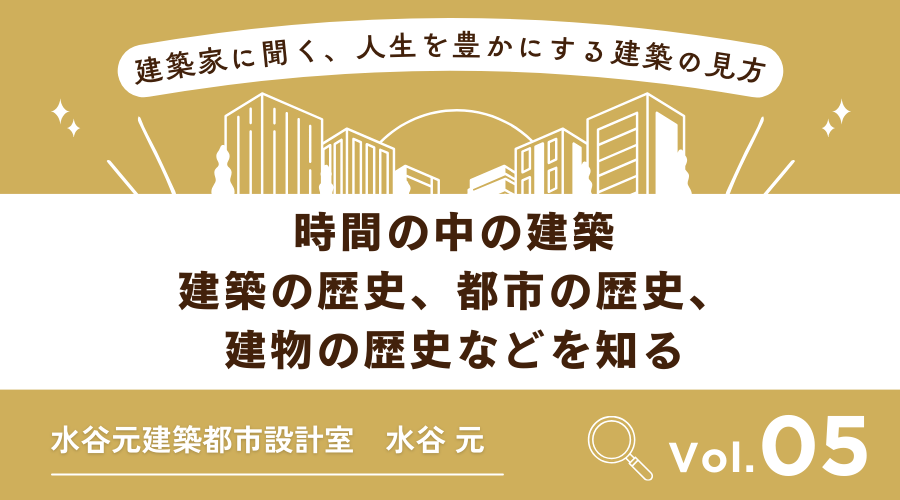
.jpg)