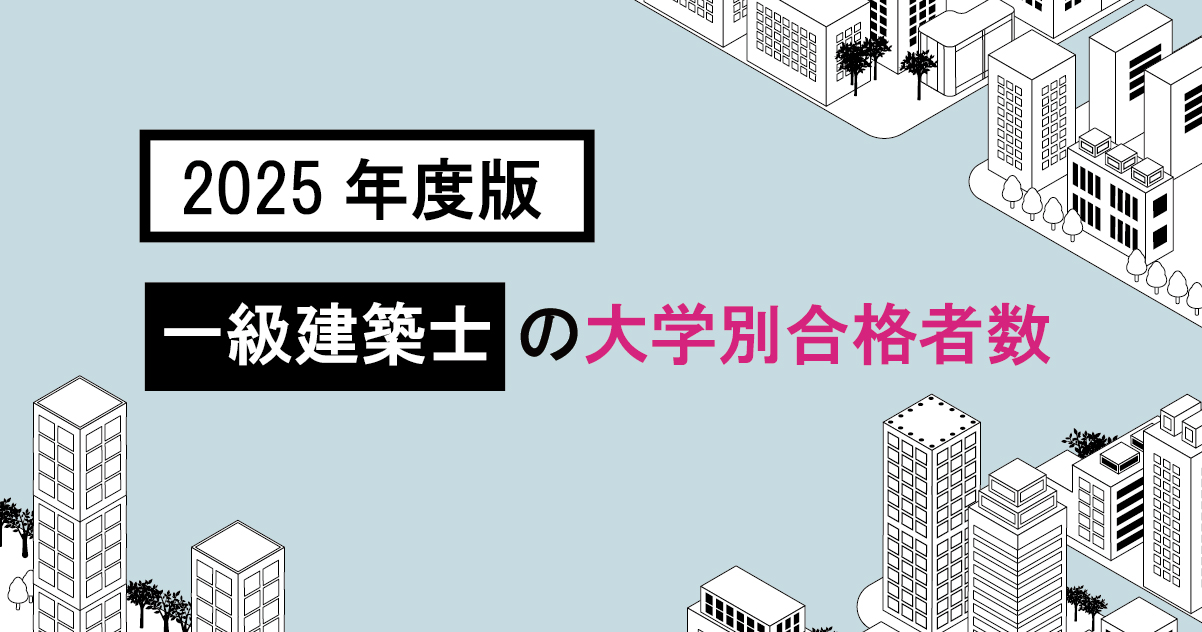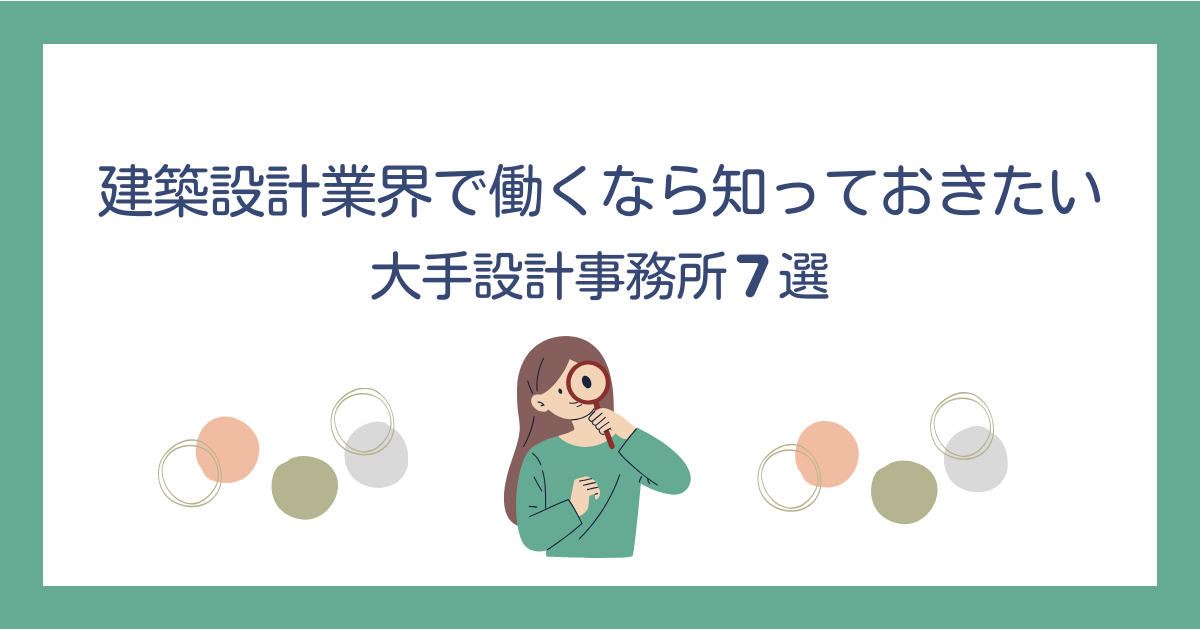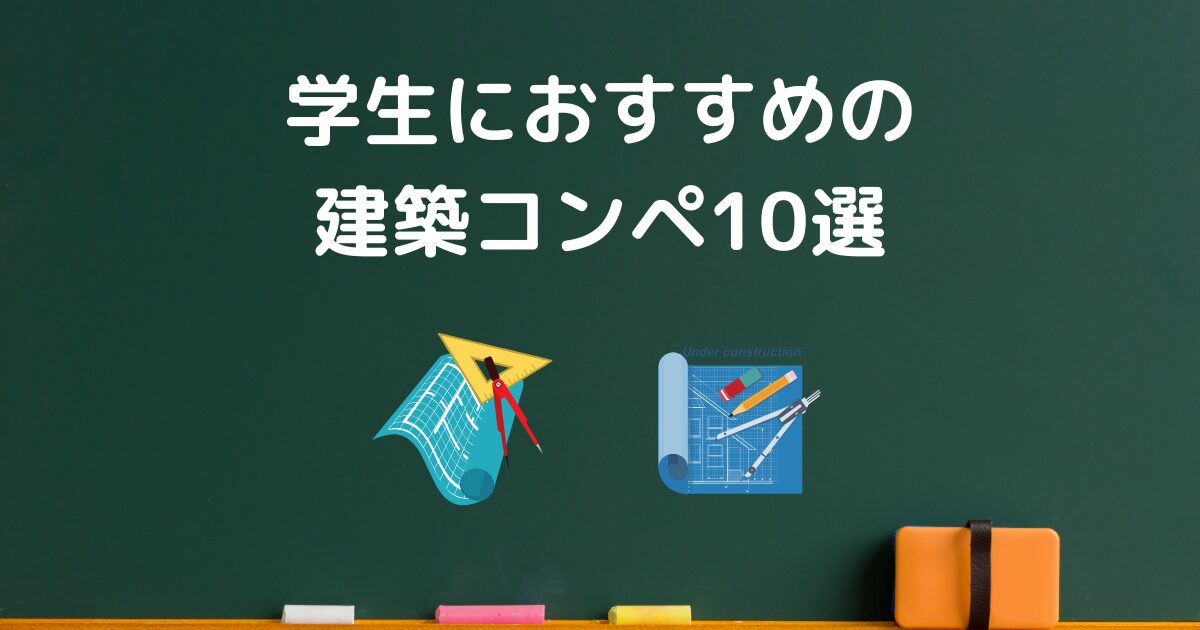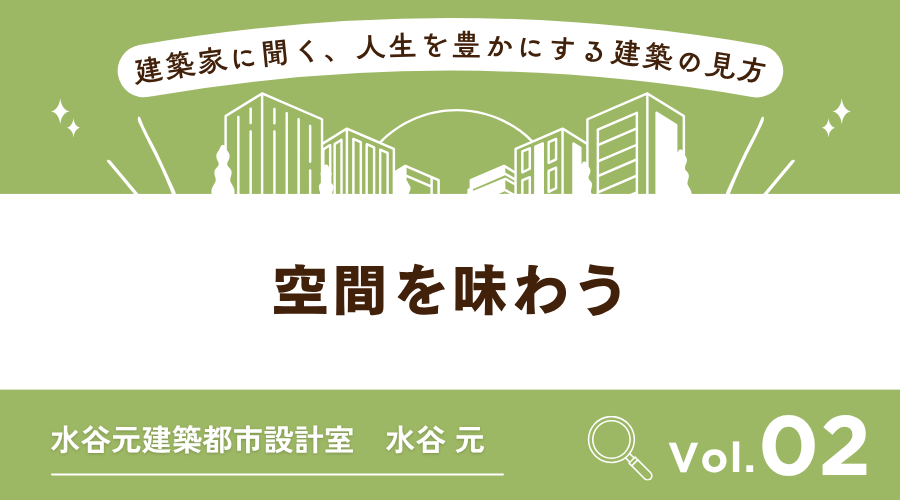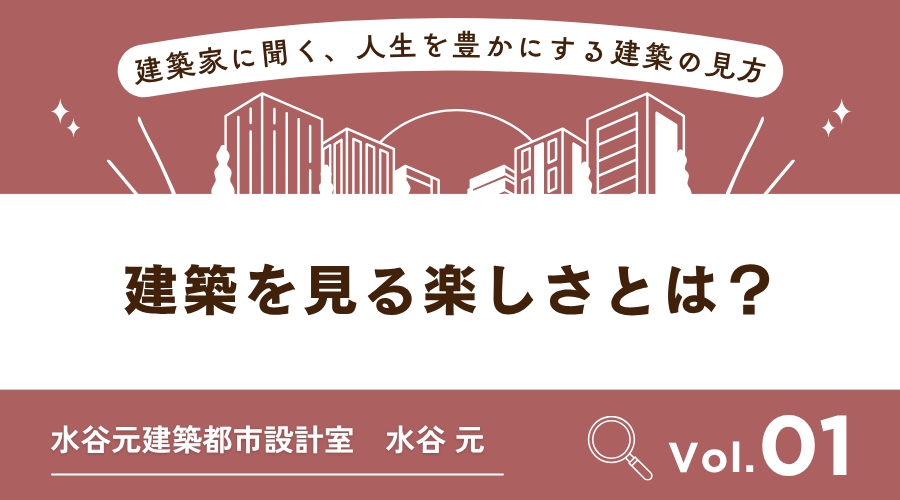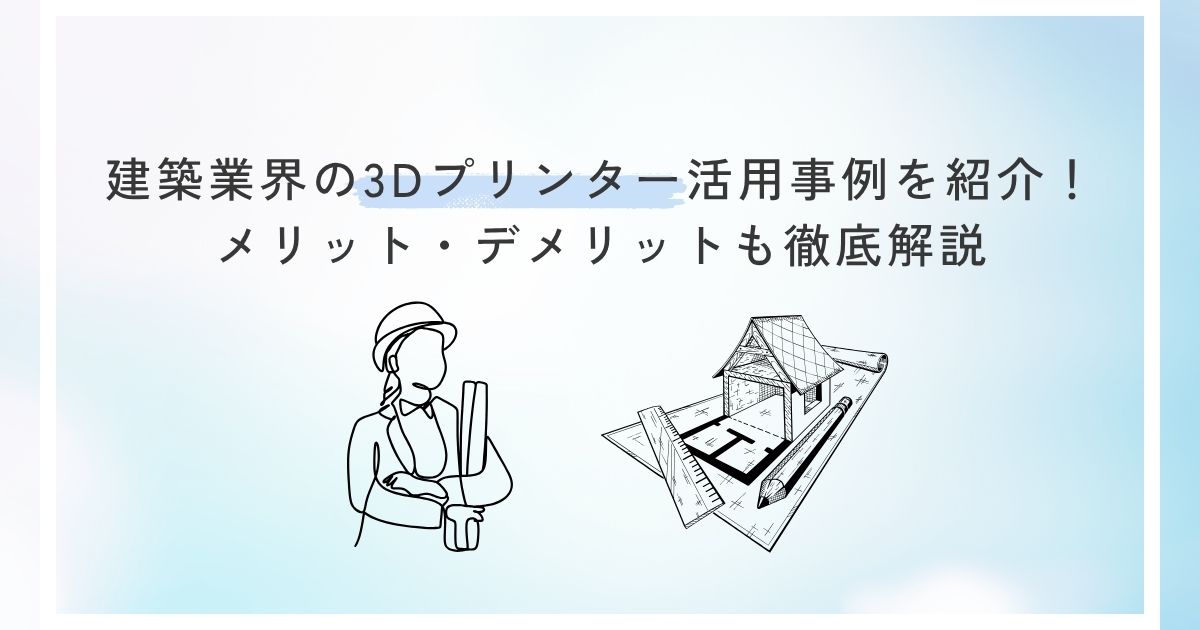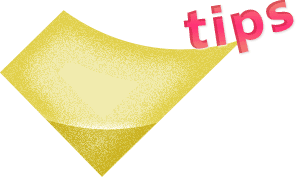
建築業界のリアルな情報や就職・転職活動で役立つ情報を紹介します。
2025.04.10
BIMの人気ソフトとは?BIMを活用するメリットも解説!

BIMとは建築情報モデリング(Building Information Modeling)の略で、建築物のデジタル設計・管理を可能にする革新的な技術です。
近年、建設業界ではBIMの導入が進み、多くの専門家が様々なBIMソフトを活用しています。
本記事では、BIMの人気ソフトと、BIMを活用することで得られる具体的なメリットについて詳しく解説します。

BIMとは
BIM(Building Information Modeling)は、建築物の3次元モデルにあらゆる建築情報を統合する設計手法です。
従来の図面作成ツールと異なり、BIMでは建物の形状や寸法だけでなく、材料特性、コスト、工程、エネルギー性能などの情報も一元管理できます。
つまり、単なる3Dモデルではなく、建築物のライフサイクル全体をデジタルで表現する「情報の統合プラットフォーム」なのです。
設計段階から施工、維持管理、解体に至るまで、建物に関わるすべての情報を1つのモデルに集約することで、建設プロジェクト全体の効率化と品質向上が実現します。
BIMは建築業界における中核技術として、世界中で急速に普及しています。
CADとの違い
CADとBIMの最も大きな違いは「情報量」にあります。
CADは主に図面作成ツールとして発展し、線や面といった幾何学的要素を用いて建物を表現します。
一方、BIMでは壁や窓などの建築部材それぞれに物理的特性や属性情報が付与されています。
例えば、壁をCADで描くと単なる平行線ですが、BIMでは厚さ、素材、断熱性能などの情報を持った壁として扱われます。
また、CADでは各図面が独立しているため、設計変更の際には複数の図面を手作業で修正する必要があります。
しかし、BIMではモデルを変更すると関連するすべての図面が自動的に更新されます。
このような違いから、CADが「描く」ツールであるのに対し、BIMは「構築する」ツールと言えるでしょう。
BIMを活用するメリット
BIMを活用するメリットは、以下の通りです。
・完成形をイメージしやすくなる
・効率的に設計変更できる
・具体的にシミュレーションできる
・完成したBIMモデルを再利用できる
BIMを活用するメリットを把握しておくことで、BIMの良さを最大限発揮できます。
完成形をイメージしやすくなる
BIMの最大のメリットの1つは、プロジェクトの初期段階から完成形を視覚的に把握できることです。
従来の2D図面では専門家でも完成イメージを正確に捉えることが難しい場合がありました。
しかし、BIMでは3Dモデルを通じて誰でも直感的に建物を理解できます。
これにより、施主とのコミュニケーションがスムーズになり、設計の意図を明確に伝えることが可能になります。
また、完成前に仮想空間で建物内を歩き回る「ウォークスルー」も実現でき、実際の使用感や空間の広がりを体験できます。
この視覚化能力によって、設計段階での認識の齟齬を減らし、後工程での手戻りを大幅に削減することができるのです。
効率的に設計変更できる
BIMでは設計変更が驚くほど効率的に行えます。
従来のCADでは、1箇所の変更が他の図面に与える影響を設計者が1つずつ確認し、手作業で修正する必要がありました。
しかしBIMでは、モデル内のある要素を変更すると、関連するすべての図面、数量表、スケジュールなどが自動的に更新されます。
例えば、壁の位置を移動させると、平面図だけでなく立面図、断面図、さらには材料表や面積計算にも即座に反映されるのです。
これにより、設計変更にかかる時間と労力が大幅に削減され、より多くの設計案を検討する余裕が生まれます。
また、ミスも減少し、設計品質の向上にもあ繋がります。
具体的にシミュレーションできる
BIMの強力な機能の1つが、様々な側面におけるシミュレーション能力です。
日照・採光シミュレーションでは、季節や時間帯によって建物内にどのように光が差し込むかを可視化でき、最適な窓の配置や日よけの設計が可能になります。
また、空調シミュレーションでは熱の流れや空気の循環を予測し、快適な室内環境と省エネルギー性を両立する設計ができます。
さらに、構造解析や避難経路のシミュレーションも行え、安全性の高い建物設計に貢献します。
こうしたシミュレーションによって、実際に建設する前に問題点を発見し、コストをかけずに設計を最適化できることがBIMの大きなメリットです。
完成したBIMモデルを再利用できる
BIMモデルの価値は設計・施工段階だけでなく、建物の完成後も継続します。
完成したBIMモデルには、建物のあらゆる情報が詰まっているため、施設管理のデータベースとして活用できます。
例えば、設備の交換時期の管理や修繕計画の策定、エネルギー使用の最適化などに役立てることが可能です。
また、将来のリノベーションや増築の際には、詳細な建物情報がすでにデジタル化されているため、設計作業が効率化されます。
さらに、類似プロジェクトの設計時にはテンプレートとして再利用でき、新たな設計作業の時間を短縮できます。
このように、BIMモデルは建物のライフサイクル全体を通じて価値を生み出し続けるのです。
BIMの人気ソフト5選
ここからはBINの人気ソフト5選を紹介します。
1.Revit
2.Archicad
3.GLOOBE
4.VectorWorks
5.Rebro
それぞれ特徴が異なるため、自分に合ったBIMソフトを選びましょう。
①Revit
Autodesk社が開発する「Revit」は、世界的に最もシェアの高いBIMソフトです。
建築、構造、設備を統合的に扱える総合的なBIMプラットフォームとして、大規模プロジェクトから小規模案件まで幅広く対応します。
Revitの最大の特徴は、他のAutodesk製品(AutoCADなど)との連携のしやすさにあります。
また、豊富なライブラリと拡張機能が用意されており、ユーザー独自のワークフローに合わせたカスタマイズが可能です。
英語版が基本ですが日本語版も提供されており、国内でも設計事務所や建設会社を中心に広く採用されています。
世界標準のソフトウェアであるため、海外プロジェクトや国際的な協業にも適しています。
②Archicad
Graphisoft社の「Archicad」は、建築専門のBIMソフトとして30年以上の歴史を持ち、直感的なインターフェースと操作性の良さで多くの建築家に支持されています。
3Dモデリングの精度が高く、美しいレンダリング機能を備えているため、デザイン重視の設計事務所に特に人気があります。
Archicadの特徴的な機能として「BIMx」があり、クライアントにモデルを共有する際に専門知識がなくても閲覧・操作できるビューアを提供できます。
また、「Teamwork」という独自の共同作業環境によって、複数のデザイナーが同時に1つのプロジェクトに取り組むことが可能です。
日本語サポートも充実しており、国内の中小規模の建築事務所を中心に広く使われています。
③GLOOBE
福井コンピュータアーキテクト社の「GLOOBE」は、日本の建築基準や設計プロセスに特化した国産BIMソフトです。
日本の建築実務に合わせた独自の機能が多く、例えば確認申請や構造計算に必要な図面・資料の作成を効率的に行えます。
また、自動伏図作成や日本の部材・仕上げ材のライブラリが充実しており、国内のBIM初心者にも扱いやすいのが特徴です。
GLOOBEの操作性や機能は、日本の設計者視点で開発されています。
そのため、日本の建築業界の慣習や法規に対応した作図が可能で、国内の設計事務所に広く導入されているのです。
④VectorWorks
A&A社の「VectorWorks」は、建築設計だけでなく、造園、舞台デザイン、プロダクトデザインなど幅広い分野で使われる汎用性の高いBIMソフトです。
特に、「VectorWorks Architect」が建築BIM向けのバージョンとして人気があります。
CADとしての使いやすさとBIMの機能を両立させており、2D作図からBIMへのステップアップが比較的容易なソフトとして知られています。
操作性が直感的で学習曲線が緩やかなため、個人事務所や中小規模の設計事務所に広く採用されているのです。
また、Macでも動作する数少ないBIMソフトウェアとしても評価されており、デザイン系の事務所でも人気があります。
日本語サポートも充実しており、国内での利用者も多いのが特徴です。
⑤Rebro
NYKシステムズ社の「Rebro」は、設備設計に特化したBIMソフトです。
空調、衛生、電気などの設備設計を3次元で行うことができます。
配管やダクト、電気配線などを3Dで配置し、干渉チェックや数量拾いなどを効率的に行える点が大きな特徴です。
特に、複雑な設備ルートの検討や、限られたスペースでの設備計画に威力を発揮します。
また、建築や構造のBIMモデルとの連携も可能で、総合的な建物情報モデルの1部として設備モデルを統合できます。
Rebroは、国内の設備設計事務所や建設会社の設備部門で広く採用されており、日本の設備設計の標準的なBIMです。
操作性や機能は、日本の設備設計者の視点で開発されているため、使いやすさも高評価を得ています。
BIMソフトの選び方のポイント
BIMソフトの選び方のポイントは、3つあります。
・予算で選ぶ
・用途で選ぶ
・周囲の環境で選ぶ
それでは、1つずつ見ていきましょう。
予算で選ぶ
BIMソフトの導入において、予算は重要な選定基準の1つです。
BIMソフトの価格は、製品によって大きく異なります。
また、導入時にはソフトウェア本体だけでなく、対応するハードウェアのアップグレード費用や、スタッフのトレーニング費用も考慮すべきです。
小規模事務所の場合は、初期投資を抑えられるクラウドベースのBIMソリューションや、機能を絞った廉価版の検討も選択肢となるでしょう。
用途で選ぶ
BIMソフトの選定では、具体的な使用目的や業務内容に応じた機能の評価が不可欠です。
例えば、意匠設計中心の事務所であれば、デザイン表現力やレンダリング機能が充実したArchicadやVectorWorksが適しているでしょう。
構造設計に重点を置く場合は、Revitとその構造解析プラグインの組み合わせが強みを発揮します。
また、設備設計専門ならRebroのような専門特化型ソフトの方が効率的です。
プロジェクトの規模も重要で、大規模プロジェクトの場合はチーム連携機能や外部システム連携が充実したRevitのようなプラットフォームが適しています。
最終的には、自社の主要業務プロセスにおいて最も効率化が図れるソフトを選ぶことが成功の鍵となります。
周囲の環境で選ぶ
BIMソフトの選定では「エコシステム」の考慮も重要です。
つまり、連携する協力事務所や取引先、元請けなどが使用しているソフトとの互換性やデータ交換のしやすさを検討する必要があります。
例えば、主要クライアントがRevitを使用している場合、同じソフトを採用することでデータのやり取りがスムーズになります。
また、地域や業界によって主流のBIMソフトが異なることもあるため、地域の傾向も考慮に入れるべきでしょう。
さらに、サポート体制や技術者の採用のしやすさも重要な要素です。
普及率の高いソフトであれば、操作できる人材の確保やトラブル時のサポートが受けやすくなります。
特に日本国内では、日本語サポートの充実度や日本の建築業界の慣習に合ったサポート体制があるかどうかも選定の重要なポイントとなります。
補助金を使えば安くBIMを導入できる
BIMの導入には初期費用がかかりますが、国や自治体の補助金・助成金を活用することで負担を軽減できます。
特に注目すべきは、国土交通省の「BIM導入・活用に向けた取組への支援事業」です。
この事業では、中小建設業者や設計事務所がBIMを導入する際の費用の1部を補助しています。
また、経済産業省の「IT導入補助金」もBIMソフトの導入に適用できる場合があります。
これらの補助金は導入費用の最大半額程度をカバーするものもあり、大きな負担軽減になります。
補助金の申請には条件や期限があるため、最新情報の確認が必要です。
将来的な業務効率化とコスト削減を見据えた投資として、補助金を賢く活用しましょう。
BIMに関連した資格
最後に、BIMに関連した資格を解説します。
・一般社団法人日本BIM協会「BIM資格認定試験」
・一般社団法人コンピュータ教育振興協会「BIM利用技術者試験」
・Autodesk「Revit Architectureユーザ試験」
・Graphisoft「Archicad認定試験」
BIM関連の資格を持っていれば、就職や転職において有利になります。
一般社団法人日本BIM協会「BIM資格認定試験」
一般社団法人日本BIM協会が実施する「BIM資格認定試験」は、国内でBIMに関する知識と技能を証明する代表的な認定制度です。
この試験はBIMの基礎知識から実務応用まで幅広く問われ、BIMマネージャー、BIMコーディネーター、BIMオペレーターなど、役割に応じた複数のグレードが設定されています。
試験は年に数回実施され、合格者には認定証が発行されます。
この資格は建設業界でのキャリアアップや転職に有利に働くだけでなく、BIMを導入する企業にとって社内の技術力証明にもなります。
受験資格には実務経験などの条件があるため、協会のウェブサイトで最新情報を確認するのがおすすめです。
一般社団法人コンピュータ教育振興協会「BIM利用技術者試験」
一般社団法人コンピュータ教育振興協会(ACSP)が主催する「BIM利用技術者試験」は、BIMを実務で活用するための知識と技能を体系的に評価する認定試験です。
特定のソフトウェアの操作スキルではなく、BIMの概念理解や活用方法など、より普遍的な知識が問われるのが特徴です。
ペーパーテストとCAD操作の実技試験の両方が含まれており、実践的な評価が行われます。
この資格は建設・設計業界での就職や昇進に役立つほか、BIMを新たに学ぶ方にとって学習の指針となるカリキュラムが整備されています。
未経験者でも取得可能な入門レベルの認定から始められるため、BIMキャリアのスタートとして最適な資格の1つです。
Autodesk「Revit Architectureユーザ試験」
Autodesk社が提供する「Revit Architectureユーザ試験」は、世界的に普及しているBIMソフトウェア「Revit」の操作スキルを証明する国際認定資格です。
この試験はRevitの基本操作から高度な活用方法まで、実務で必要なスキルを評価します。
Revitは世界中の建設プロジェクトで使用されているため、この資格は国際的な通用性があり、グローバルに活躍したいBIM技術者には特に有用です。
Graphisoft「Archicad認定試験」
Graphisoft社が提供する「Archicad認定試験」は、建築家に人気のBIMソフト「Archicad」の操作スキルを証明する専門資格です。
試験内容はArchicadの基本操作から高度なモデリング技術、BIMワークフローの最適化まで幅広く、実務での活用力が問われます。
日本でも日本語での受験が可能で、Graphisoftの日本法人であるA&A社が試験を実施しています。
合格者にはデジタル認定証が発行され、Archicadユーザーのコミュニティでの活動や就職活動において自身のスキルをアピール可能です。
まとめ
本記事では、BIMの人気ソフトについて解説しました。
BIMの人気ソフトは、以下の通りです。
1.Revit
2.Archicad
3.GLOOBE
4.VectorWorks
5.Rebro
予算や用途、周囲の環境でBIMソフトを選びましょう。