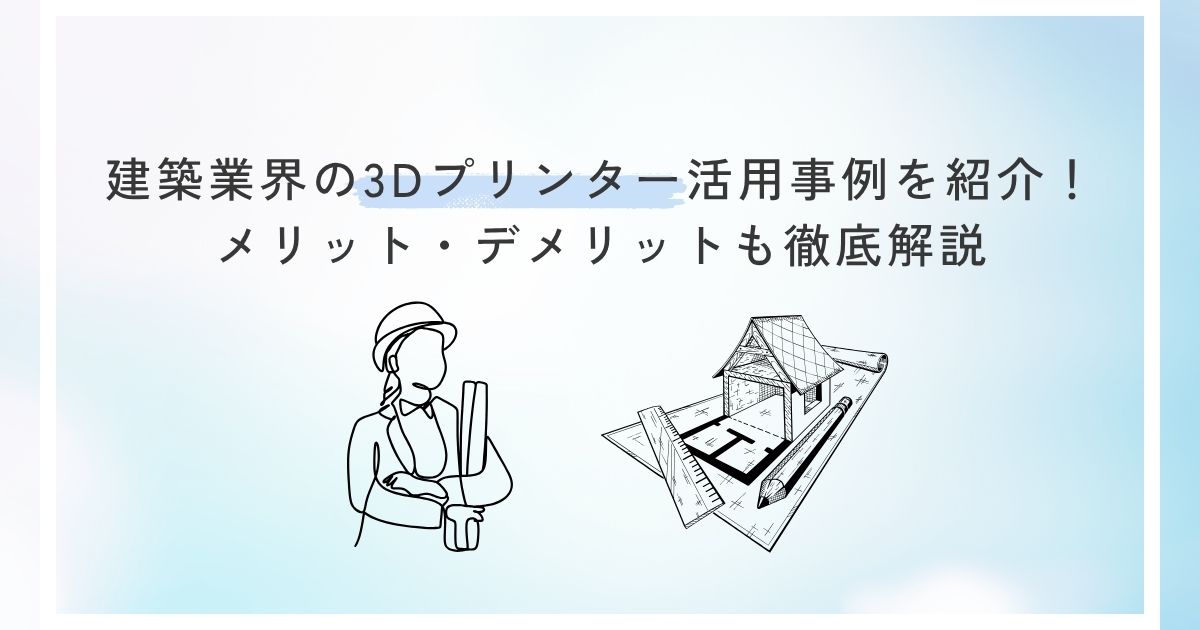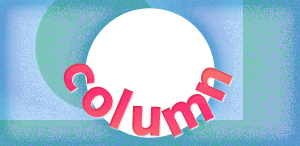
人生の指針となるようなインタビューや、スキマ時間にお楽しみいただけるコラムを紹介します。
2025.04.18
建築設計と働く喜び ── 第2回 江島史華
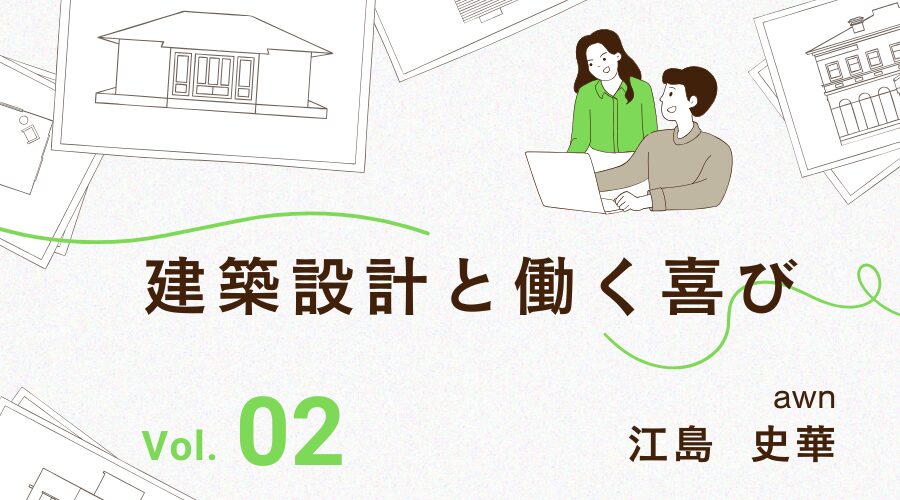
建築人を豊かにすることを目指すA-magazineが、建築設計に携わる人びとが建築設計のどのような点に働く喜びを見出しているのかをシリーズで紹介する”建築設計と働く喜び”。連載第2回はアトリエ系の建築設計事務所に所属しながら、個人でも作品を発表している江島史華さんに寄稿していただきました。
======
awn/architecture workshop networkに所属して設計活動をしている江島史華です。
2016年に横浜国立大学大学院Y-GSAを卒業し、当時Y-GSAの校長だった北山恒さんの主宰する旧architecture WORKSHOPへ入社しました。2021年にCOVID-19をきっかけに事務所がarchitecture WORKSHOP→awnへ組織改編を行うことになり、それ以降はパートナーとして参画しています。
今日はわたしがなぜ建築設計という職業をえらび、日々何を考え、建築設計を通して何を目指しているのか、書いてみようと思います。
共同するたのしさ
わたしの所属するawnには、
arcitecture=生活を支える建築 workshop=共同作業所 network=自在な組織
という意味があります。
生活を支える建築とは、権力装置や経済の道具としての建築ではなく、人間が主体となる建築を目指しているということです。近しい建築思想をもったメンバーが集まり、共同して建築を考えることを大事にしています。わたしが個人での独立のかたちをとらず、パートナーとしてawnに所属し続けている理由のひとつに、共同する楽しさがあります。図面や模型をもとに、メンバーがわっと集まって議論や対話や雑談を繰り返す中で、設計案が大きくドライブする瞬間があります。複数の意思を持ち寄ることで、ひとりの考えでは到達できない、思いもよらないところに着地すること。それによって、建築が単一の理論だけでは語れない複雑さをもつこと。それこそが、次の時代の建築のつくり方なのではないかと期待して、設計を続けています。
また、自在な組織という点で、新しい設計事務所のあり方を模索している最中でもあります。中核となる組織は最低限の人数で運営し、仕事の規模に応じて外部パートナー(主に事務所のOBOG)とネットワークを組む、組織の輪郭が無いような柔軟なかたちをとっています。働き方や組織のデザインをすることも、建築に対する試行錯誤のひとつではないかと考えています。
生き続ける建築
建築設計を生業にしていると、日々、膨大な考え事の中に浸り続けることになります。それも、目の前の材料同士の接合から、社会を規定する大きな制度、施主の要求、明日の天気、地域固有の歴史や文化、構造力学や哲学、経済、心理学、etc……激しくスケールを横断し続けながら、時代が求める新しい建築の姿を構想します。建築はある程度の時間を必要とする行為なので、わたしが扱う規模だと、短くても1年、通常は数年かけて竣工に向かうことになります。そんな風に時間をかけて、寝ても覚めても建築を考え続けることは、その建築の大きさに関わらず、まるで世界の一部をつくる行為のようにも感じます。
そのようにしてようやく実体として建ち現れた建築は、施主に引き渡された後、場合によっては生命スパンを超えてこの世界に建ち続けることになります。この、建築家にとっての竣工が建築にとってははじまりに過ぎないという事実が、建築の最も創造的な部分ではないかと思います。建築家の手を離れ、施主という自由な存在が建築を乗っ取り、ダイナミックに使い倒していくことで建築が生きはじめる。建築家の思惑を超えた先に建築の面白さがあります。
設計する建築が、人の行動を制限したり限定する存在ではなく、多様な状況を受け止める柔軟性を持つ存在であってほしいと思い設計をしています。
所有と向き合った自邸の設計
ところで、わたしが建築や都市という学問に辿りついた原点として、「家族」と呼ばれる関係性や社会制度への疑いがあります。個人的な話になりますが、川崎のマンション街に生まれたわたしの両親は、早いうちに離婚しています。父はその後再婚し、わたしはしばらく母と墨田区の下町で、雑居ビルの1室暮らしをしていました。数年二人暮らしが続いた後、母の再婚をきっかけに解散の号令がかかり、言わば家族がバラバラに解体された状態になりました。複雑な家庭環境のようにも聞こえますが、実際は一個人として尊重し合うドライな関係は自由で心地よく、不完全ながらも前向きなものでした。かつて家族という社会的に強力な繋がりのあったはずの個人がバラバラに生きている状況も面白く、現在当たり前とされている家族の形や、それによる幸福や豊かさ、そしてその家族を内包する住宅というものを考え直すようになりました。また、それまでファミリー向けに商品化された3LDKのマンションで、自分と凡そ同じ属性の近隣住民に囲まれて暮らしていたわたしにとって、下町の雑居ビル暮らしはかなり刺激的で面白いものでした。町工場、喫茶店、居酒屋、学校、コンビニ、病院、公園、美容院、銭湯、ありとあらゆるものが混在する状況の傍ら、建設中のスカイツリーが見たことのない高さに成長していく。身内も余所者も関係なく、人々の欲望や切実さが露わになっている。生活の現場にいる当事者になった感覚でした。
そんな雑話をふまえ、同じく墨田区の下町に構えた自邸の話をしたいと思います。
敷地は2本の商店街に挟まれ、革や金属加工の町工場が点在する準工業地域の木造密集市街地のはずれに位置しています。敷地面積35平米程の小さな土地に建つ鉄骨造3階建ての狭小ビルを購入し、リノベーションしたものです。このビルは住宅ローンを使って購入しましたが、住宅ローンは敷地と上物の面積に対して、住居に充てるべき最低面積が設定されています。 住宅とは家族の器なので、家族を成立させるための広さが必要ということですが、外食したり、銭湯に行ったり、生活のほとんどを都市空間に依存しているわたしたち夫婦にとっては持て余してしまう広さでした。
そこで、最低限の私的空間(寝床と、共有できない所有物)以外のすべての空間を、誰にも占有されない場と仮定して計画することにしました。
ピロティ状の半屋外空間とした1階、ほぼスケルトンの状態にした2階には、それぞれ最低限の水回り設備を備えつつ、わたしたち以外の他者が使うことも想定したつくりとしました。収納と寝室のある3階を唯一の占有空間として、セキュリティの管理を切り分けています。屋上には眺めの良い小さな小屋が載っていて、3階の占有部分を通ることなくアプローチすることができます。

[スケルトン状にした空間に、シンクだけを置いた2階。店舗や事務所など、住居以外の用途で使われることを期待している(提供/江島史華)]
ここを所有し、毎日生活しているのはわたしと夫の二人ですが、それぞれの友人や地域住民など関わり合いのある人たちが使いはじめたり、仕事や遊び、商い等さまざまな出来事が発生する雑居的状況がつくれるといいなと考えています。
「あたりまえ」のその先に
家族の解体に直面したのが大学で建築を学びはじめた頃で、大学の初回の講義では、北山恒さんに「制度を疑え」とレクチャーを受けます。強烈な言葉ですが、一人ひとりが社会の当事者であり、社会は民主的に自分たちの手でつくるものであり、その一部に建築があるのだと理解しました。建築によって、人びとの関係性や生活様式が規定されていることを自覚するとともに、建築を設計することの自由さや面白さにも気づかされました。その後に取り組んだ大学の設計課題ではそういった既存の枠組みを壊し、豊かさや自由を再構築するような設計を繰り返していました。
その中で、建築家の役割とは、まだ見ぬ「あたりまえ」を提示することなのではないかと考えるようになります。その考えは学生から今まで変わることなくもち続けています。
今日「あたりまえ」とされているビルディングタイプや建築言語では補いきれない、人間が本来もつ自由さに対応した、新たな建築を提示していきたいと考えています。
(企画・編集:ロンロ・ボナペティ)
江島 史華
1991年 神奈川県生まれ
2016年 横浜国立大学大学院Y-GSA修了
2016-2021年 architecture WORKSHOP勤務
2021年- awn coo / AWN
https://archws.com/network/members/f-ejima/




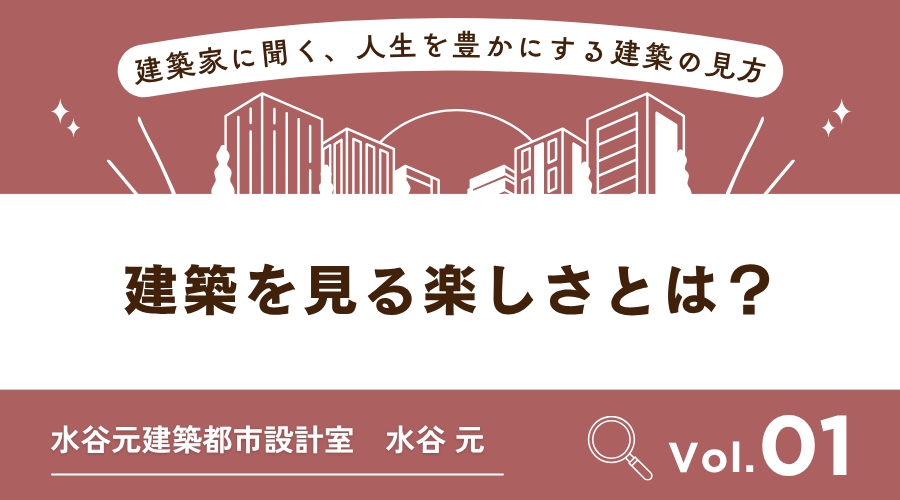
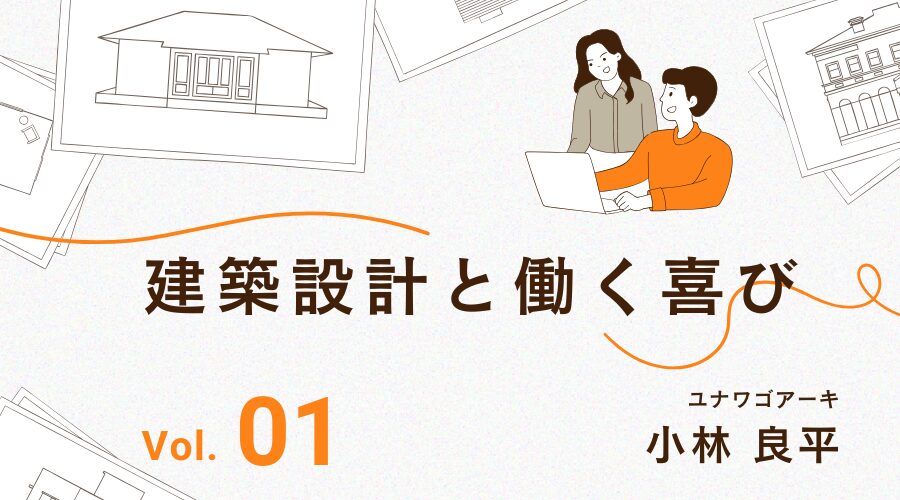

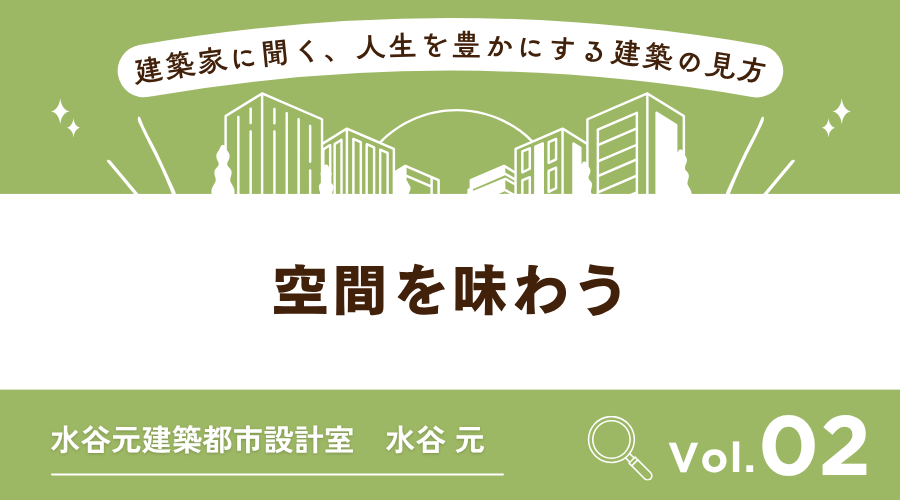
.jpg)
が設計した金沢21世紀美術館-21st-Century-Museum-of-Contemporary-Art-Kanazawa-DesignSANAA.jpg)
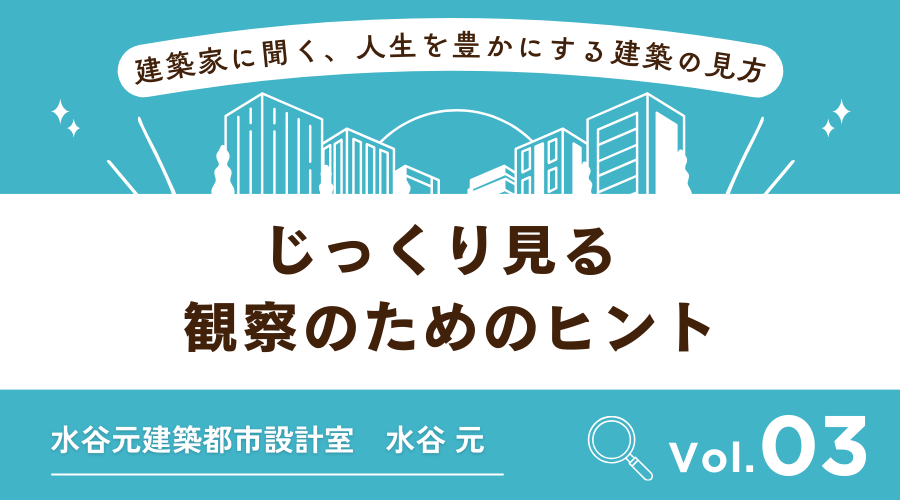

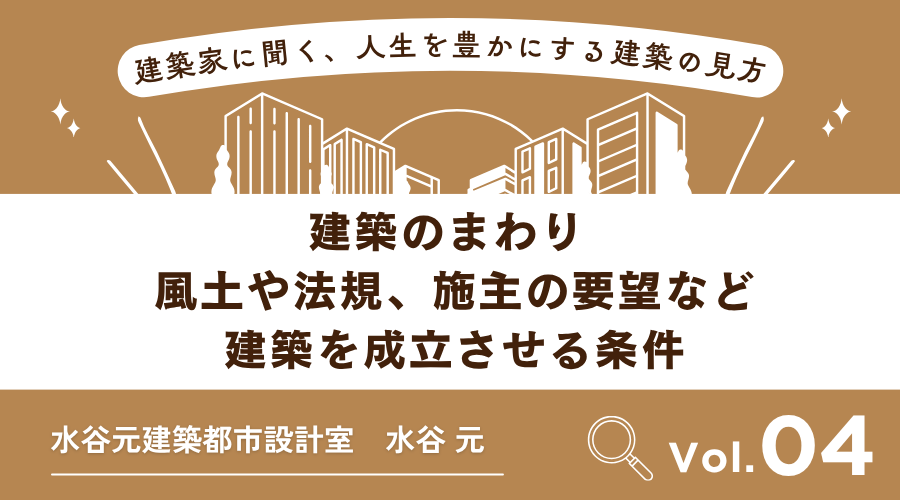
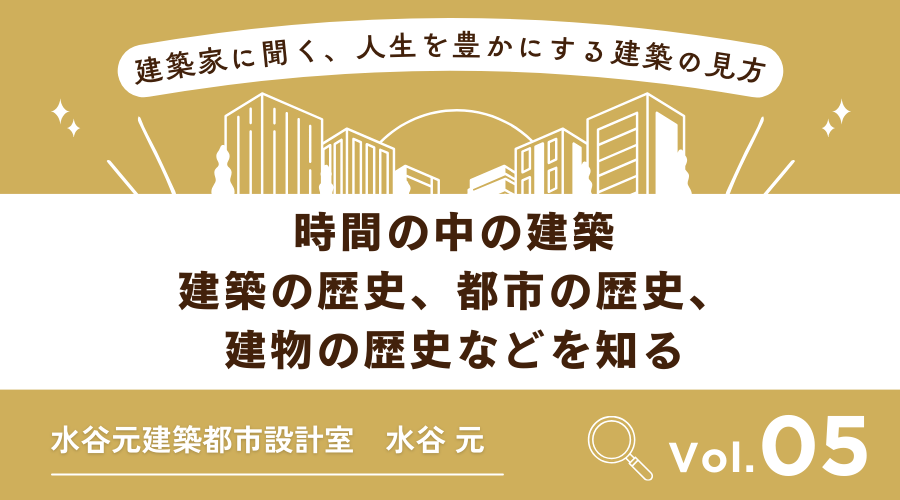
.jpg)