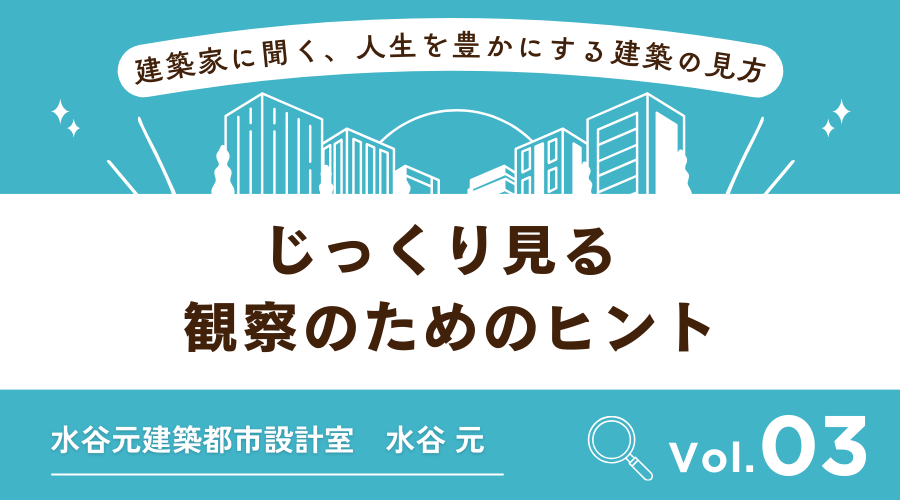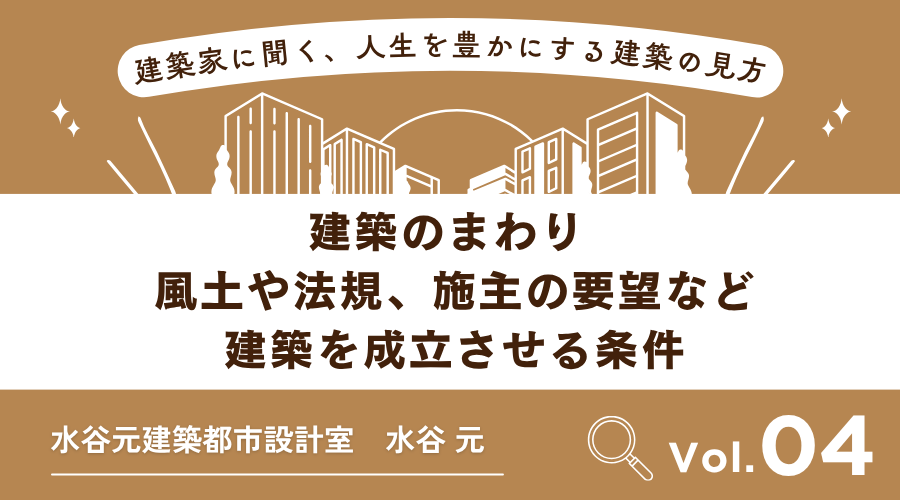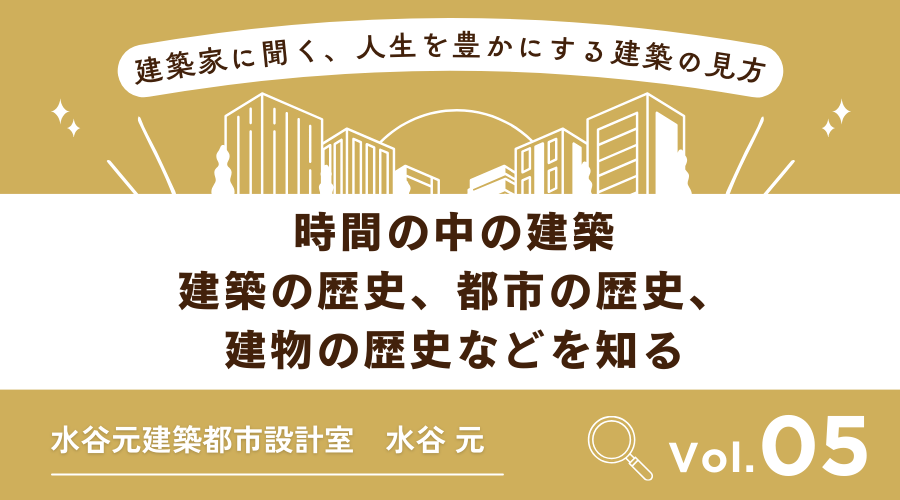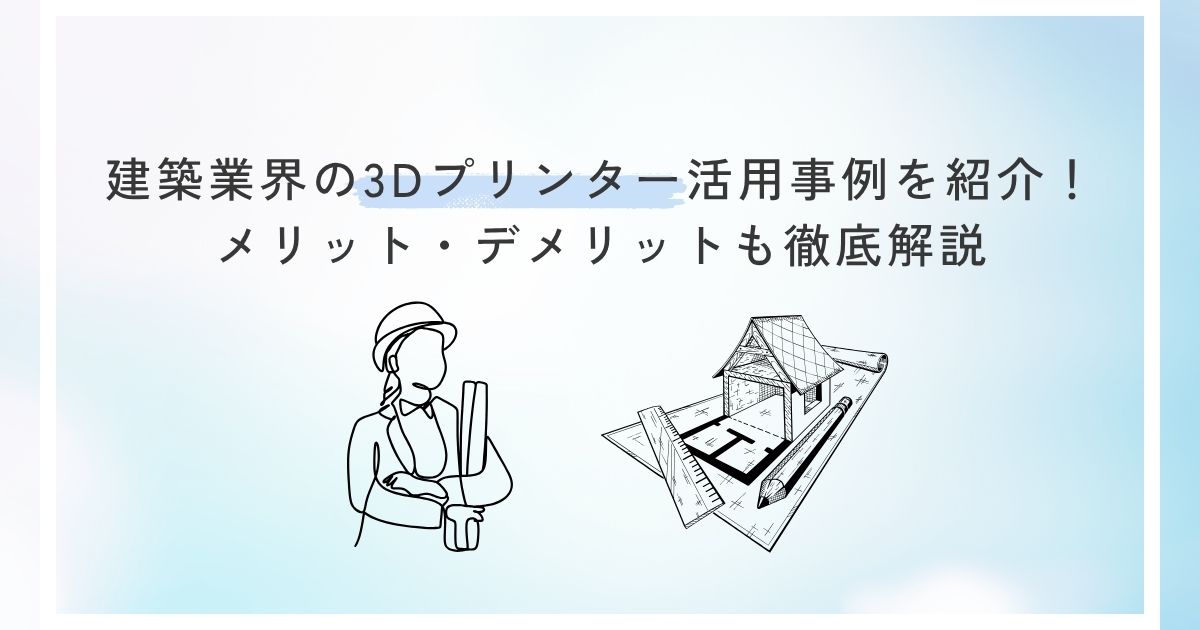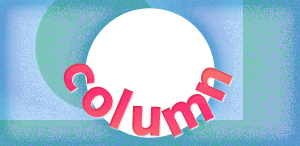
人生の指針となるようなインタビューや、スキマ時間にお楽しみいただけるコラムを紹介します。
2025.11.27
建築設計と働く喜び──第5回 西村拓真
.jpg)
建築人を豊かにすることを目指すA-magazineが、建築設計に携わる人びとが建築設計のどのような点に働く喜びを見出しているのかをシリーズで紹介する”建築設計と働く喜び”。第5回は、日本を代表する組織系設計事務所、日本設計でスタジオジブリの世界を表現する「ジブリパーク」の設計にも携わられた西村拓真さんに寄稿していただきました。
======
日本設計の西村拓真です。
大学時代や今の立場を目指すきっかけを振り返りながら、これまで自分がどのように建築設計を捉えてきたかを書いてみたいと思います。大学での学びや人との出会い、社会人としての経験を通して、考えてきたことが少しだけかたちになってきました。
1.大学での出会いと気づき
明治大学建築学科に入学した当初、私は建築というものを「形をつくること」だと単純に考えていました。課題に追われる日々の中で、建築雑誌の図面や写真を参考にしながら、それらしい建物をつくろうとしましたが、そこに自分の考えや意思はほとんどありませんでした。
そんな中、建築史・建築論(青井哲人)研究室に配属されたことが大きな転機になりました。青井先生との出会いを通じて、建築や都市を単なる造形の問題としてではなく、歴史や社会、思想の連なりの中で捉える視点を学びました。建築とは、人の営みと時間の積層の上に生まれるものだということ。都市の風景や地域の生活を読み解くことが設計の基盤になるということ。何より、「問いを立てる力」こそが、設計者にとって最も重要な資質であると感じました。研究室での学びは、後に社会に出てからも、設計における思考の軸をつくる礎になりました。
2.社会へ身を投じる–研究・就職活動を通じて–
研究室に所属する年に、東日本大震災が日本を襲いました。あの出来事をきっかけに、建築家の役割や建築のあり方が、目まぐるしく書き換えられていくのを肌で感じました。建築は単にモノをつくることではなく、人の暮らしや地域の再生、社会の仕組みそのものに関わる営みなのだと、強く意識するようになりました。
そのような出来事や研究室での活動を通じて、次第にそうした建築家のあり方に自分の将来像を重ねるようになり、「自分はどんな建築をつくりたいのか」「どんなかたちで社会と関わりたいのか」を考える時間が増えていきました。
「建築家」とは完成された存在ではなく、時代の変化や社会の要請に応じて常に観察し、考え、そして新しい価値を提示していく職能をもつ人だと思います。変化の激しい時代だからこそ、その柔軟さが求められます。その意味で、建築家とは“半熟”な存在だと思います。専門性に凝り固まらず、学び続け、変わり続けることが求められる職能です。そうした柔らかい働き方に魅力を感じ、私は日本設計に入社しました。大きな組織の中でも、自分なりに考え、提案し、社会に対して新しい視点を提示できるようになりたいと思いました。建築設計に留まらず、都市計画やランドスケープ、といった多層的な領域を横断しながら、社会の変化に応答していく姿勢。その中で、自分も“半熟”なまま、学びながら社会に価値を返していく設計者でありたいと思い、入社を決めました。
3.ジブリパークの仕事と建築の媒介性
入社してからの数年間は、とにかく「経験の連続」でした。
図面を描き、模型をつくり、現場に立ち、事業者や施工者、行政、時には地域の方々と議論を重ねる。ひとつの建築が形になるまでに関わる人の多さ、調整の複雑さ、そしてその中で建築が「社会の一部」として建ち上がっていくダイナミズムを実感しました。
特に印象的だったのは、ジブリパークの設計に携わった経験です。
このプロジェクトでは、「ジブリ作品の世界観を空間として表現する」という明快なテーマがある一方で、それをどのように現実の場所に落とし込むかという難しさもありました。単なる再現ではなく、訪れる人が“体験”を通して作品の余韻を感じられる空間にすることを目指しました。
さらに、チームとして働くことの重要性も強く感じました。発注者、スタジオジブリをはじめ、日本設計のチームメンバー、施工者など、立場も専門も異なる人々と協働する中で、「設計」は一人で完結しないことを再確認しました。複数の視点を横断的に統合し、互いの思想や想像力をつなぎ合わせていくことが、設計の本質であり、同時に“働く喜び”でもありました。
印象的だったのは、設計が「物語と現実をつなぐ媒介」になる瞬間でした。図面や模型が、スタッフや職人、行政、そして来場者の想像をつなぎ、ひとつの世界をかたちづくっていく。その過程で、建築は単なる物理的な構造物ではなく、人と人、人と時間、人と物語をつなぐ“媒介”なのだと改めて感じました。設計に携わる喜びは、まさにその媒介の力にあると思います。誰かの思いを空間として翻訳し、それが多くの人の体験へと広がっていく――その循環の中に、自分の仕事の意味を見いだすことができます。
4.未完成のまま歩み続ける喜び
社会の変化が加速する今、設計者の役割も日々変化しています。
サステナビリティや地域共生、デジタル技術、災害への備え、働き方や暮らし方の多様化――。そうした課題のどれにも、建築は深く関わっています。これからの時代における建築設計の喜びとは、固定的な答えを出すことではなく、変化に寄り添いながら「新しい問い」を生み続けることにあると感じています。
建築設計という仕事は、終わりのない学びの連続ですが、その過程にこそ「働く喜び」があります。問いを立て、仲間と考え、社会の一角に新たな価値を築いていく。その連鎖の中で、自分自身も成長していきたいです。
(企画・編集:ロンロ・ボナペティ)
西村拓真
一級建築士(2019年取得)/認定コンストラクション・マネジャー(2024年取得)
1988年 神奈川県生まれ
2012年 明治大学理工学部建築学科 建築史・建築論研究室 卒業
2014年 明治大学理工学研究科建築学専攻 建築史・建築論研究室 修了
2014年~ 株式会社 日本設計
主な受賞歴に、「ジブリパーク 魔女の谷」みんなの建築大賞 特別賞(2025年)、日本建築学会優秀修士論文賞(2014年)がある。




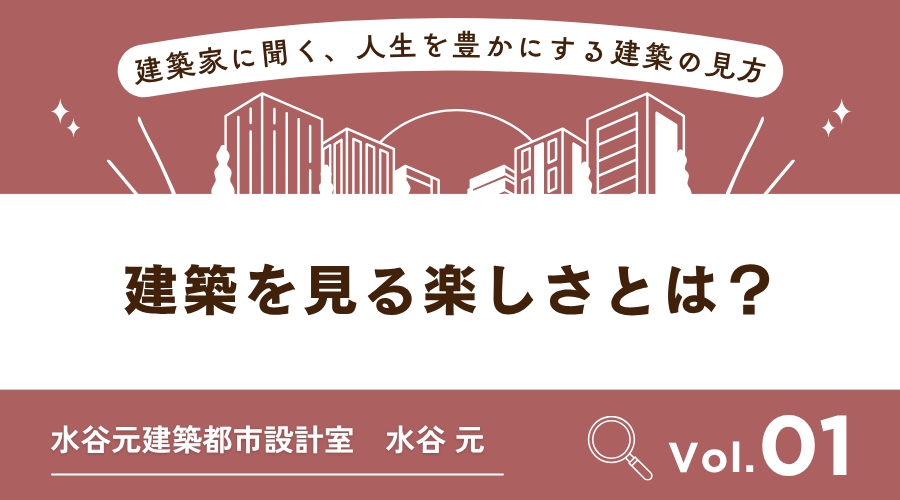
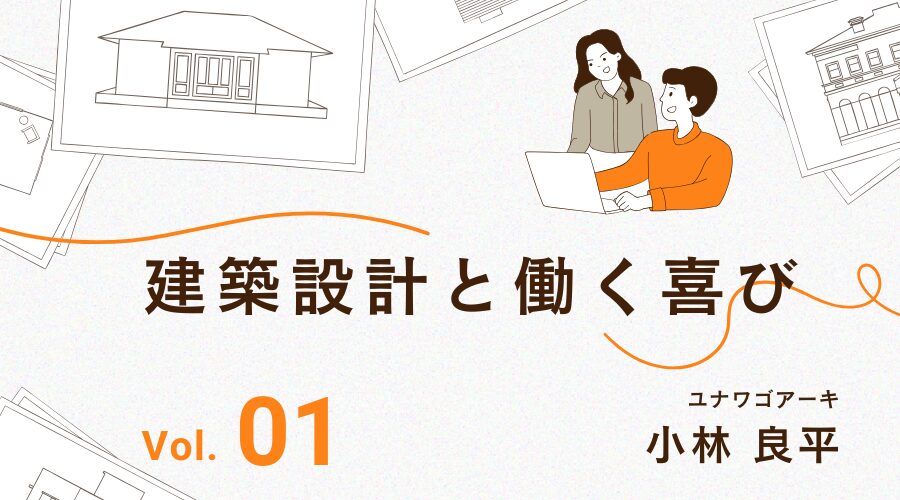
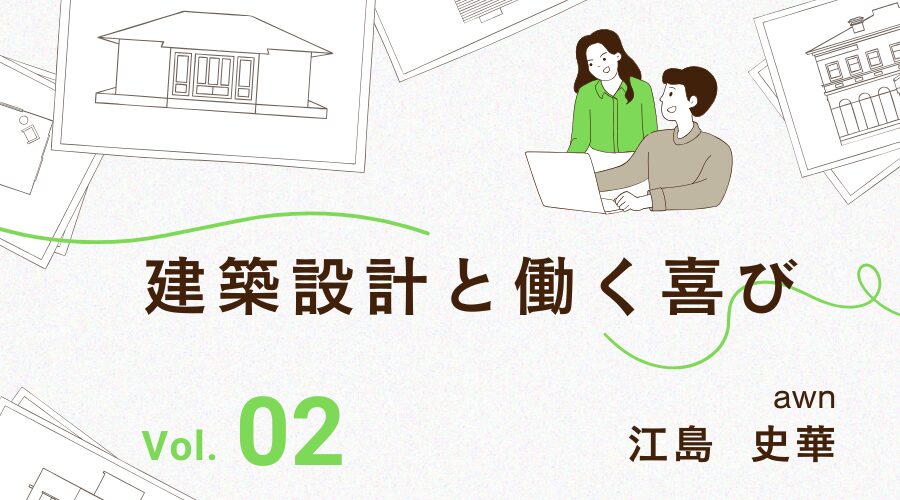

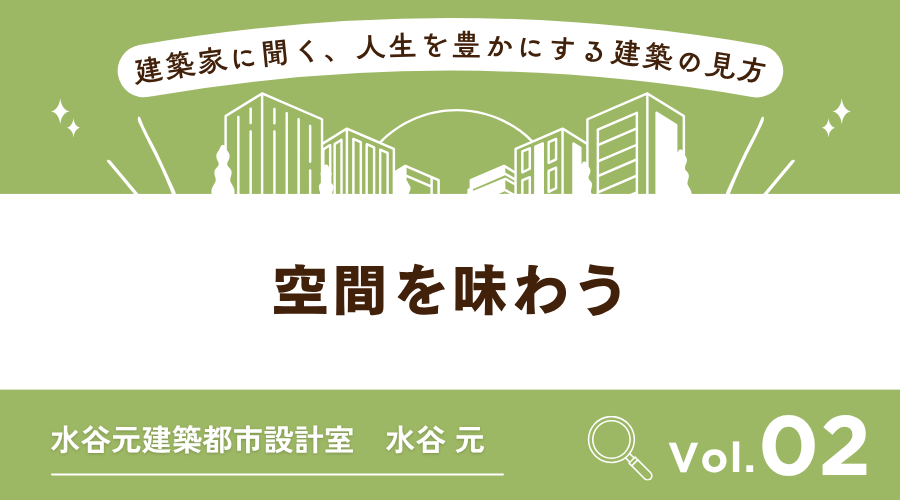
.jpg)
が設計した金沢21世紀美術館-21st-Century-Museum-of-Contemporary-Art-Kanazawa-DesignSANAA.jpg)