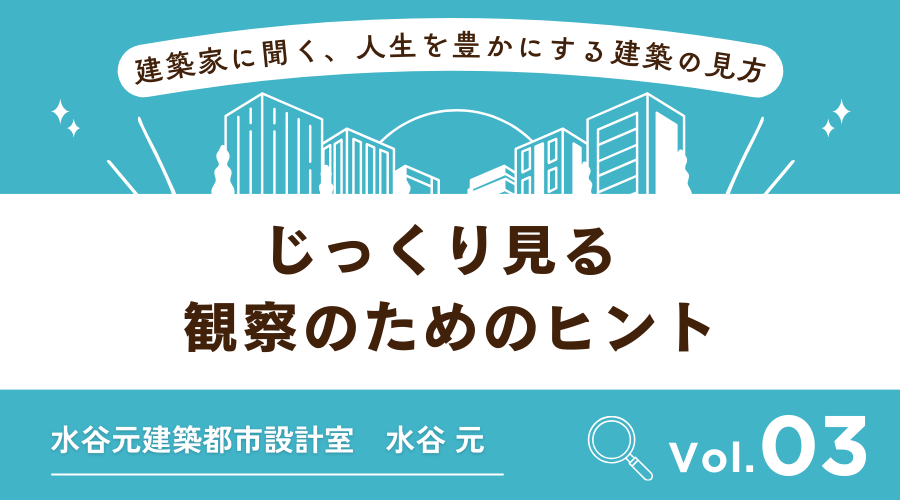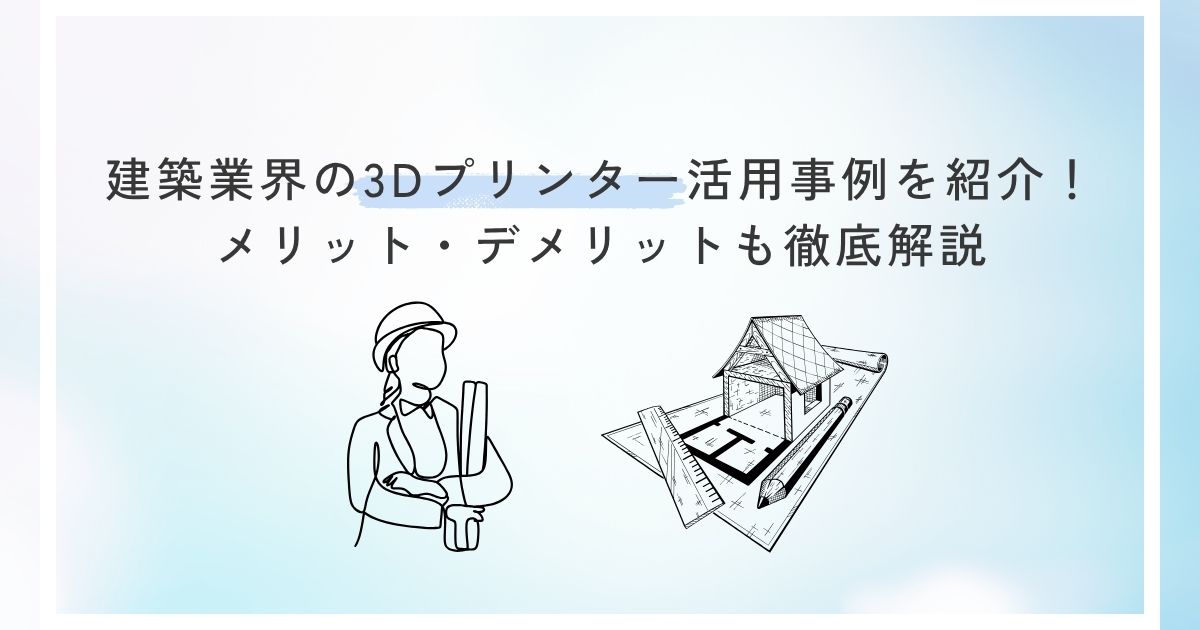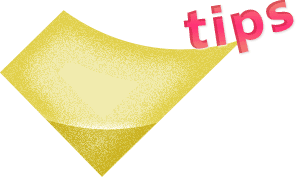
建築業界のリアルな情報や就職・転職活動で役立つ情報を紹介します。
2025.11.14
手描きパース初心者向け|成功するための3つのコツと実践テクニック
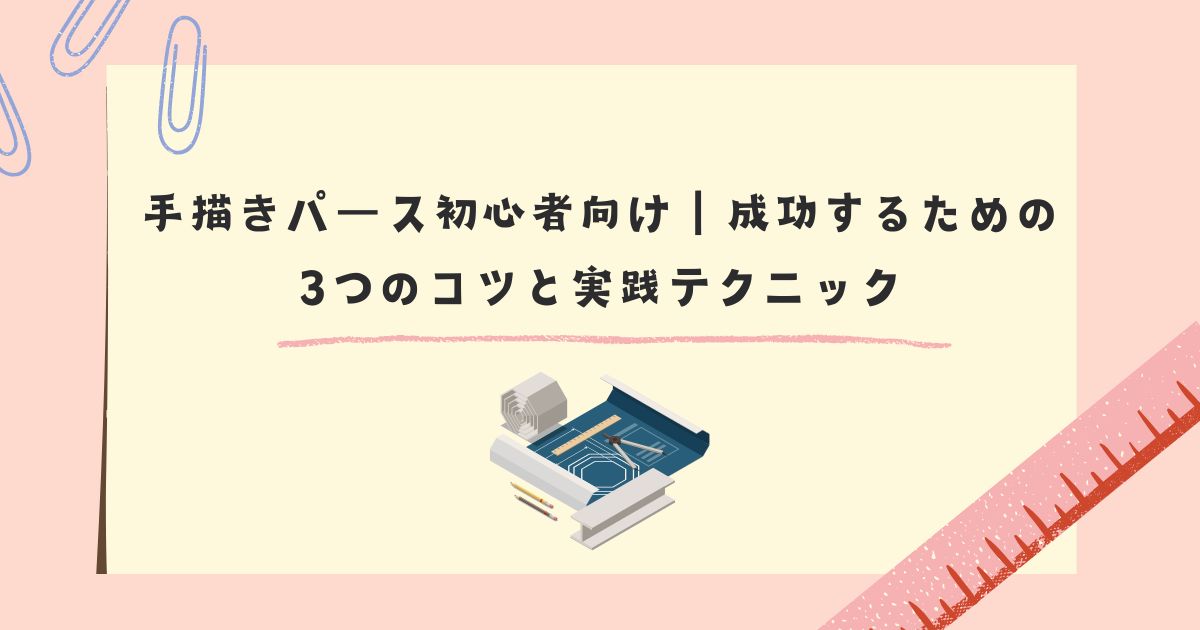
「手描きパースって難しそう…」「絵心がないと描けないかも…」と、挑戦するのをためらっていませんか?
建築やインテリアのイメージを伝える手描きパースは、CGにはない独特の温かみと表現力があります。
一見、専門的な技術が必要そうに見えますが、実は初心者でも押さえるべきポイントさえ知れば、誰でも魅力的なパースを描くことが可能です。
本記事では、手描きパース初心者のあなたに向けて、成功するための「3つのコツ」と、今日からすぐに試せる具体的な「実践テクニック」を分かりやすく解説します。
基本を学んで、楽しくパース作成を始めましょう。

手描きパースとは
手描きパースとは、建築物やインテリア空間などを、あたかもその場で見ているかのように立体的に表現する手法のことです。
CGで作成されるパースとは異なり、フリーハンドで描かれる線や色の濃淡には、独特の温かみや味わいが生まれます。
設計者やデザイナーがクライアントにイメージを伝えるための手段として使われるほか、趣味として楽しむ人も増えています。
一見難しそうに見えますが、基本的なコツや手順を学べば、初心者でも魅力的なパースを描くことが可能です。
手描きパースの3つのコツ
手描きパースの上達には、いくつかのポイントがあります。
初心者の方がまず意識したい、成功するための3つのコツをご紹介します。
1.住宅の写真を見る
まずは、プロが撮影した住宅やインテリアの写真をたくさん見ることが大切です。
実際の建物がどのように見えているか、光はどこから当たり、影はどこにできるのか、素材感はどう表現されているかを観察しましょう。
美しい構図やリアルな寸法をインプットすることで、自分が描く際の引き出しが増えます。
気に入った写真があれば、それを模写してみるのも効果的な練習方法です。
2.好きなものを楽しく描く
上達のためには継続が不可欠ですが、義務感で描いていると長続きしません。
最も大切なのは「楽しく描く」ことです。
自分が「素敵だな」と思う家、好きなデザインのカフェ、お気に入りの家具など、心惹かれるものをテーマに選びましょう。
描きたいというモチベーションが、技術を向上させる一番の原動力になります。
3.基本的な作成手順を学ぶ
いきなり我流で描き始めると、途中でつまずいたり、バランスの悪い絵になったりしがちです。
遠近感や立体感を正しく表現するためには、基本的な作成手順を知っておくことが重要です。
どのようなステップで描き進めていくのか、どこから手をつけるべきかを理解することで、効率的に学び、着実にスキルアップできます。
手描きパースの作成手順
ここでは、手描きパースを作成する際の一般的な流れを解説します。
この手順に沿って練習してみましょう。
基本的な構造を把握する
まず、描きたい対象物(建物や部屋)がどのような形をしているかを理解します。
複雑に見える建物も、基本的には大きな箱(立方体や直方体)の組み合わせとして捉えることができます。
全体の形、屋根の形状、窓やドアの大まかな位置関係を把握しましょう。
構図を決める
次に、対象物をどの角度から見て描くか、紙面のどこに配置するかという「構図」を決めます。
ここで重要になるのが「アイレベル(目線の高さ)」です。これは、描き手の目の高さを表す水平線で、このアイレベルを決めることで、建物を見上げているのか、見下ろしているのかが決まります。
さらに、遠近感を表現するために「消失点(VP)」を設定します。
消失点とは、実際には平行な線路や道路が、遠くに行くにつれて交わって一点に見える点のことです。
この消失点をアイレベル上のどこに置くかによって、パースの遠近感や見え方が大きく変わってきます。
ラフなスケッチを描く
構図が決まったら、鉛筆などで薄く、大まかな形を描き出していきます。
これをラフスケッチと呼びます。
消失点を意識しながら、全体のバランスや遠近感を確認し、修正を加えながら形を整えていきます。
線画を追加する
ラフスケッチで大まかな形が取れたら、線画を描き加えていきます。
建物の輪郭、窓枠、ドア、家具のディテールなどを明確にしていきましょう。
線の強弱や太さを変えることで、質感や立体感を表現できます。
影を追加する
パースにリアリティと立体感を与えるために、影を描き込みます。
まず光源(太陽や照明)がどこにあるかを決め、それによってできる影を加えていきます。
物が落ちる影と、物自体の暗い部分を描き分けると、よりリアルになりおすすめです。
着色する
最後に着色して仕上げましょう。
色鉛筆、水彩絵の具、マーカーペンなど、使用する画材によって仕上がりの雰囲気は大きく変わります。
素材の質感や光の当たり方を意識しながら色を塗ることで、パースの魅力が一層引き立ちます。
手描きパースの着色テクニック
着色はパースの印象を左右する重要な工程です。
代表的な画材(色鉛筆、水彩、マーカーペン)とそれぞれのテクニックを紹介します。
色鉛筆
手軽に扱え、初心者にもおすすめの画材です。
重ね塗りをすることで色の深みを出したり、美しいグラデーションを作ったりできます。
筆圧の強弱で濃淡をつけやすく、木の温もりや布の柔らかさといった、温かみのある質感を表現するのに適しています。
水彩
透明感のある仕上がりが特徴です。
水の量を調節することで、色の濃淡や「にじみ」「ぼかし」といった水彩ならではの表現が可能です。
特に空やガラス、柔らかな光の表現に適しています。
乾くまでに時間がかかりますが、ふんわりとした優しい雰囲気のパースに仕上がります。
マーカーペン
発色が良く、スピーディーに色を塗れるのが特徴です。
特に、コピックなどのアルコールマーカーがよく使われます。
ムラなく均一な面を塗るのが得意で、シャープでクリアな印象を与えられるのです。
重ね塗りによる濃淡表現も可能で、モダンな建築やインテリアの表現に適しています。
手描きパースの透視テクニック
パースに正しい遠近感を与えるためには、「透視図法」の理解が欠かせません。
これは、構図決めの際に設定した「消失点」をいくつ使うかによって、大きく3つの種類に分けられます。
1点透視法
消失点(VP)が1つだけの最もシンプルな図法です。
対象物を正面から見た構図で、奥行きのある空間を表現するのに適しています。
例えば、部屋の奥に向かってまっすぐ伸びる廊下や、線路などを描く際に使われます。
2点透視法
消失点(VP)がアイレベル上の左右に2つある図法で、最も一般的に使われます。
対象物を角から見たような、より立体的で自然な構図を描くことが可能です。
建物の外観や、部屋のコーナーを斜めから見た場合などに用いられ、ダイナミックな印象を与えます。
3点透視法
左右の2点に加え、アイレベルの上または下にもう1つの消失点(VP)を持つ図法です。
高層ビルを下から見上げた構図や、街並みを上空から見下ろした構図など、高さやスケール感を強調したい場合に使われます。
最も複雑ですが、迫力のある表現が可能です。
まとめ
手描きパースは、コツと手順を理解すれば初心者からでも楽しく始められます。
成功の秘訣は、まず住宅の写真をよく観察し、インプットを増やすことです。
そして、何よりも自分が好きなものを楽しく描き続けることが大切です。
基本的な作成手順(構造把握、構図、ラフ、線画、影、着色)を学び、色鉛筆やマーカーなどの着色テクニック、1点・2点透視法といった透視テクニックを実践することで、表現の幅は格段に広がります。
ぜひ手描きならではの温かみあるパース作成に挑戦してみてください。




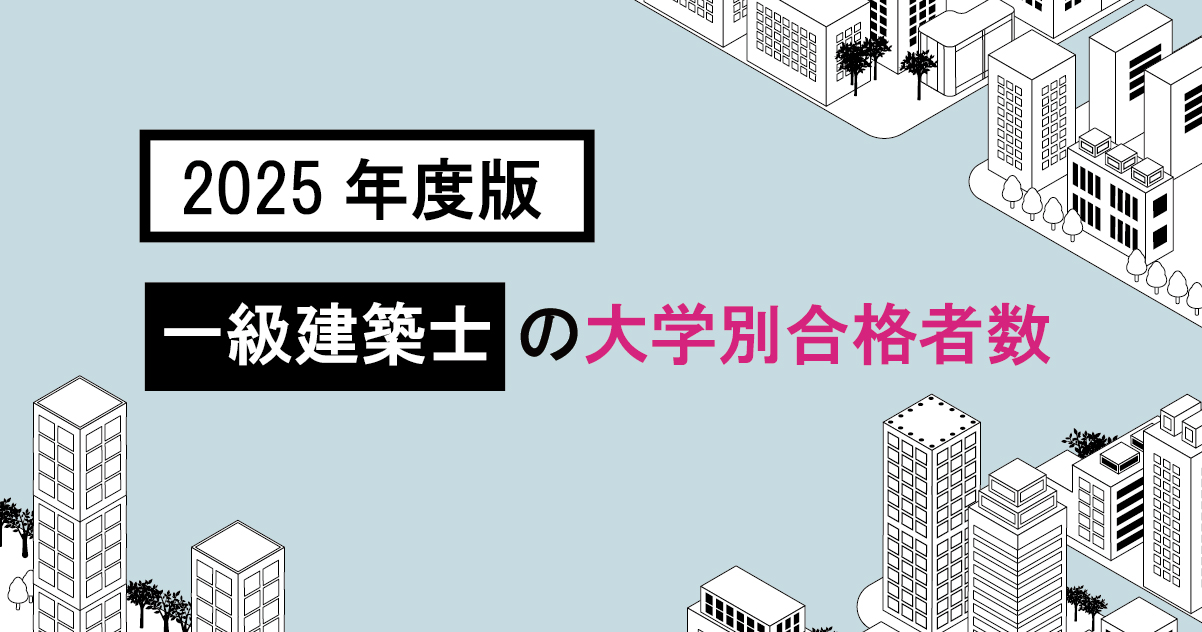


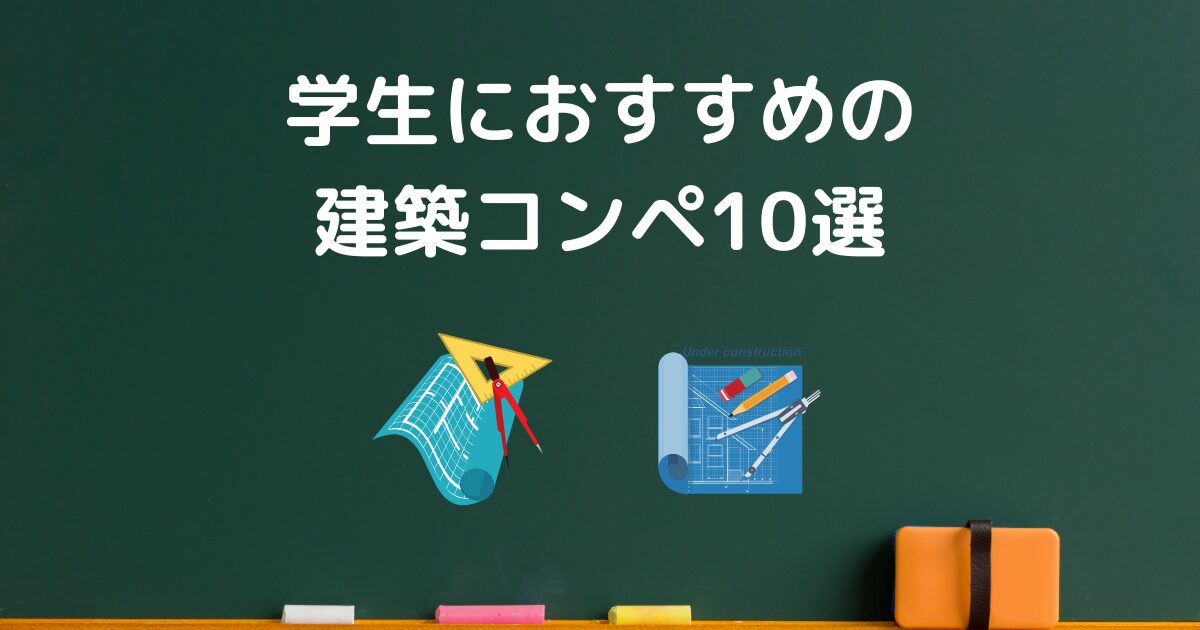




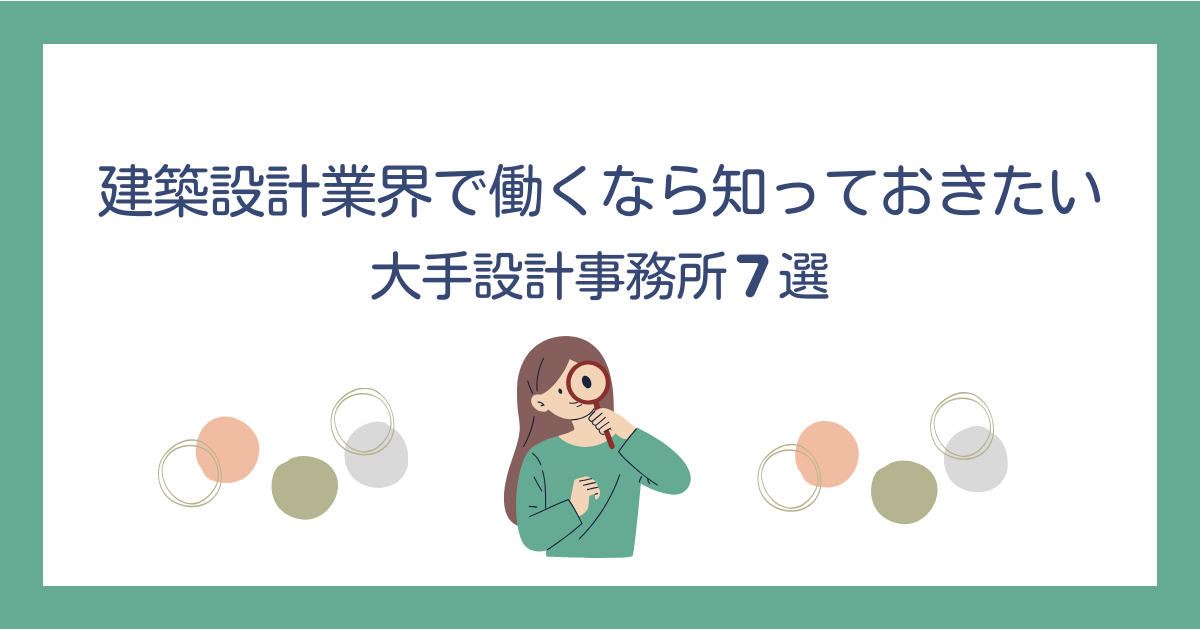

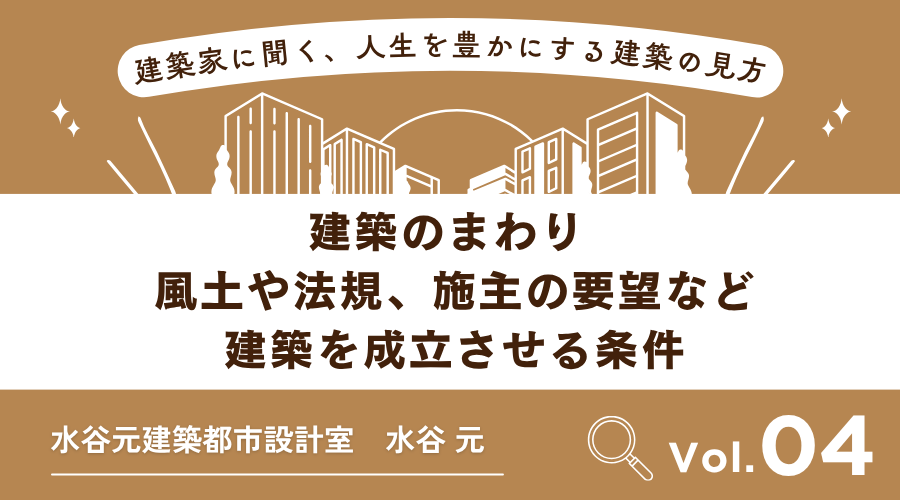
.jpg)