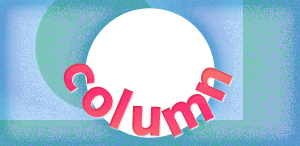
人生の指針となるようなインタビューや、スキマ時間にお楽しみいただけるコラムを紹介します。
2025.10.30
人生を豊かにする建築の見方──第4回 建築のまわり 風土や法規、施主の要望など建築を成立させる条件 水谷元
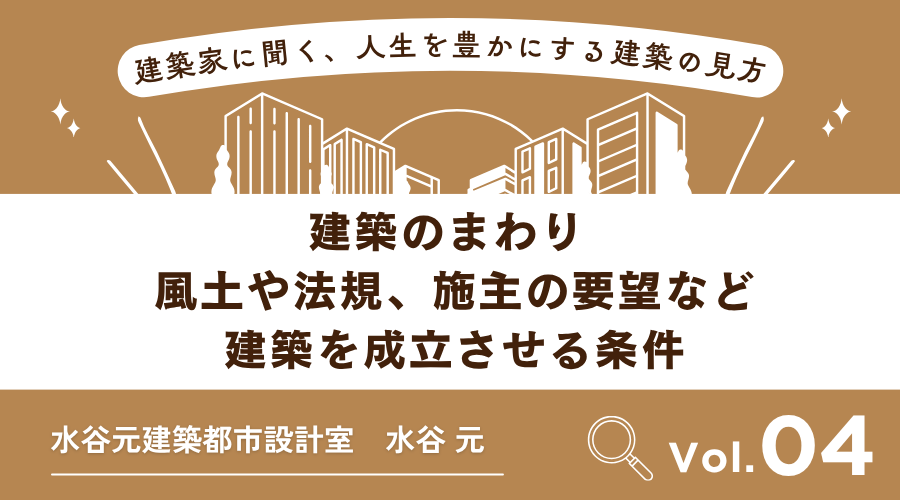
建築の見方を学ぶ連載、「人生を豊かにする建築の見方」の第4回をお届けします。案内人は「建築を楽しめるようになると人生が豊かになる」と語る建築家の水谷元(みずたに・はじめ)さん。今回は、少し引いた目線で建物を見渡して、ある建築を成立させる条件についてまとめていただきました。
======
建築物は建築される土地に固定され、縛られるため、一定の公共性が求められます。計画される地域の風土、都市計画法や建築基準法などの法律、そして何よりもそこで暮らす、利用する市民の要望など、複雑な条件の中で、建築は成立します。
建築計画は条件に合った土地を探すところから始めることもありますが、本格的な計画は建設する土地が決定し、「敷地」となることから始まります。敷地の形状や周囲の自然環境や住環境、街並みを読み解くことが大切です。なぜなら、土地に縛られる建築は商業施設であっても住宅であっても、公共性を帯びるからです。長く地域住民に親しまれ、守られてきた歴史的な街並みであれば分かりやすいですが、外観や建物の大きさ、建築されることによる外部空間の形成は周辺地域に大きな影響を与えます。
私たちが計画を行う際、まずは敷地周辺の街歩きから始めます。調和を考えるためのヒントは、周辺地域や街並みに潜んでいるからです。街路空間や建築の屋根や外壁、窓や玄関の開口部、バルコニーの手すり、門構えや垣根や塀やアプローチの外構など、住宅や施設など建築の用途は問いません。古い街並みであれば、それは市民によって守られてきた景観で、さまざまなエレメント(要素)によって構成されています。商業施設などの外観にも街並みを構成するエレメントが及んでいるのであれば、地域の都市計画で景観規制などの制度設計がよく機能している証拠でしょう。建築家の宮脇檀がデザインコードを設定し、建築協定によって街並みの統一が図られた「シーサイドももち戸建て街区」などの事例もあります。工業化により量産品で構成されたどこにでもある風景であっても、何かしらヒントがあります。70年代以降に形成された郊外や集落であれば、地元の工務店や住宅デベロッパーの癖や思想が現れている場合もあります。また、画一的に開発された街、都市計画が機能していない無秩序に開発された街であれば、良いところばかりだけではなく、問題を発見することもあるでしょう。それらは私たちが敷地周辺の街並みや市民に建築を通してどのようにまちづくりに寄与できるのかを考えるきっかけになります。

シーサイドももち戸建街区 1993年~
必ずしも周辺との調和だけが大事というわけではなく、より良い方向や可能性を見出すための緊張感を与えることも時に大切です。内藤廣さんの設計した「島根県芸術文化センター・グラントワ」は、外壁から屋根に至るまで島根県益田市で親しまれてきたベンガラ色の石州瓦で包まれています。石州瓦は、凍害や塩害に強く、水分を吸収しにくい高い耐久性をもつのが特徴で、山陰地方の厳しい自然風土に育まれた実用的な瓦です。グラントワは、コンサートホールや美術館という機能を内包しているため、人口約4,000人という低層の集落の街並みに対してかなり大きなボリュームですし、石州瓦で包まれた様相は強烈なインパクトを与えています。しかし、石州瓦という素材への市民の親近感が建築への信頼性を増していると同時に、街への心地よい緊張感を生み出すことの両立を実現しています。フランスのパリにあるレンゾ・ピアノとリチャード・ロジャースの設計による「ジョルジュ・ポンピドゥー国立芸術文化センター」 は、パリの街並みにふさわしくないと当初は批判されましたが、旧来の厳格な文化施設と比べて、自由で活発な街並みと市民のアクティビティに寄与しています。
住宅のような小さな建築であっても、複合施設のような大きな建築でもあっても、建築が公共性から逃れられない以上、時に設計者は批判に晒されます。街並みの当事者となる上で私が大切にしている言葉のひとつに、「変わらないもの、変え難いものを発見し、理解することが、取りもなおさず、変えなければならないこと、変えうることの真の理解に必要である」 (『見えがくれする都市』槇文彦/1980)という言葉があります。
建築が社会的な営みである以上、法規による規制は避けて通れません。その代表的なものが、都市計画法における「集団規定」と、建築基準法における「単体規定」です。都市計画法は、土地の利用方法や施設の配置など、都市全体の計画的な発展を目指すものです。用途地域によって、建築の種類や高さ、容積率などが厳しく定められています。活発で発展的な市街地、良好な住環境を形成する低層の住宅地、それぞれの地域に適した集団規定が設定され、無秩序な開発を防いでいます。
建築基準法は、個々の建築物の安全性や衛生、防災などに関する最低基準を定めたものです。建物の構造の強度、採光・換気、避難経路の確保など、多岐にわたる項目が規定されています。近年では、バリアフリー法や省エネ法といった関連法規も、建築物に求められる比較的新しい要件です。
これらの法規は、時に建築家の創造性を縛る制約と捉えられがちですが、デザイン(設計)は建築のスタイリングや空間だけではありません。私たち市民が豊かさを享受するためには、建築は安心して暮らすことのできる基盤でなければなりません。都市や建築の空間、街並みを制度が規定している以上、法律は制約ではなく、先人たちが長い時間を掛けて積み重ねられてきたデザインだといえるでしょう。法律という条件に向き合った設計作業は先人たちとの共同作業と捉えることもできます。
建築設計監理はクライアントワークスです。依頼主がいなければ成立しません。公共施設であれば市町村などの地方自治体、商業施設やオフィスやマンションなどであればデベロッパー、住宅であればそこに住まう家族です。建築の用途はそれぞれ異なりますから、条件も異なります。建築物の建設は経済行為ですから、予算はもちろんこと、面積や容積、その運用による利益などの資産性や経済性も考慮しなければなりません。少なくとも最低限のお金の不安が解消されていなければ、創造的で前向きな議論は難しくなります(当然、計画を遂行する設計者も不安になります)。
また、建築設計を通してつくづく思うのですが、クライアントワークスとはいえど、目の前に座っている設計依頼主だけがクライアントではないということです。先の周辺地域への配慮の話にも通じますが、建築はさらにその先を見なければならないということです。公共施設は特にわかりやすい例で、発注は行政から行われますが、実質のクライアントは市民です。90年代頃までは、行政側にもこの意識は希薄でしたが、最近では市民を巻き込んだ議論と施設計画を行うため、ワークショップなども開催されるようになりました。契約の条件に盛り込まれることも少なくありません。また、意識の高い設計者は、自ら行政に提案して行うこともあります。
公共施設に限らず、商業施設や住宅においても、その建築が生み出される社会的な価値を考えます。時代を超えて愛される建築となることは設計者としての希望であり本望ですが、目の前のクライアントを超えて、建築に関わる当事者を増やしていく力が建築にはあるように思うのです。その力は良い方向にも悪い方向にもなり得ます。故に設計者は、優れた創造性を発揮するための想像力を養うために、様々な事象に触れていなければなりません。
設計依頼主とのコミュニケーションを通じて、新しい気づきに出会うこともあります。思ってもないような要望を伝えられる時がわかりやすいですが、自分にはなかった価値観や感性を依頼主を通して得られることがあります。有名な話では、手塚建築研究所の手塚貴晴+手塚由比の設計による「屋根の家」です。屋根の家のご家族は、自宅の屋根の上で食事を家族で楽しむ習慣があったそうで、屋根の上でできるだけ多くの時間を過ごせる住宅を要望されたそうです。「屋根の家」が建築専門誌に発表された際、「依頼主のことを考えていない」と専門誌を通して批判されたそうなのですが、批判文が掲載された専門誌に設計依頼主ご家族が抗議の手紙を送ったという有名なエピソードがあります。こういった「思ってもないような要望」は時に、時代の価値観を揺さぶるような名建築を生み出すことがあるのです。
また、これは建築設計の現場に限らず、人と人とのコミュニケーションにおいても日常的にもよくあることですが、人は深層的に感じていることを言葉にできないということです。例えば、住宅の計画で「リビングを広くしてほしい」という要望をもらったとしても、実際は広いリビングがほしいわけではなく、家族それぞれが好きなことをやっていても、皆が同じ空間を共有できるような空間を求めているのかもしれません。
設計者はクライアントの本来の要望を引き出すような能力を持つ必要があります。それに気づくためにも、様々な事象に触れ、感動し、感動をそのままにせずに、感動の理由を追求し、記憶に留め、力にする努力が必要です。
(企画・編集:ロンロ・ボナペティ)
水谷元(みずたに・はじめ)
1981年兵庫県神戸市生まれ/福岡県福岡市の能古島育ち/九州産業大学にて森岡侑士に師事し、2004年に中退/2011年よりatelierHUGE主宰、2020年より水谷元建築都市設計室/著書に『現在知 Vol.1 郊外その危機と再生』(共著:NHK出版)、『地方で建築を仕事にする』(共著:学芸出版)、『臨海住宅地の誕生』(編集協力:新建築社)、日本建築学会2018年-2019年『建築雑誌』編集委員、九州大学『都市建築コロキウム』2020年前期非常勤講師





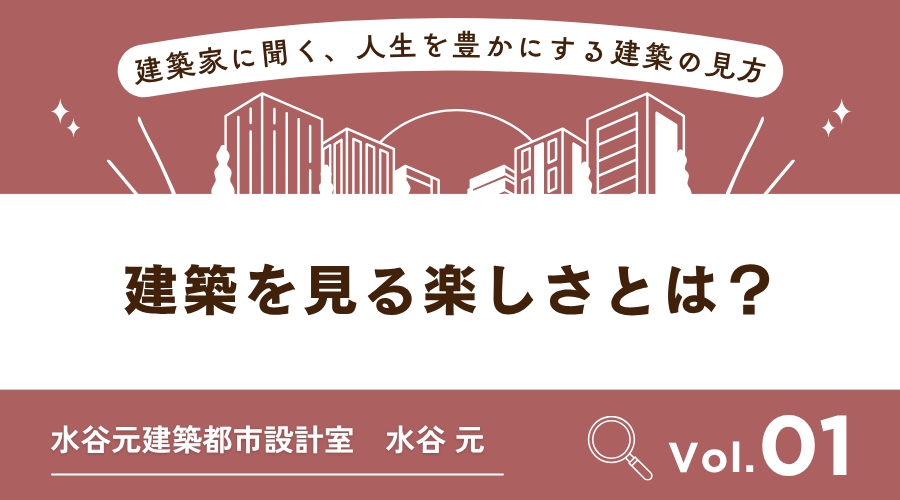
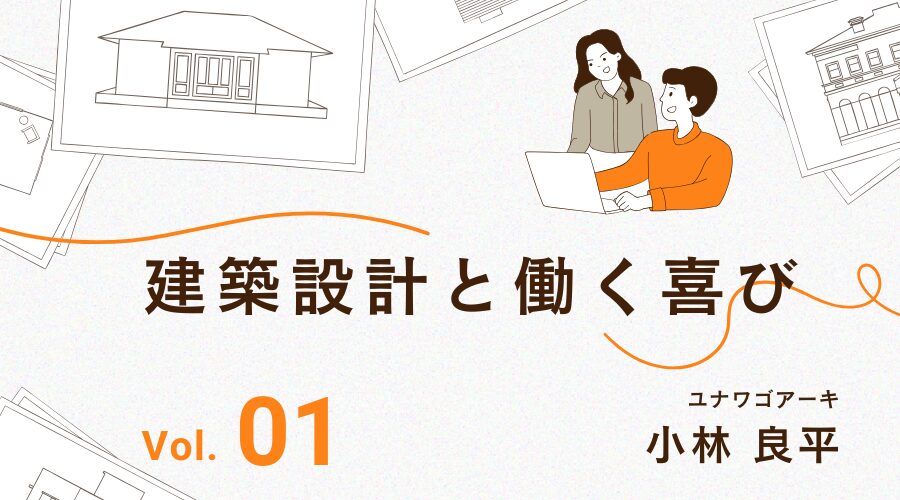
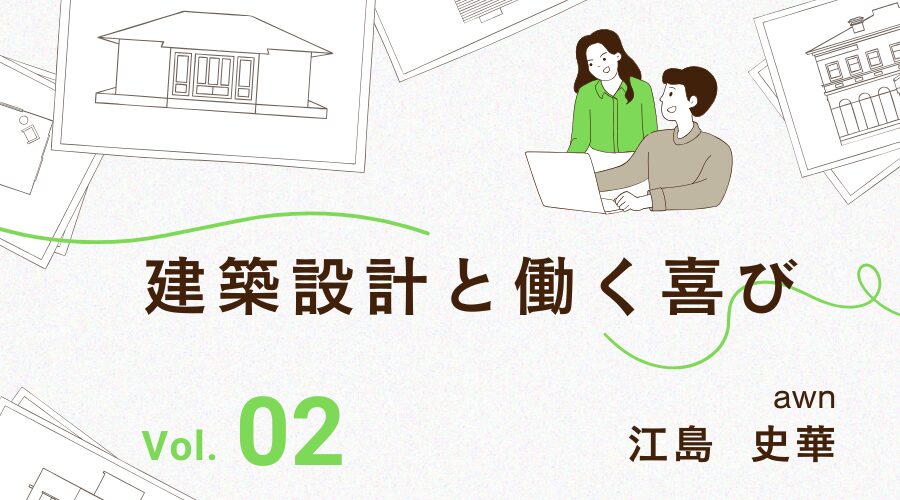

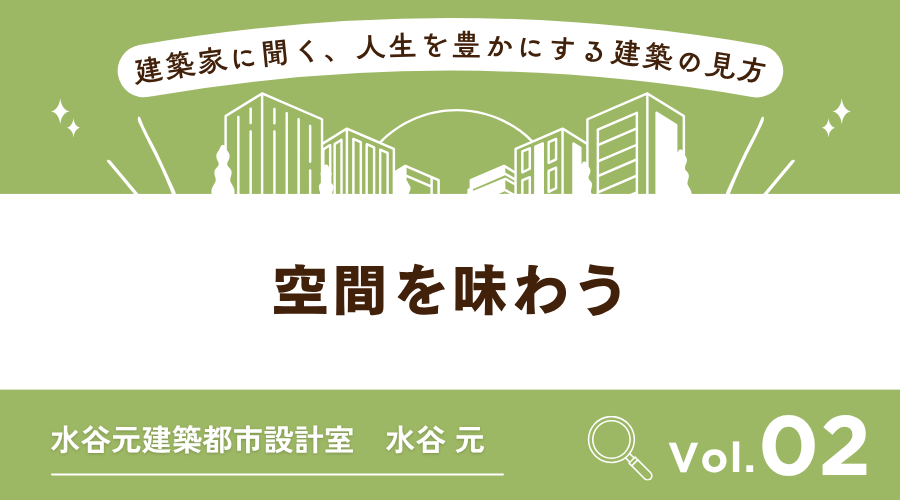
.jpg)
が設計した金沢21世紀美術館-21st-Century-Museum-of-Contemporary-Art-Kanazawa-DesignSANAA.jpg)
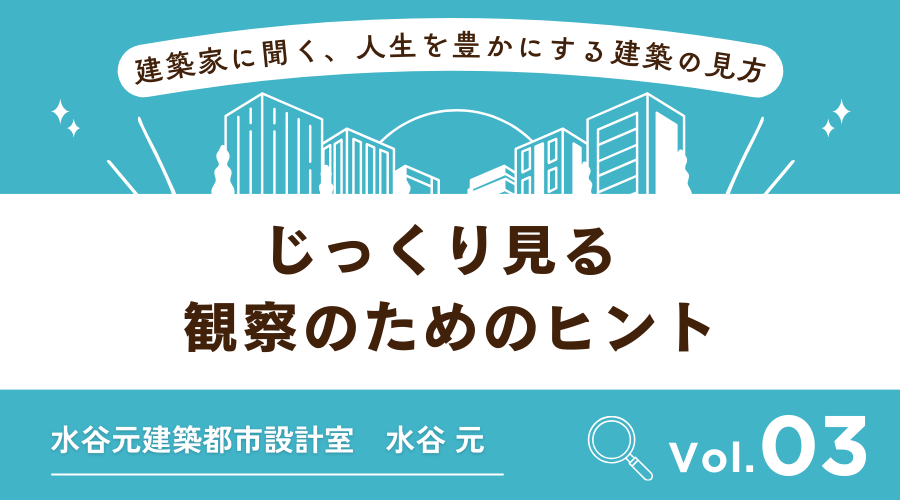

.jpg)
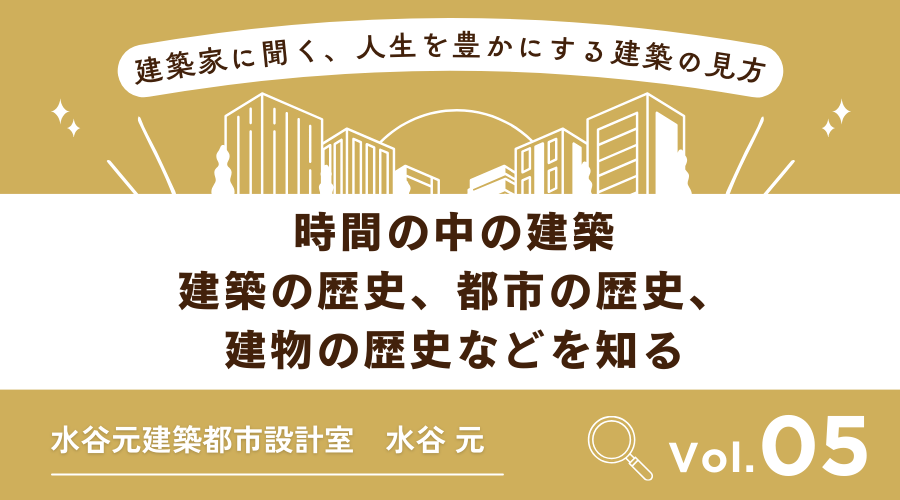
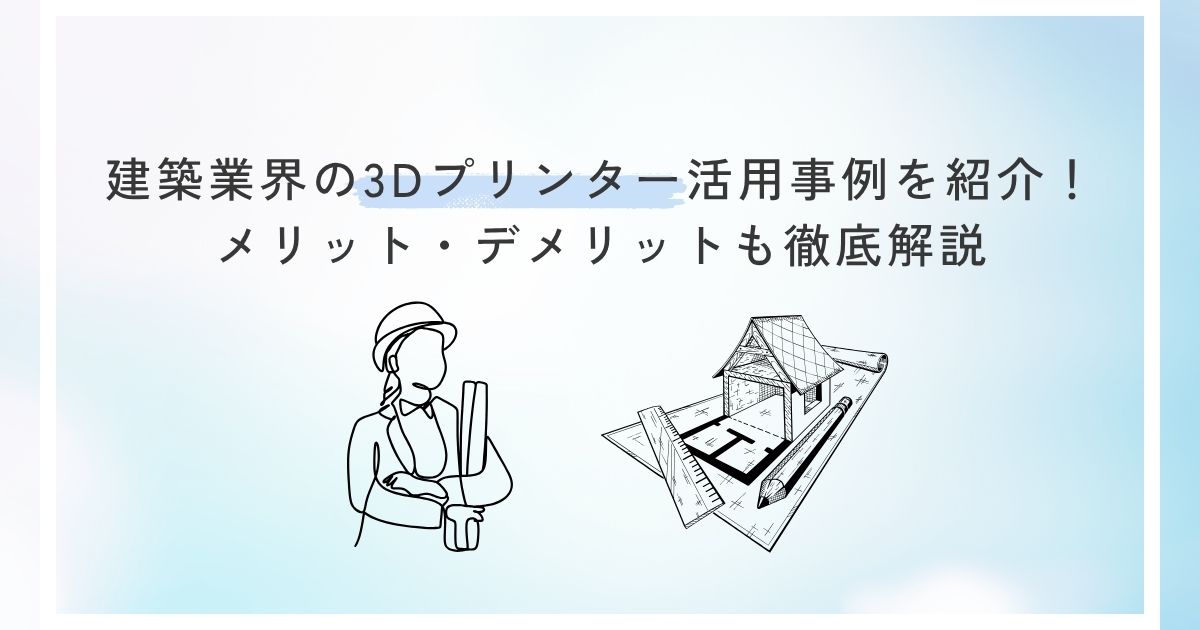
.jpg)