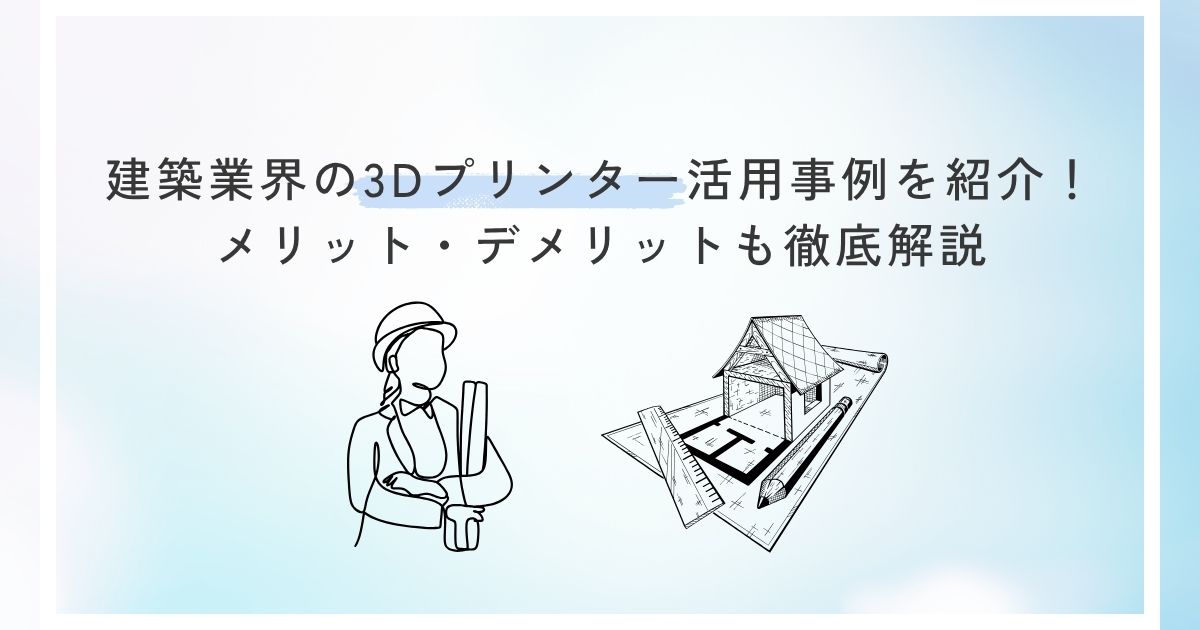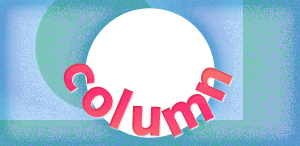
人生の指針となるようなインタビューや、スキマ時間にお楽しみいただけるコラムを紹介します。
2025.10.06
建築設計と働く喜び ── 第4回 竹村優里佳
.jpg)
建築人を豊かにすることを目指すA-magazineが、建築設計に携わる人びとが建築設計のどのような点に働く喜びを見出しているのかをシリーズで紹介する”建築設計と働く喜び”。第4回は、大阪・関西万博で若手建築家を対象としたコンペで選定され、トイレの設計に携わった竹村優里佳さんに寄稿していただきました。
======
背景
初めまして、現在奈良と海外(サンフランシスコ)を拠点に建築を設計している、Yurica Design & Architectureの竹村優里佳です。
元々奈良の三輪という場所の出身で、大神神社という日本最古の神社の麓で生まれ育ちました。その後大学院まで関西で学び、東京で最初のキャリアを積みホテルや学生寮の設計に従事しました。大学院時代にモナッシュ大学というオーストラリアの大学と長期のプロジェクトで協働したことをきっかけに日本以外の人たちと建築をつくる新しさと楽しさ、言語よりも空間性を通じて案が発展する現場を体感しました。社会に出た後も、偶然にも海外のクライアントやクリエイターと協働して建築をつくる機会などに恵まれました。こうした経験から言語や文化を超えて建築というひとつのものをつくりあげる可能性の片鱗を感じ、地元である奈良と海外の両方を拠点に活動するに至りました。
高校時代、桂離宮の月波楼を見た際に、古きの中に新しさのようなものがあり、当時の「月を見る」という習慣や時代感覚が建築によって現代まで引き継がれていることに感動しました。建築家を志すきっかけとなった出来事です。
奈良の身の回りを見渡しても、前述の大神神社やコンビニよりも数の多い古墳群などの「原初的なもの」と、さまざまなチェーン店が幹線道路沿いに立ち並ぶ「近代的なもの」は見事に分断されています。「原初的なもの」はかつてから当たり前にある場所として、説明的な情報のみを付与されて、近代の都市計画からは除外され、生活とは無縁の場となってしまっています。
こうした背景から、この2つをブリッジするような何か、あるいは原初的なもの(日本的なもの?)の延長線上にある建築を考えてみたいと思うようになりました。
自然と時間を耕す建築へ
現代社会は大地震やパンデミック、世界の分断といった混沌の中にあり、さらに情報や技術の急速なデジタル化とAI化によって、物質的には豊かであっても人間の感性や伝統的な技術、自然や文化といった「見えないが大切なもの」が知らず知らずのうちに失われつつあります。こうした時代において、Yurica Design & Architectureは、建築を通じて「過去の記憶と価値を未来へひらく」ことを目指す思想──オープンノスタルジア(Open Nostalgia)*──に基づき、活動を続けています。
オープンノスタルジアとは筆者が提唱する概念で、過去に閉じこもることなく、歴史や記憶、素材の声に耳を傾けながら、それらを未来へとひらく設計思想です。ノスタルジアを保存や模倣ではなく、「継承と変容」の契機と捉え、建築を通じて人と自然、時間と物質、そして地域との関係性を耕し直すことを志向します。
Traces of Earth / 地球の形跡
直近で竣工したプロジェクトとしては、大阪・関西万博でのプロジェクト(「Traces of Earth / 地球の形跡」)があります。
近代の都市では合理性の観点から、石は薄くスライスされ、均質化された同じ大きさの規格材となり建築の装飾的な部分を彩る要素として用いられることが一般的です。しかしひとつひとつの石がもつ多様な表情や大きさを建築に取り込むことで、設計の中に「予測不可能性」をパラメーターとして取り込み、人間だけでは完結しない、人の想像を超えた建築をつくることができるのではないかと考えました。
デジタルテクノロジーによって石の正確な大きさ・重さ・重心をアーカイブし、石工さんたちの職人技術とハイブリッドさせることで、石場建工法を再解釈しながら石を立て、建築をつくっていきました。
ここでは16世紀に大坂城の石垣再建のために大変な労力で切り出されたものの、使われずにそのままになっていた巨石を用いて建築を設計しました。
万博の会場はほとんど何のコンテクストもない敷地です。そこにある種のノスタルジアをもつこの石を用いて建築をつくることで、多くの人たちが”大阪・関西万博”という地で行われる建築を自分ごと化したり、興味をもつきっかけを与えることを意図しました。加えて何かこれまで続くものの延長線上にこの出来事を位置付けられるのではないかと考えました。
そのような石は後世の人たちが、「せっかく大阪に行くために切り出されたのに、行けなくてかわいそう・残念」という想いを寄せたことから「残念石」と呼ばれていました。関西の各地に複数散らばっているなかで、今回貸していただくことになったのは、京都府木津川にある石です。当時、その石があるエリア一体で高速道路の工事が行われるため、全てを埋めてしまうか、あるいは保存や活用の道があるのか、といったことが未確定で「残念石、400年経てもなお残念」という見出しで新聞記事になった矢先でした。
こうした文化的には貴重であるものの、さまざまな理由で埋められそうになっていたり失われる危機に瀕しているものが、この石に限らず多くあることを同時に知りました。
これまで多くの人に見過ごされてきたものが、みんなで巨石を運び、石を立て、そこに人の居場所となる空間が出来上がることで、多くの人びとに注目され、より親しまれる存在となりました。それを可能にしたのは建築の力であり、万博という公共的なプロジェクトだからこそ、誰のものでもない石をみんなで運ぶということが可能になったのだと思います。
全てのことに意味や理由が求められる社会だからこそ、”巨石を運ぶ”という誰の利益にもならない行為に、なぜか人びとはワクワクと心を躍らせ、多くの人びとがこのプロジェクトに協力者として参加してくださいました。
こうした状況は、「残念石」という400年前の人が切り出した石そのものの魅力も然り、その歴史的背景も然り、またこれらを現世まで大切に言い伝えて守ってきた地域の方々の想いがあったからこそ生まれたものです。そしてそれらが奇跡のようなタイミングで重なったことで、今回の建築(「Traces of Earth/地球の形跡」)というかたちで完成し、多くの方にこのプロジェクトの意義を理解していただくことにつながりました。それは単に情報を掲示するだけではなく、場所としての建築が出来上がり、訪れた人とその場を共有することができて初めて可能になったことだと考えています。

完成した「Traces of Earth/地球の形跡」©yosuke ohtake
建築をつくることを通して新たに獲得されるもの
建築をつくる、という行為は捉え直すと、建物をただ物質的につくることにとどまらず、今回のように賛否両論を巻き起こしながらも、今既にある価値を揺さぶりながら何かを前に進めるためのエネルギーにもなりうるのではないでしょうか。「建築は近代で稀に見る”誰でも参加できる”唯一の行為(仕事)かもしれない」と建築史家の藤森照信さんも言及されています。関わりしろを開きながら建築をつくっていくことが、単純に建物を建てるだけでなく、忘れていたものを取り戻していく行為なのではないか、そこに建築の可能性があるのではないかと私は考えています。
そうした広義の意味での”建築をつくる”ことに、これからも挑戦していきたいです。
————————————————
*Open Nostalgia(オープン・ノスタルジア)とは、過去を再現や修復の対象とするのではなく、その記憶や痕跡を未来にひらいていくための創造的な態度です。この概念は、スヴェトラーナ・ボイムが提示したふたつのノスタルジーの類型、すなわち「復旧的ノスタルジー」と「反省的ノスタルジー」の中でも、特に後者に親和性をもちながらも、それをさらに拡張するものです。
復旧的ノスタルジー(restorative nostalgia)は、「失われた過去の完全な回復」を目指し、しばしば国家的記憶やイデオロギーと結びつきます。それは「過去の真実」を唯一のものとして仮定し、歴史を修復可能な構造物として捉える態度です。一方、反省的ノスタルジー(reflective nostalgia)は、過去を再現することの不可能性を認識し、その断絶や矛盾を抱えたまま記憶と向き合うものです。
Open Nostalgiaはこの反省的態度を踏まえつつも、さらに「開かれた生成の場」としてのノスタルジアを提唱します。過去の物質や風景、記憶を単なる鑑賞や記録にとどめるのではなく、それらが現代において新たな意味や価値を生み出すための素材として作用する場をつくりだす。これは、過去と現在、そして未来が交錯するプロセスを肯定し、「完成」ではなく「変容し続ける関係性」として建築や空間を構築していく試みです。
懐古ではなく、記憶の運動を未来へとひらくものであり、記憶を閉じ込めるのではなく、そこに多声的で動的な可能性を見出す態度として建築を考え始めるコアのような位置付けとして考え続けています。
————————————————
(企画・編集:ロンロ・ボナペティ)
竹村優里佳
YuricaDesign&Architecture主宰
yuricadesign一級建築士事務所株式会社代表取締役
1991年 奈良県三輪生まれ
2015年 近畿大学建築学部環境都市デザイン学科卒業
2016年 立命館大学スタジオデザインプログラム Monash University(オーストラリア)との半期共同研究スタジオを修了
2017年 立命館大学大学院理工学研究科環境都市専攻建築都市デザインコース卒業
2022年 大阪・関西万博若手建築家優秀若手提案者20組に選出
主な受賞歴に、日本建築学会設計協議優秀賞(2018年)、淡河本陣リノベーションデザインコンペ最優秀賞(2017年)他多数。




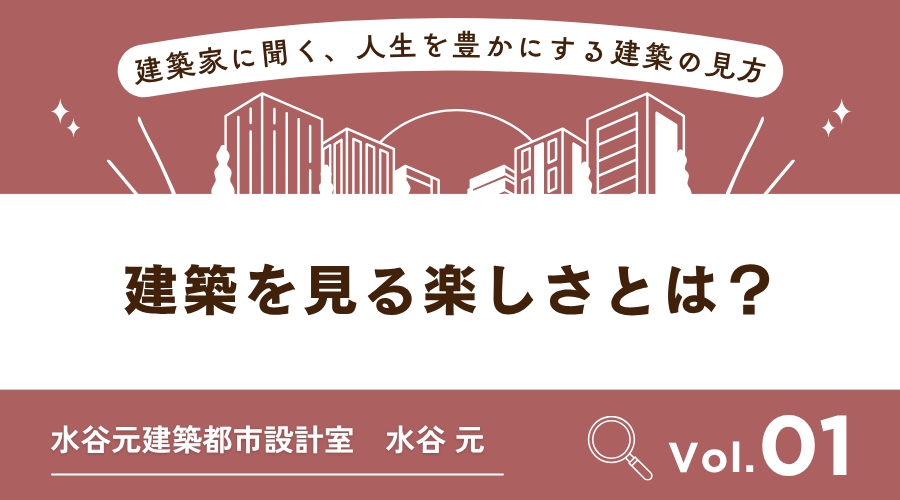
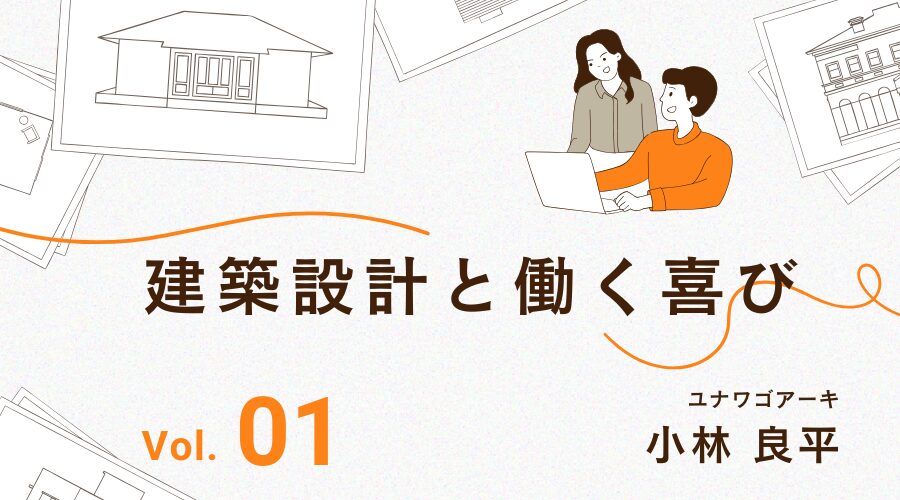
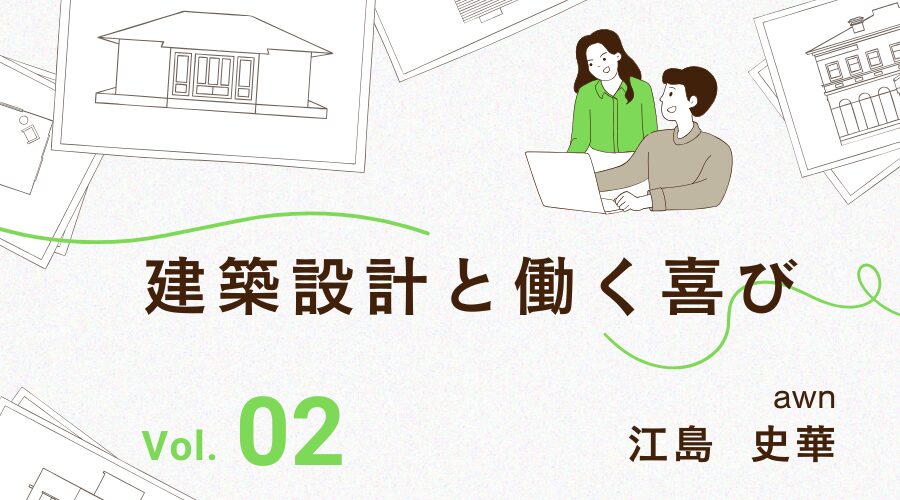

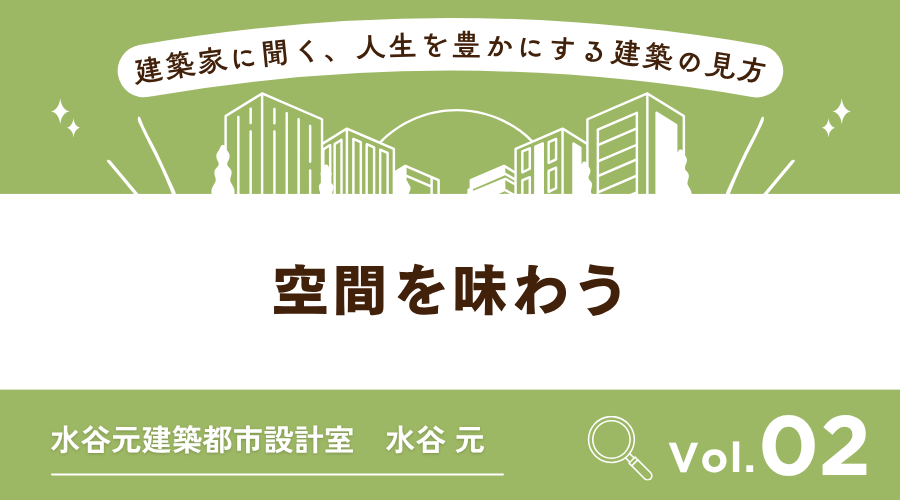
が設計した金沢21世紀美術館-21st-Century-Museum-of-Contemporary-Art-Kanazawa-DesignSANAA.jpg)
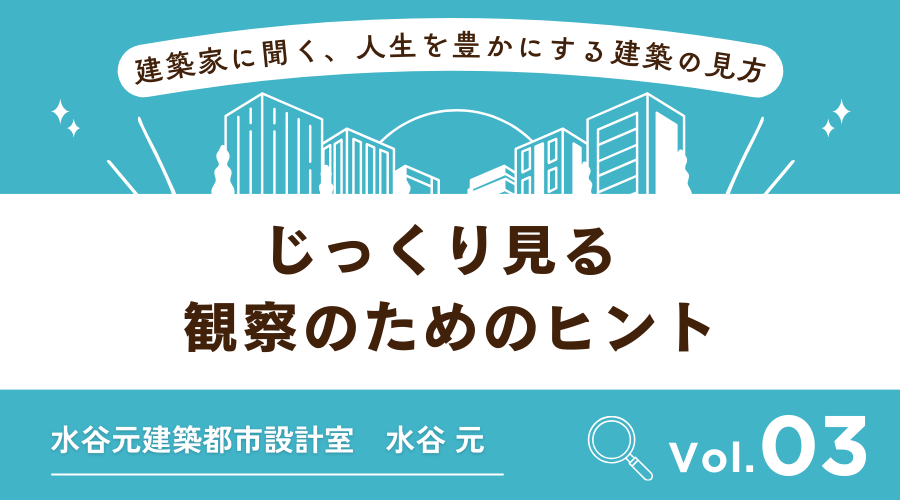

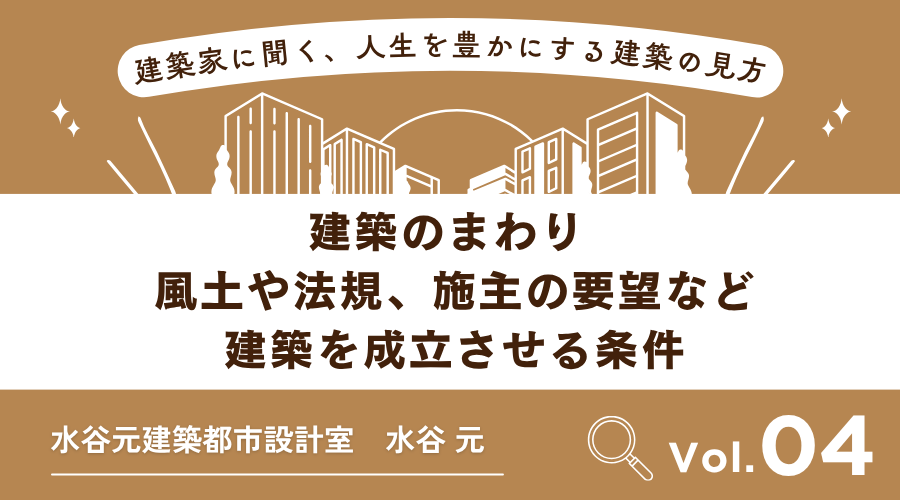
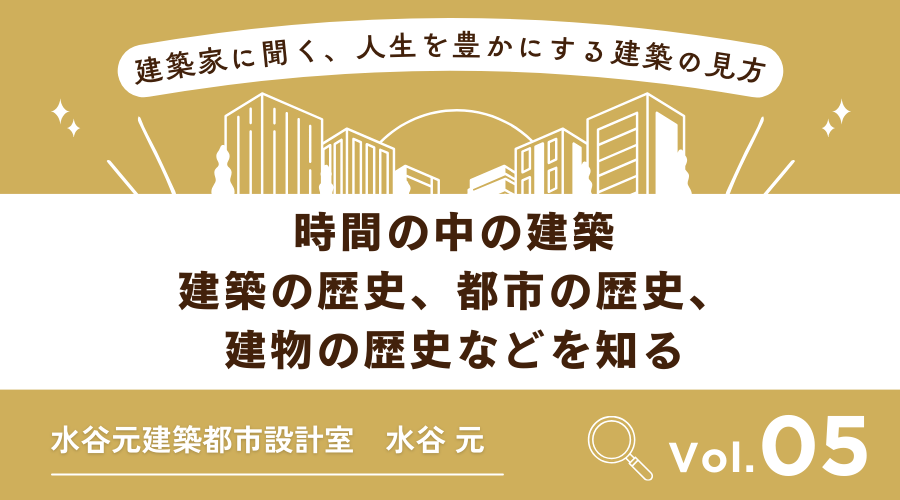
.jpg)