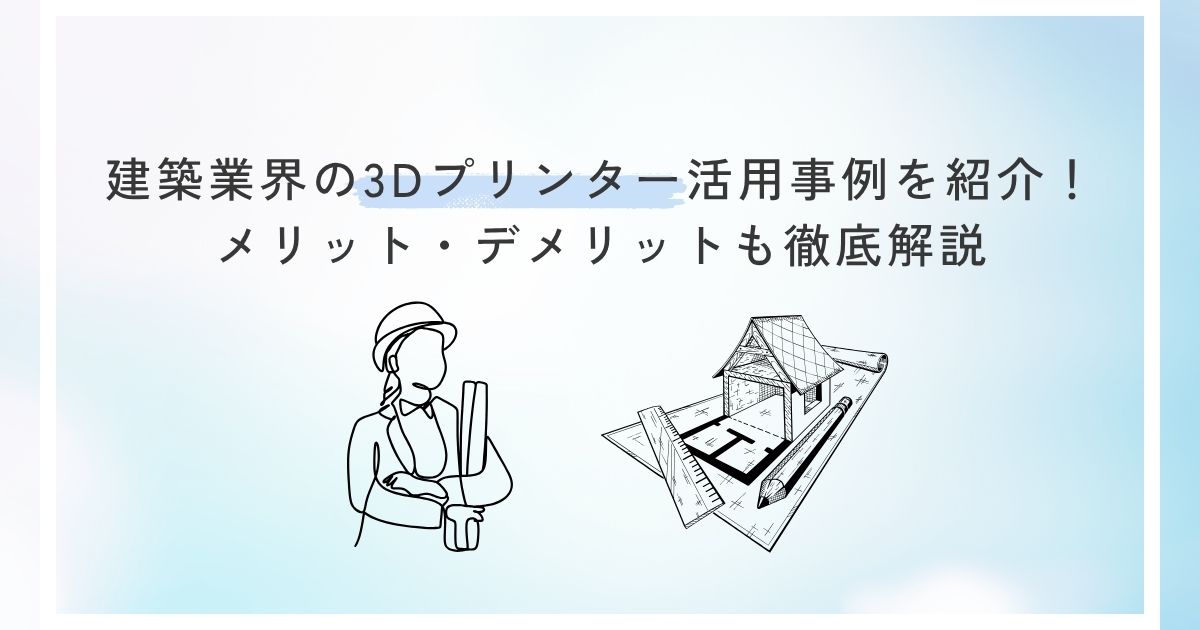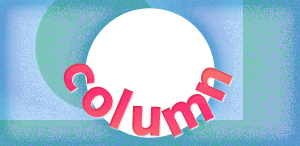
人生の指針となるようなインタビューや、スキマ時間にお楽しみいただけるコラムを紹介します。
2025.08.18
【体験談】工務店と建築設計事務所どっちに就職すべき?設計士の仕事内容・働き方の違い

みなさん、こんにちは!
mono monoです。
建築系の就職先は多岐にわたりますが、その中で設計を目指す人の選択肢の中には設計事務所や工務店、ハウスメーカー、ゼネコンの設計部などがあると思います。
今回は設計事務所と工務店に絞ってその違いなどをご紹介できればと思います。
私はアトリエ系の設計事務所(4年間)と工務店(1年間)に勤めたことがあります。
実際に働いてみて、それぞれ設計事務所と工務店では具体的にどのような仕事内容なのかを知ることができたと思います。その違いなど、お伝えできればと思います。
ただし私はそれぞれ1社ずつしか行っていませんので、あくまで私が働いたことのある会社での比較になってしまいますが、大きなところはそれほど違う会社であっても変わらないのではないかと思います。
設計事務所のこと
わたしは大学の頃は意匠系の研究室に所属していました。研究室の先生は建築家の方で実際に先生の作品を見たり、先生から建築のお話を聞くうちに建築のおもしろさを知っていったと思います。
「建築は簡単な方がいい。」
「自分が建てると思って設計する。」
「この建築は素晴らしい。あの建築は良くない。」
などさまざまな言葉を聞く内に、建物を設計することの奥深さを知ったり、自分の中でいい建築とはどういうものかという一種美意識のようなものを持つことの大切さを学んでいったと思います。
また、私は建築家という人自体をおもしろいと思いました。建築家はそれぞれの人が建築に対する独自の考え方を持っていて、それを建築という自分より大きなものをつくって、ある意味表現するということはすごいことだと思います。
そんな中で建築家とはどんな仕事をするのか知りたいと思ったのが設計事務所を選んだ理由です。
まず設計事務所の仕事の内容ですが、基本的に「設計」と「現場監理」が主な仕事になります。
「設計」については、設計事務所ではさまざまな案件を受けることが多いため、その時々の物件に合わせて、お客様の要望を聞き、周辺環境や敷地の条件、決められた予算などの制約の中でいろいろな案を考えます。
私が仕事をしていた設計事務所では用途としては住宅や店舗兼用住宅が多く、新築や改修の物件がありました。
検討は図面のほか、模型や3Dモデルでも検討をしていました。工務店では模型や3Dモデルで検討する会社はあまりないかもしれませんね。
というのも、設計事務所は基本的には毎回物件ごとに違うことをしようとするので、都度確認や検討が必要なのですが、工務店ではある程度出来上がる建物のイメージは変わらないので確認が必要ないといえるのかなと思います。
扱う物件は設計事務所の過去の実績を確認すれば、どのような用途の建物が多いかや建物の規模感、新築・改修どちらが多いかなど分かると思います。
また、設計事務所では、一人の建築家がいて、その建築家の作風を推しているので、それぞれの事務所が強い個性を持っていると思います。
日本には建築家がたくさんいますし、首都圏に限らずローカルなところで活動されている方もいて、場所も違えばつくる建物も違います。建築系の学生であれば大学の設計課題の際にさまざまな建物を参考にしたり、建築を見たりする体験の中で、自然と建築家の作品に触れることもあり、設計事務所では独自性のある建物を設計するというイメージはつきやすいのではないでしょうか。
大学との違いとしては、実際に建つということが大きな違いで、大学で行わないこととして敷地の詳細な調査をしたり、法令への適合確認 (確認申請と呼ばれるもののために図面作成等)をしたり、予算のなかで何ができるかを検討したりします。
異なる部分もありますが、ある意味、大学の設計課題の延長という言い方もできると思います。
工事は施工をしてくれる会社である工務店(後半で書いている工務店と同じものです)にお願いする形になります。
設計事務所は基本的に全国、場合によっては国外の物件の場合もあり、各物件に応じて工務店を探してお願いする形になります。
工事に進んでからは、「現場監理」といって図面で指示していることが、きちんと現場でできているかの確認をします。
現場監理では工事が進む中で、大枠はあまり変わることはありませんが、細かな部分の検討をするので部分的な変更は必ず起きます。
また、図面が納まっていないことが分かったり、現場サイドからこのように施工できないか、という相談を受けたりします。そのような変更事項に対して、都度答えていく作業が現場が始まってからは続いていきます。
働いている人は大学を卒業したばかりの人が多く、将来建築家として独立したい人が多いと思います。
ですので、働いている年齢層としては若いと言えるのではないでしょうか。
ある程度人数のいる事務所ですと番頭さんという経験を数年ほど積んだ人がいたり、パートナーという形で事務所の恒久的なメンバーとして事務所を支える人もいます。
給与は一般的にあまり高くないところが多いと言われていますが、具体的には各会社によると思います。
私が仕事をしていた設計事務所では給与は普通の建築系の会社よりは少なかったですが、保険関係(健康保険、社会保険など)は完備されていました。
最近は以前に比べると就業環境は改善されてきたと言われていると思います。
工務店のこと
設計事務所で4年間勤務した後は少し興味が移って、建築の施工のことをもう少し知りたいと思いました。
設計事務所にいるときには工務店の担当の方とやり取りをするので、大工さんや左官屋さん、電気屋さんなどたくさんいる職人の方と直接お話しすることはあまりできません。
職人さんがどのようにして工事をするのかをもっと知りたいと思って、その中の手段のひとつに工務店に入るという選択肢がありました。
工務店は、「設計」に加え、「施工」までを請け負うところが大きく異なると思います。
設計事務所では設計をし、工務店に見積りをお願いするところまでを行いますが、工務店では自社で見積りをし、施工までを担います。
工務店では物の発注から現場への搬送、現場での組み立てまでさらに広い範囲で見ることができると思います。
具体的には木を切り出す山に木材を発注したり、それを加工するプレカット屋さんとやりとりをしたりもします。
また図面から材料を拾い出して発注したり、それを何トンのトラックで現場にどういうルートで入れるのか確認したりもします。
これらは施工の中のほんの一部分ではありますが、関わる人が増えますし、業務もだいぶ範囲が広くなるといえると思います。
工務店によっては施工のみを請け負うところもありますが、設計まで含めて請け負うことで強みを出している会社が多いのかなと思います。
工務店では自然素材を使い、住環境に配慮したところを強みにしているところが多いです。
例えば、高気密高断熱住宅などが挙げられますが、これは家が自然の暑さや寒さの影響を受けにくいようにし、また一度空調をつければ家全体ががすぐに快適な環境になってくれるというようなものです。
あまり実務をするまでは建築の環境のことを気にしないかもしれませんが、住宅などでは住み心地などとても大切なことだと思います。
このような機能的なことに加え、室内の床や壁・天井の仕上げや使うサッシ(窓)、外観に使う素材などの基本的な仕様も決まっています。
使う材料などが決まっているということはハウスメーカーにも言えることだと思いますが、より自然素材によっているというのが工務店の特色でしょう。
反対にハウスメーカーはなるべく手のかかりにくいメンテナンスフリーなどが一つ仕様を決める基準になっていると思います。
工務店に来られる方は自然素材が好きな方や工務店でつくられる木を感じられる家に住みたいというイメージを持って来られる方が多いと思います。
工務店でも設計事務所と同じように必要な部屋などの要望をお施主様からお聞きし、敷地を確認し、図面を作成したり、建築確認をしたりします。その後、工事に進んでいきます。
これは工務店に入って初めて意識したことですが、工務店とひとことに言っても、工務店の下にはさまざまな業種の取引先の業者さん、職人さんがいます。
建物の骨格を造る基礎屋さん、大工さんから仕上げをするクロス屋さん、カーペット屋さん、タイル屋さん、トイレや洗面、浴室などの設備機器や配管を取り付ける給排水設備屋さん、電気屋さん、さらには家具屋さんや外構屋さん、洗い屋さんなどここには挙げきれないほどの業種の方がいます。
これらの職人さんに現場で仕事をしてもらうための手配、段取りをするのが設計事務所との大きな違いだと思います。
実際に物を発注したり職人さんと関わる中で、より作り手サイドのプロセスを知ることができます。
給与面については一般的な建築系の会社とそれほど変わらないのではないかと思います。
簡単にはなっていますが、設計事務所と工務店の大きな違いはお伝えできたのではないかと思います。
参考になりますと幸いです。




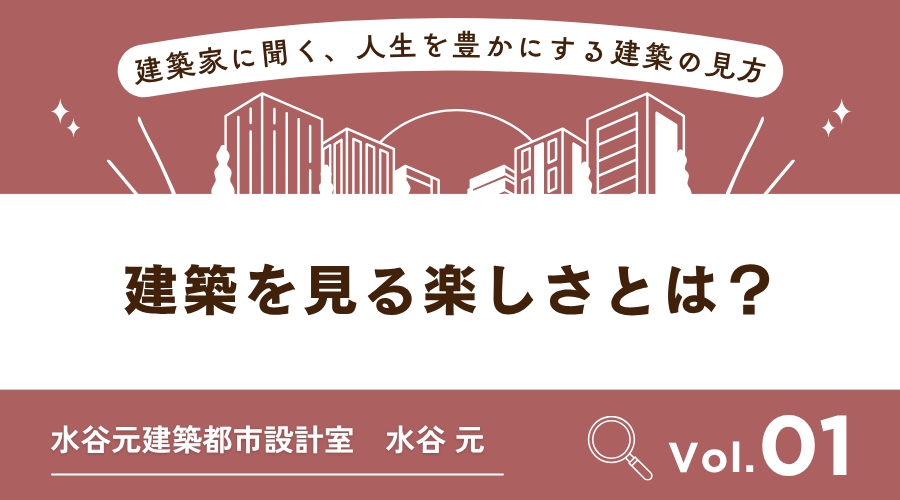
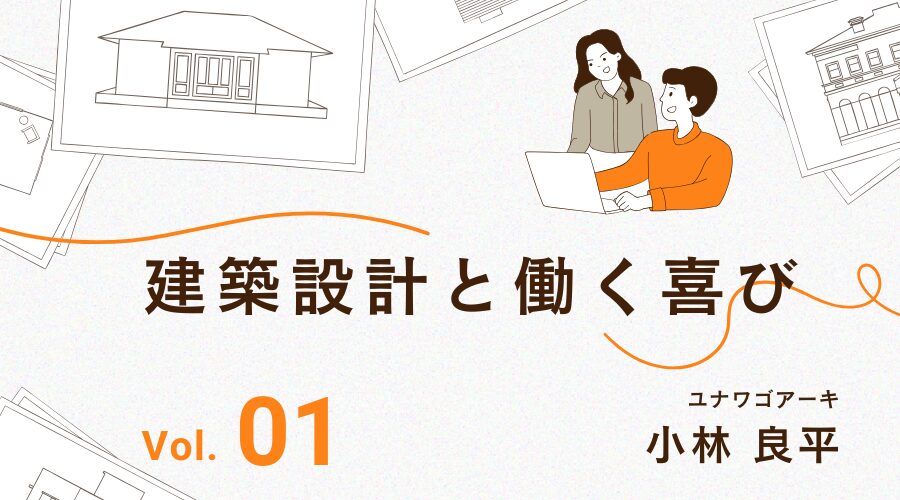
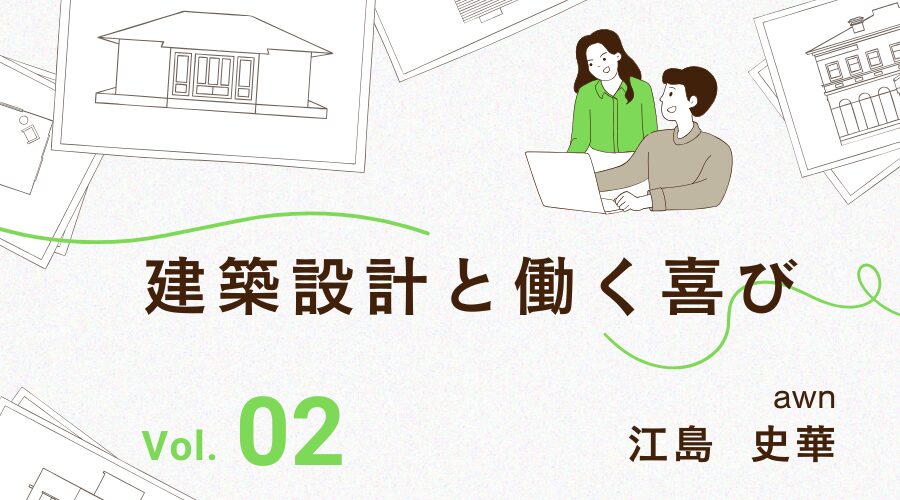

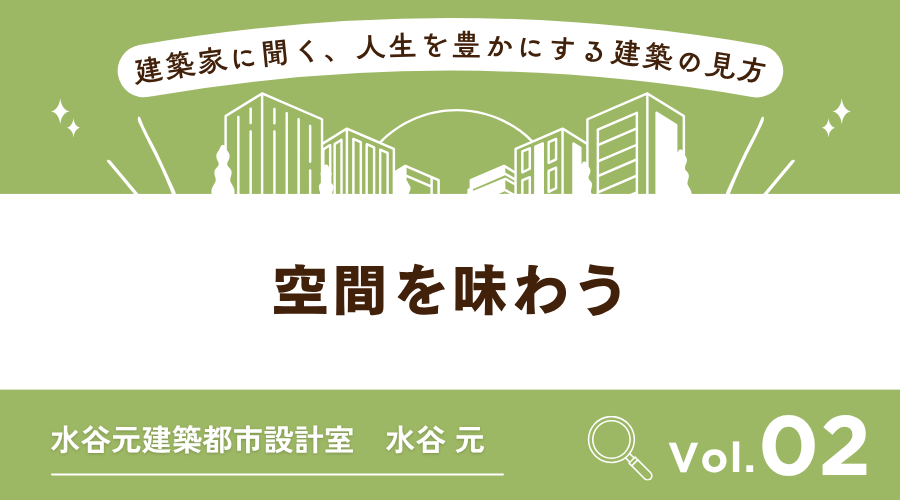
.jpg)
が設計した金沢21世紀美術館-21st-Century-Museum-of-Contemporary-Art-Kanazawa-DesignSANAA.jpg)
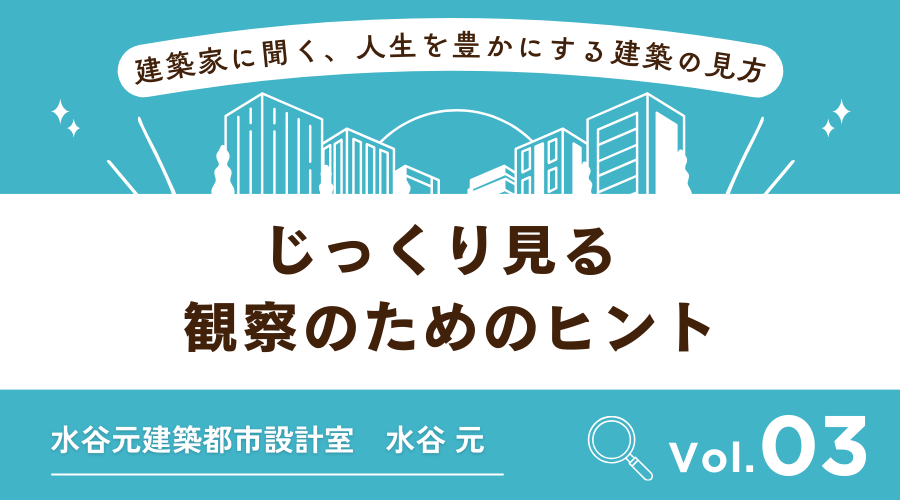

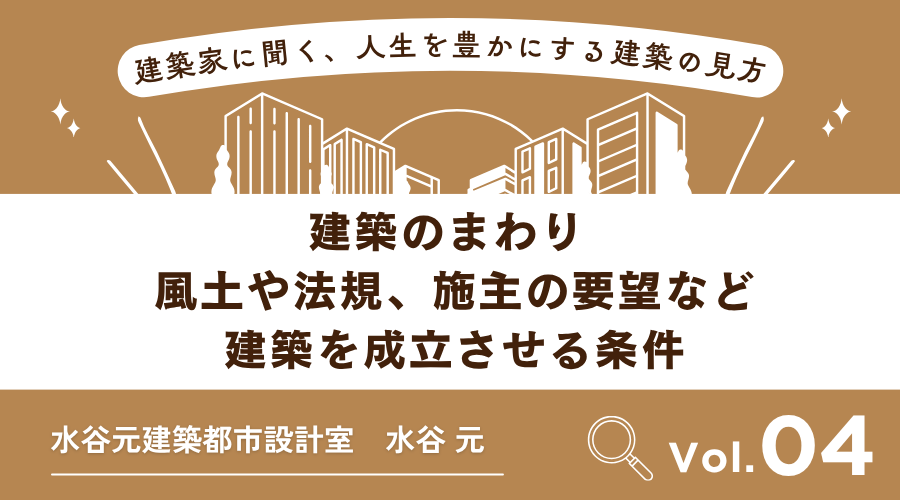
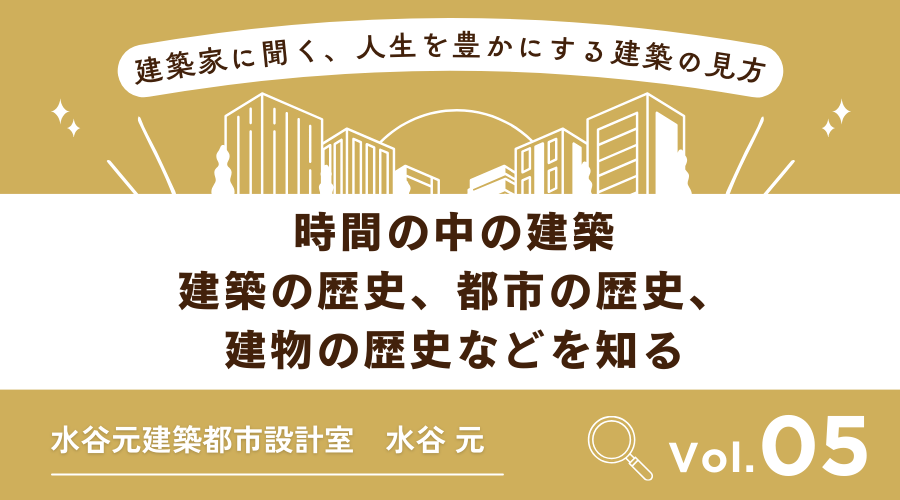
.jpg)