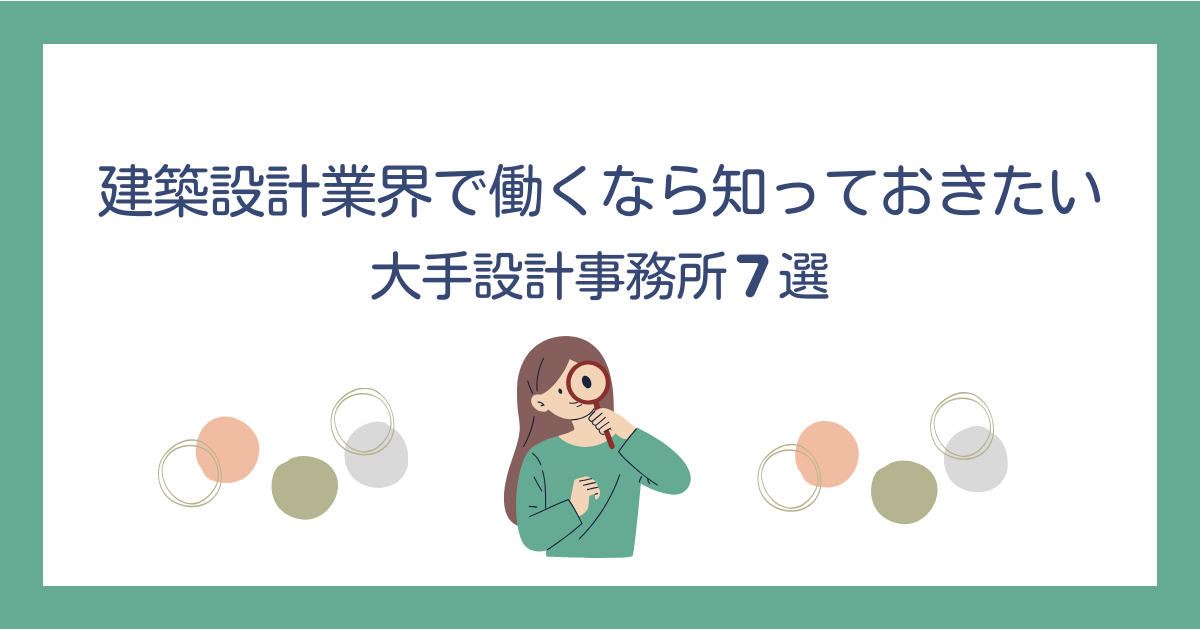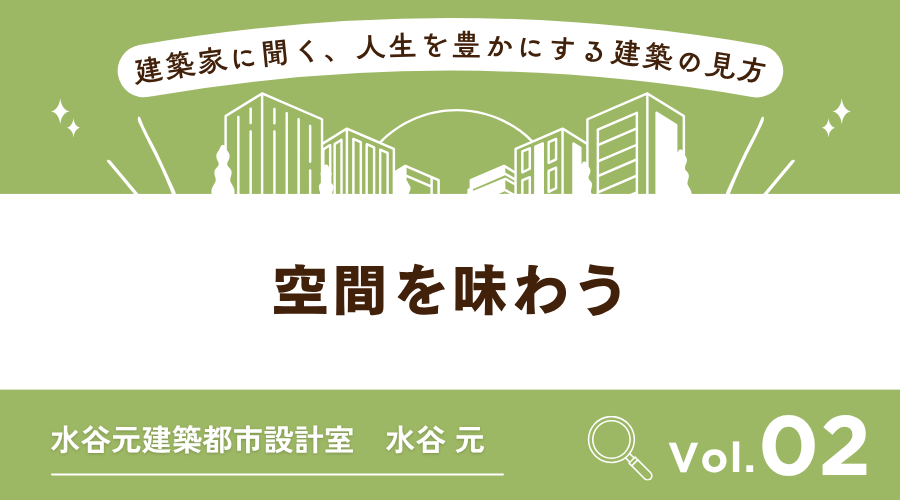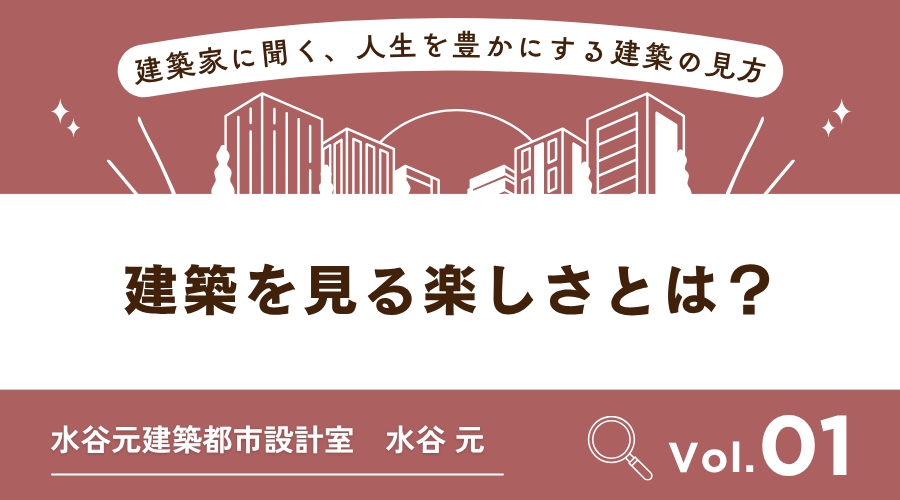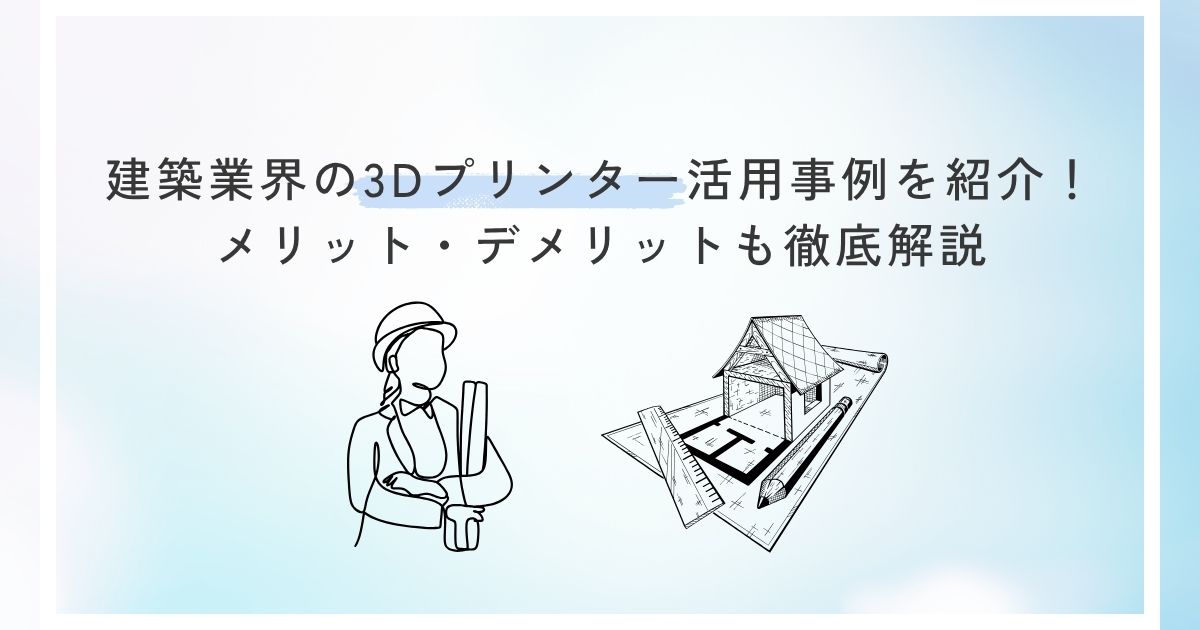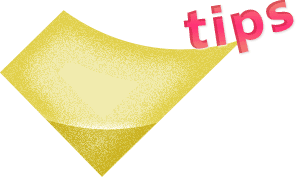
建築業界のリアルな情報や就職・転職活動で役立つ情報を紹介します。
2025.05.15
建築学科の研究室選択方法とは?研究室の特徴や主な就職先を徹底解説!

建築学科の学生にとって、研究室選びは将来のキャリアに影響を与える選択の1つです。
適切な研究室を選ぶことで、自分の興味ある分野を深く学び、卒業後のキャリアパスを切り開く第一歩となります。
本記事では、建築学科の研究室選択方法から各研究室の特徴、就職先について詳しく解説します。
研究室選びで迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

建築学科の研究室選択方法
研究室選びは単なる興味だけでなく、様々な要素を考慮する必要があります。
以下のポイントを参考に、自分に合った研究室を見つけましょう。
教員を尊敬しているか
研究室選びで最も重要な要素の1つが、教員を尊敬しているかどうかです。
教員の研究実績、専門知識、人間性などを総合的に見て、「この教員から学びたい」と思える存在であることが理想的です。
教員の著書や論文、過去の作品などに目を通し、その研究姿勢や考え方に共感できるかどうかを確認しましょう。
また、その教員の講義を受けたことがある場合は、講義のスタイルや内容から相性を判断できます。
教員との相性は良いか
尊敬できる教員であっても、相性が合わなければ研究活動はスムーズに進みません。
教員の指導スタイルや性格と自分の学習スタイルが合うかどうかは、研究生活の質に大きく影響します。
例えば、自主性を重んじる教員のもとでは、自ら積極的に研究を進める必要があります。
逆に、細かく指導してくれる教員もいます。
自分がどのような指導を受けたいのか、自分の性格を踏まえて考えることが大切です。
可能であれば、その研究室の先輩や卒業生から教員の指導スタイルについて事前に情報を得ておきましょう。
外部とのネットワークがある研究室か
建築業界では、実務経験やコネクションが重要になることも少なくありません。
外部の建築事務所や企業、研究機関とのネットワークが豊富な研究室であれば、在学中から実践的なプロジェクトに関わる機会が得られたり、就職活動の際に有利になったりします。
研究室が過去にどのような外部プロジェクトや共同研究に携わってきたか、企業との繋がりがあるかなどを調査しましょう。
また、卒業生がどのような進路に進んでいるかも参考になります。
興味がある分野なのか
最終的には、自分が本当に興味を持てる分野かどうかが最も重要です。
建築学は幅広い分野をカバーしているため、自分が深く学びたい分野と研究室の専門分野が一致しているかを確認しましょう。
例えば、建築デザインに興味がある場合は意匠系の研究室、構造計算や力学に興味がある場合は構造系の研究室というように、自分の関心に合った研究室を選んでください。
将来のキャリアプランと照らし合わせて、その研究室での経験が自身の目標達成にどう貢献するかを考慮しましょう。
研究室の特徴や主な就職先
建築学科の研究室は、専門分野によって様々なタイプに分けられます。
それぞれの特徴と主な就職先について見ていきましょう。
意匠系研究室
意匠系研究室は、建築のデザインや空間構成に焦点を当てた研究を行います。
美学、形態学、デザイン理論などを学び、建築の芸術的側面を追求します。
【特徴】
・建築デザインの理論と実践を学ぶ
・設計コンペなどに積極的に参加する機会がある
・モデル製作やCG制作などのビジュアル表現も重視される
・創造性が求められる
【主な就職先】
・建築設計事務所
・ゼネコン(設計部門)
・インテリアデザイン会社
・都市開発会社
・ハウスメーカー(デザイン部門)
計画系研究室
計画系研究室では、建築や都市の機能性や利便性に焦点を当て、効率的な空間配置や動線計画などを研究します。
人間の行動パターンや建築の使われ方を分析し、最適な建築計画を提案します。
【特徴】
・統計データや調査に基づいた客観的な研究
・建築の使われ方や人間の行動パターンを分析
・機能性、効率性、利便性を重視した設計手法を学ぶ
【主な就職先】
・建築設計事務所
・都市計画コンサルタント
・公共施設の計画部門
・不動産デベロッパー
・シンクタンク
住居学系研究室
住居学系研究室では、住宅や集合住宅に特化した研究を行います。
居住環境や住まい方の変化、家族構成の多様化に対応した住宅設計などを研究テーマとします。
【特徴】
・住宅の歴史や変遷を学ぶ
・実際の居住者の生活様式や満足度を調査
・新しい住まい方や住宅のあり方を提案
【主な就職先】
・ハウスメーカー
・住宅設計事務所
・マンションデベロッパー
・住宅関連メーカー
・不動産会社
構造系研究室
構造系研究室では、建築物の構造力学や構造設計に関する研究を行います。
建物の安全性や耐震性、新しい構造システムの開発などが研究テーマです。
【特徴】
・数学や物理学の知識を活かした研究
・構造計算や構造解析の手法を学ぶ
・実験やシミュレーションを通じた検証
・論理的思考力が求められる
【主な就職先】
・構造設計事務所
・組織設計事務所
・ゼネコン(構造設計部門)
・研究機関
・公務員(建築職)
材料系研究室
材料系研究室では、建築材料の性能や開発に関する研究を行います。
コンクリート、鋼材、木材、新素材などの特性や応用方法を研究し、より優れた建築材料の開発を目指します。
【特徴】
・材料実験や物性試験を行う
・材料の劣化メカニズムや耐久性を研究
・環境負荷の少ない材料開発にも取り組む
・化学や材料工学の知識が必要
【主な就職先】
・建材メーカー
・ゼネコン(技術研究部門)
・材料試験機関
・公的研究機関
・建築コンサルタント
建築構法・生産系研究室
建築構法・生産系研究室では、建築物の施工方法や建設プロセス、建築生産システムに関する研究を行います。
効率的な施工技術や品質管理手法の開発などが主なテーマです。
【特徴】
・建築の「つくり方」に焦点を当てる
・現場での施工技術や管理手法を研究
・BIMなどのデジタル技術の活用も含む
・実務と密接に関連した研究が多い
【主な就職先】
・ゼネコン(施工管理部門)
・建設会社
・ハウスメーカー(生産・施工管理部門)
・建設コンサルタント
・工務店
環境工学・設備系研究室
環境工学・設備系研究室では、建築環境や設備計画に関する研究を行います。
省エネルギー技術、室内環境の制御、自然エネルギーの活用などをテーマとします。
【特徴】
・建物の熱、光、音、空気などの環境要素を研究
・環境シミュレーションやモデリングを行う
・サステナブルな建築技術を探求
・設備設計の理論と実践を学ぶ
【主な就職先】
・設備設計事務所
・組織設計事務所
・ゼネコン(設備部門)
・設備メーカー
・環境コンサルタント
・エネルギー関連企業
歴史系研究室
歴史系研究室では、建築の歴史や様式、保存・再生に関する研究を行います。
古建築の調査や文化財の保存方法、歴史的建造物の活用などが研究テーマです。
【特徴】
・建築史や様式史を学ぶ
・文献調査やフィールドワークが多い
・文化財建造物の実測や記録作業も行う
・人文学的な素養も必要
【主な就職先】
・文化財関連機関
・建築設計事務所(保存・再生部門)
・公務員(文化財保護関連)
・博物館・美術館
・教育・研究機関
都市計画・まちづくり系研究室
都市計画・まちづくり系研究室では、都市の構造や機能、計画手法に関する研究を行います。
持続可能な都市づくりや地域活性化、都市の課題解決などをテーマとします。
【特徴】
・都市の空間構造や土地利用を研究
・地域住民との協働プロジェクトも多い
・社会学や経済学の知識も必要
【主な就職先】
・都市計画コンサルタント
・公務員(都市計画部門)
・不動産デベロッパー
・まちづくり団体・NPO
防災系研究室
防災系研究室では、建築や都市の防災・減災に関する研究を行います。
耐震設計、火災安全、避難計画、災害復興などをテーマとします。
【特徴】
・災害リスク評価や被害予測を行う
・防災計画や避難シミュレーションを研究
・災害後の復興プロセスも研究対象
・社会的意義の高い研究が多い
【主な就職先】
・防災コンサルタント
・ゼネコン(技術研究部門)
・公務員(防災部門)
・研究機関
・損害保険会社
ランドスケープ系研究室
ランドスケープ系研究室では、建築と外部空間の関係や景観設計に関する研究を行います。
公園やオープンスペースの計画、都市緑化、ランドスケープデザインなどがテーマです。
【特徴】
・建築と外部環境の関係性を研究
・植物や生態系に関する知識も学ぶ
・デザインと環境の両面からアプローチ
・多様な空間スケールを扱う
【主な就職先】
・ランドスケープ設計事務所
・造園会社
・都市計画コンサルタント
・公園管理団体
・公務員(公園緑地部門)
学部卒なら研究室と就活はほとんど関係ない
建築学科の学生の多くは、研究室選びが就職に直結すると考えがちです。
しかし、学部卒業後に就職する場合は、研究室の専門分野と就職先が必ずしも一致するわけではありません。
特に、大手ゼネコンや住宅メーカーなどは、専門分野よりも総合的な能力や適性を重視する傾向があります。
多くの企業は新卒者に対して、入社後に専門知識や技術を身につけさせるための研修プログラムを用意しています。
そのため、研究室での専門性よりも、建築学の基礎知識や問題解決能力、コミュニケーション能力などが評価されることが多いのです。
ただし、研究室での活動や研究テーマが就職活動の面接で話題になることはあります。
自分の研究内容を分かりやすく説明し、そこから得た知見や成長を伝えられるように準備しておくことは重要です。
また、構造設計事務所や設備設計事務所など特定の専門分野での就職を目指す場合は、関連する研究室での経験が有利に働くこともあります。
修士課程や博士課程に進学する場合は、研究室の専門性がより重要になってきます。
特に研究職や高度な専門職を目指す場合は、研究室選びと将来のキャリアパスの整合性を意識しましょう。
研究室選択〜卒業研究までの流れ
研究室選択から卒業研究までの一般的な流れを解説します。
1.研究室の候補を出す
2.研究室の教員と面接する
3.研究室が決定する
4.卒業研究をする
大学によって異なる部分もあるため、詳細は各大学に問い合わせるのがおすすめです。
①研究室の候補を出す
まず、自分の興味のある分野や将来のキャリアプランを考慮して、いくつかの研究室の候補を挙げましょう。
研究室のホームページや過去の研究実績、卒業論文のテーマなどを調査し、情報収集を行います。
また、研究室見学や研究室説明会に参加したり、その研究室に所属する先輩から話を聞いたりすることで、研究室の雰囲気や日常的な活動内容を把握できます。
②研究室の教員と面接する
多くの大学では、研究室配属前に教員との面接が行われます。
この面接では、研究に対する意欲や適性、研究テーマの希望などについて質問されることがあります。
面接に向けて、自分がなぜその研究室を志望するのか、どのような研究をしたいのか、将来どのようなキャリアを目指しているのかなど、自分の考えを整理しておきましょう。
面接は双方向のコミュニケーションの場でもあります。
教員へ積極的に質問し、研究室の雰囲気や指導方針について確認することも大切です。
③研究室が決定する
面接や希望調査の結果を基に、研究室の配属が決定します。
配属方法は大学によって異なります。
例えば、希望者が多い人気研究室では、成績順や選考が行われることもあるのです。
研究室の決定後は、できるだけ早く研究室の活動に参加し、先輩や教員とコミュニケーションを取ることで、スムーズに研究活動に移行できます。
④卒業研究をする
研究室に配属されると、卒業研究のテーマ決めから始まります。
教員と相談しながら、自分の興味のある分野や研究室の専門性に合ったテーマを設定しましょう。
テーマが決まったら、先行研究の調査、研究計画の立案、データ収集や実験、解析、考察、論文執筆という流れで研究を進めていきます。
定期的に中間発表や進捗報告を行い、教員や先輩からのフィードバックを受けながら研究を深めていくのが一般的です。
卒業研究は自主性が求められる活動です。
計画的に進め、困ったことがあれば積極的に教員や先輩に相談しましょう。
教員と面接する際に準備すべきもの
研究室の教員との面接を成功させるためには、適切な準備が必要です。
以下のものを用意しておくと、より充実した面接になるでしょう。
ポートフォリオ
特に意匠系や計画系の研究室を希望する場合は、これまでの設計課題や作品をまとめたポートフォリオを準備しましょう。
ポートフォリオには、自分の設計思想や得意分野が表れるものを選び、見やすくまとめることが重要です。
デジタルデータとプリントアウトの両方を用意しておくと、面接の状況に応じて使い分けることができます。
卒業研究に関する企画書
研究室で取り組みたい研究テーマや問題意識を簡潔にまとめた企画書を準備しておくと、教員に自分の研究への意欲や方向性を伝えやすくなります。
企画書には、研究の背景や目的、方法論、期待される成果などを盛り込みましょう。
ただし、あまり細かい部分まで内容を固める必要はありません。
教員のアドバイスを受けて修正できる余地を残しておくことも大切です。
進路に関する希望
自分が将来どのようなキャリアを目指しているのかを明確にしておくことも重要です。
大学院進学を考えているのか、就職を考えているのか、どのような業界や職種に興味があるのかなど、現時点での希望や考えをまとめておきましょう。
教員はこうした情報を基に、より適切な研究テーマの提案や指導方針を検討できます。
また、研究室が持つ企業とのネットワークなどを活かした就職支援も期待できるかもしれません。
研究室の決定方法は大学ごとに異なる
研究室の配属方法は大学によって様々です。
主な決定方法とその特徴を見ていきましょう。
人数制限なし
一部の大学では、研究室ごとの人数制限を設けていない場合があります。
学生の希望を最大限尊重するこのシステムでは、自分の第一希望の研究室に入りやすいのがメリットです。
ただし、人数が多くなると一人当たりの指導時間が減ったり、研究スペースが手狭になったりするデメリットもあります。
人数制限あり
多くの大学では、研究室ごとに受け入れ可能な学生数を設定しています。
これにより、教員一人当たりの負担を調整し、指導の質を確保できるのです。
人数制限がある場合、希望者が多い研究室では何らかの選考が行われます。
成績順や面接結果、研究計画書の評価などに基づいて決定されることが多いです。
じゃんけんや抽選
一部の大学では、希望者が多い研究室の配属をじゃんけんや抽選で決める場合もあります。
抽選方式の場合、第二希望や第三希望も考慮されるシステムになっていることが多いため、複数の研究室について情報収集しておくことが重要です。
成績順
成績を基準に研究室配属を決める大学も少なくありません。
成績上位者から希望の研究室を選ぶことができるため、人気の研究室に入るためには日頃からの学習が重要です。
この方式では、早い段階から志望研究室を意識して関連科目の成績向上に努めることが求められます。
また、成績だけでなく、その研究室の教員が担当する授業での取り組み姿勢なども評価されることもあるでしょう。
まとめ
建築学科の研究室選びは、自分の興味のある分野や将来のキャリアプラン、教員との相性などを総合的に判断する必要があります。
各研究室には特色があり、それぞれ異なる進路に繋がる可能性を持っています。
学部卒業後すぐに就職する場合は、研究室の専門性が就職先に直結するわけではありません。
しかし、研究活動を通じて得られる専門知識や問題解決能力は、どのような進路を選んでも必ず役立ちます。
研究室選択から卒業研究までの流れを理解し、事前に十分な準備をすることで、充実した研究室生活を送ることができるでしょう。
研究室選びは自分の人生の重要な岐路の1つですが、完璧な選択はありません。
どの研究室に入っても、積極的に学び、挑戦する姿勢があれば、必ず成長できる場になります。
自分の直感や情熱を大切にしながら、最適な研究室を選んでください。