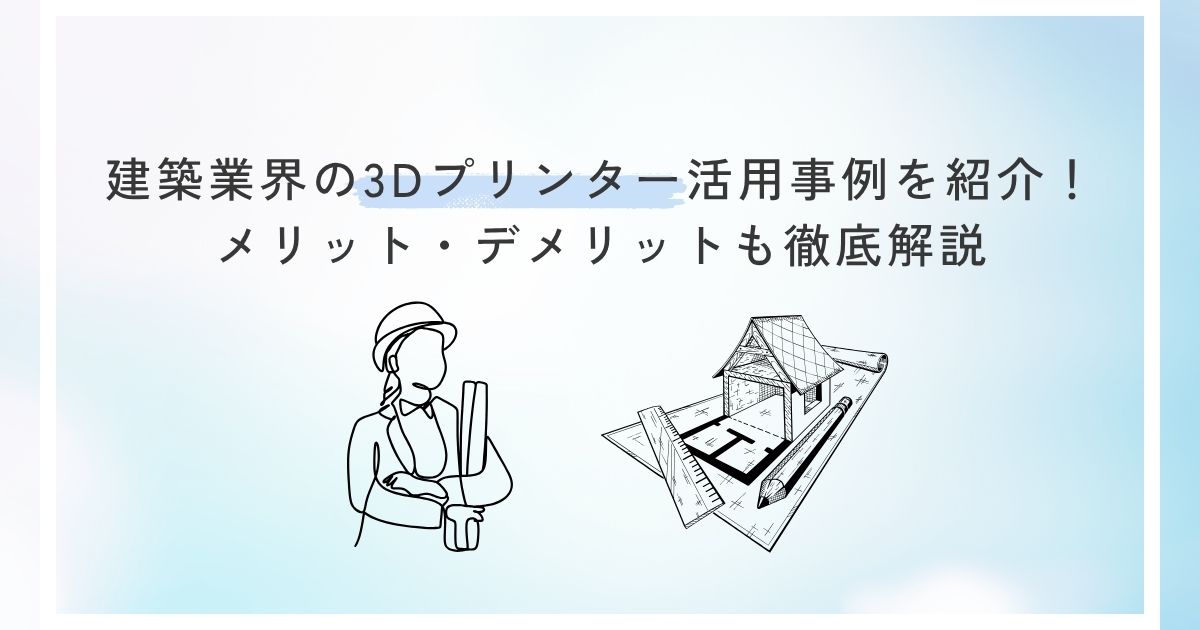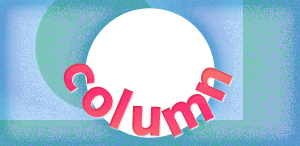
人生の指針となるようなインタビューや、スキマ時間にお楽しみいただけるコラムを紹介します。
2025.03.21
建築設計と働く喜び ── 第1回 小林良平
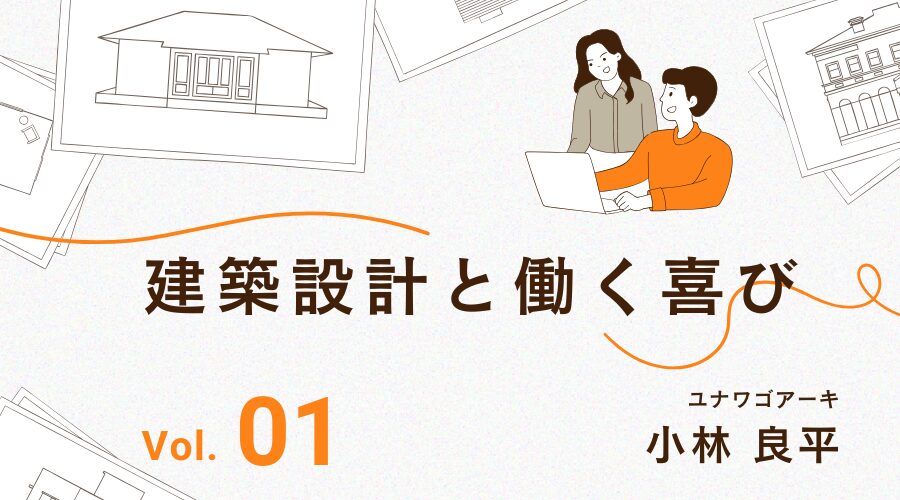
建築人を豊かにすることを目指すA-magazineでは、建築設計に携わる人びとが建築設計のどのような点に働く喜びを見出しているのか、さまざまな事例を紹介する連載をスタートします。今回寄稿していただいたのは、ユナワゴアーキの小林良平さん。学生時代から災害被災地での復興支援に継続的に関わる一方で、住宅などの建築設計にも取り組んでこられました。当初はご自身のなかで乖離していたという両者の活動につながりを見出すことができた経験をお届けします。
======
茨城県で活動しているユナワゴアーキの小林良平と申します。ユナワゴとは私の地元の地名である「油縄子」に由来しています。建築設計の仕事を始めて約10年になりますが、小さな建築の設計をする一方で、東日本大震災の被災地での復興支援、茨城県の水害の被災地での空き家再生などの活動をしてきました。今回は「建築設計と働く喜び」という題材に対して、私の経験をできる限り記したいと思います。
1.創造の喜び
おそらく建築設計を生業とする多くの方々と同じく、大学で建築設計に夢中になりました。何も無いところから試行錯誤し、唯一のものをつくり出すことは大きな喜びです。
しかし仕事になると様々な課題があります。耐震性の確保、省エネルギー、バリアフリー、価値観の多様化、家族構成の変化、建設費が高騰する中でのコスト削減など多くの課題に対応しなくてはいけません。また、空き家問題や被災地の復興など建築に関連する社会課題も多くあります。
この多様化する課題への対応と、創造の喜びのバランスを上手く取ることが、建築設計を仕事にする時に重要になると考えています。
2.東日本大震災の被災地での経験
大学生の時、仙台で東日本大震災を経験しました。多くの建築家が被災地に入っていき、学生だった私も引っ張られるように被災地に向かいました。突如、被災地の復興という難しい課題に向き合うことになりました。
以降、被災地で出会った建築家のヨコミゾマコト氏の近くで、津波被害の大きかった石巻市雄勝町の復興計画に数年間、関わりました。ヨコミゾ氏は学生と一緒に被災地を歩き回り、地元住民に共感し、真摯に雄勝町に向き合っていました。 実績のある建築家も地道に出来ることを模索している姿を見て、私もより主体的に復興の現実的な課題に向き合うようになりました。
雄勝町でしたことは、残存する民家や風景など、雄勝町特有の個性(文化的地域遺伝子)を集め、復興計画に活かすことです。
様々な活動をする中で、いくつかの苦い経験がありました。
例えば、漁師の生活が海、漁港、漁師小屋、住宅間の移動とともにあることに着目した土地利用計画案を作成しました。津波リスクが低い高台で主な漁具の保管や漁具の修理を行い、津波リスクが高い海際での活動を必要最低限とすることで、巨大な防潮堤がなくても安全な暮らしを続けられると考えて計画したものです。約6mから10mの高さで計画されていた防潮堤が建設されてしまうと、漁師小屋や作業場から海が見えなくなり、海の状態や養殖棚の様子が見えないことによる不便さや、漁港に保管する漁具や船の管理に対する不安、大雨時に防潮堤の陸地側で水が溜まることへの懸念が漁師へのヒアリングからあがっていました。文化的、景観的にも最善策ではないと考えていたことから、津波リスクに配慮した土地の使い方と避難道の整備によって、防潮堤の高さを低くする方法を検討した計画案でした。しかし、デリケートな提案であったことから、地元住民と上手く連携することができず、大きな防潮堤が建設されました。
浜のお母さん達が料理を振る舞うレストランの計画が、着工直前で中断したこともあります。復興過程の様々な負荷がかかる状況で、新しいレストランを始める心理的負担に設計者として寄り添うことができていませんでした。
また、景観を整えるために、調査に基づく雄勝町らしい景観や建物をつくるデザインコードの提案をしていましたが、いざある集会所の設計者になると、「ヴォリュームをずらす」といったデザインコードにはない建築的操作を行なったり、別の集会所ではデザインコードを守り、多くの住民意見を採り入れて作成した案を自分が魅力的と思えなかったりするなど、 上手く消化できないことがありました。
被災地の活動とは別に依頼のあった住宅の設計の仕事では、被災地での活動の反動なのか、建築の新しさを追い求めるあまり、お施主さんが納得する案がつくれず、途中で中断したこともあります。
当時の私には、新しさを追求する建築設計と被災地の復興のような現実的な課題に向き合うことの間に大きなギャップがありました。また、説得力のある良い提案であっても、相手の立場や気持ちに寄り添い、バランスを上手く取らないと実現しないことを学びました。
3.触媒になること
ある時、建築家の坂東幸輔氏から水害の被災地である茨城県常総市で、空き家を活用し地域住民が集える場をつくろうとしている人を紹介されました。浸水した建物を直せず空き家が増え、高齢化や孤立化が加速していました。そこでは建築のデザインよりも、用途の検討や資金計画などのプロジェクトの舵取りや、建築の法適合調査や耐震改修などの技術的なサポートが求められました。
坂東氏の「スターになるだけが建築家じゃないと思うし、経験がないことも調べればきっとできるよ」という言葉にも後押しされ、私はプロジェクトの実現性を高める、触媒のように働くことを意識しました。工事の大部分を地域住民やボランティアのDIYでつくるなど制限も多くありましたが、代わりに参加者の主体性が高まり、自然に物事が回り始めると、なんとも言えない達成感がありました。
建築の設計においても、少し意識が変わっていきました。その時に出会うお施主さんや大工さんなどと一緒のチームであると考えた時に、皆が得意なことを活かせるようにすることで、自分だけでは生まれなかったものが生まれることも良いと思うようになりました。
4.文脈を読み取る
そのように振る舞う時、リサーチに力を入れることを意識しています。敷地、町には必ず固有の歴史があります。地理や産業、文化、風景など様々な観点から見ていくと、現在に至るまでの流れが見えてきます。また、人との対話では、その人が何を望んでいるか、どのような経験や価値観を持っているかをよく感じるようにします。そのようにしてプロジェクト全体に流れる文脈を読み取ります。そこに自分が関わることで流れを一本化させたり、時にはより良い方向へずらしたりします。大きな方向性を守ることで適切で自然な形にしつつ、少しの新しさを加えるようなスタンスです。
現実的な課題に向き合うことと、新しい建築をつくろうとすることの感覚のギャップは時間をかけて少しずつ埋まっていきました。どちらも複雑な条件を構築的に整理し、最適解を探すという点では一緒であると思います。おそらく足枷になっていたのは、目新しい作品をつくることへの固執だったのだと思います。こだわりは持っていて良いと思いますが、柔軟性が必要なのだと思います。
5.学びの喜び
また、気分が変わることで生まれた少しの余裕によって、多様な課題を幅のある特性と捉え、自分ができる範囲に集中するようになりました。
例えば最近は、検査済証のない建物の活用のために法律の勉強漬けになったり、ある時はコスト削減のためにDIYしたり、ある時は、築100年以上の古民家の文化財保存のために仕口のディテールをじっくりスケッチしたりしています。プロジェクトごとに訪れる様々な町の特徴を知り、そこに住む人と話すことも楽しみです。それは創造の喜びというよりも、学びの喜びに近いのかもしれません。
ただ学びはいずれ創造に活かされると考えています。そのように一歩引いて考え、自分の中に正のスパイラルを作ることが、多様な課題がある中で、プロジェクトの実現性を高めつつ、成長しながら創造の喜びを感じる方法の1つなのではないかと思います。
(企画・編集:ロンロ・ボナペティ)
小林 良平
1989年 茨城県日立市生まれ。
2008年 茨城県立水戸第一高等学校卒業。
2012年 東北大学工学部建築・社会環境工学科卒業。
2014年 東京藝術大学大学院美術研究科建築専攻修了。
2015-2019年 東京藝術大学建築科教育研究助手。
2016年 一級建築士取得。
2021年 一級建築士事務所「ユナワゴアーキ」を設立。




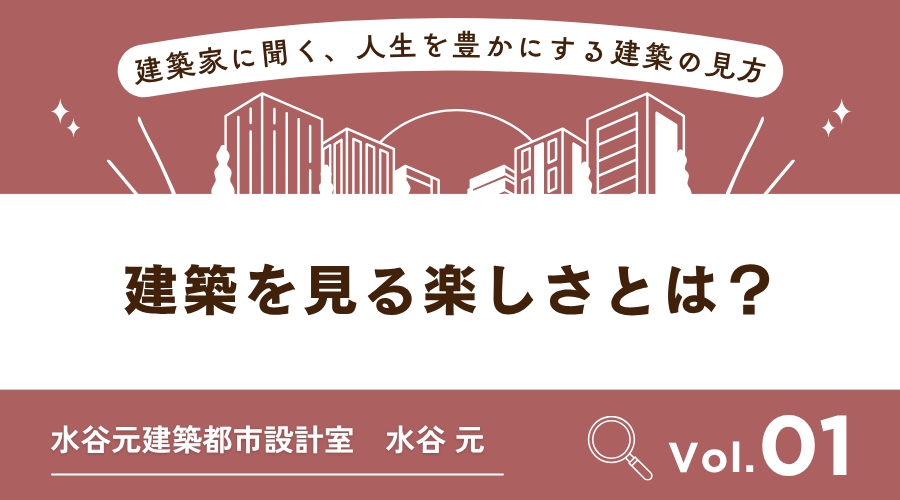
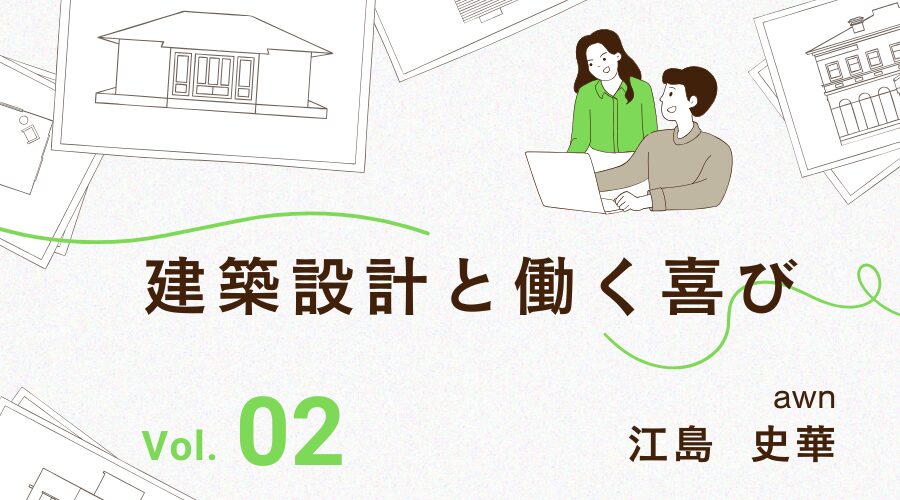

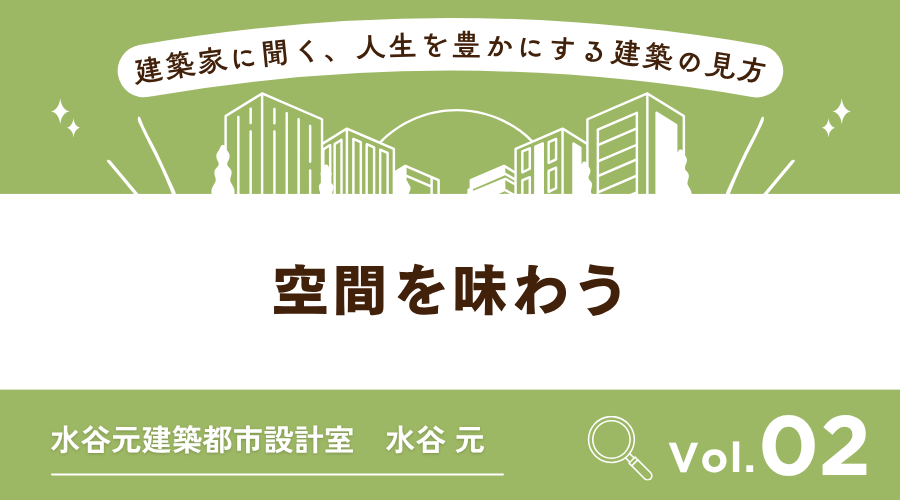
.jpg)
が設計した金沢21世紀美術館-21st-Century-Museum-of-Contemporary-Art-Kanazawa-DesignSANAA.jpg)
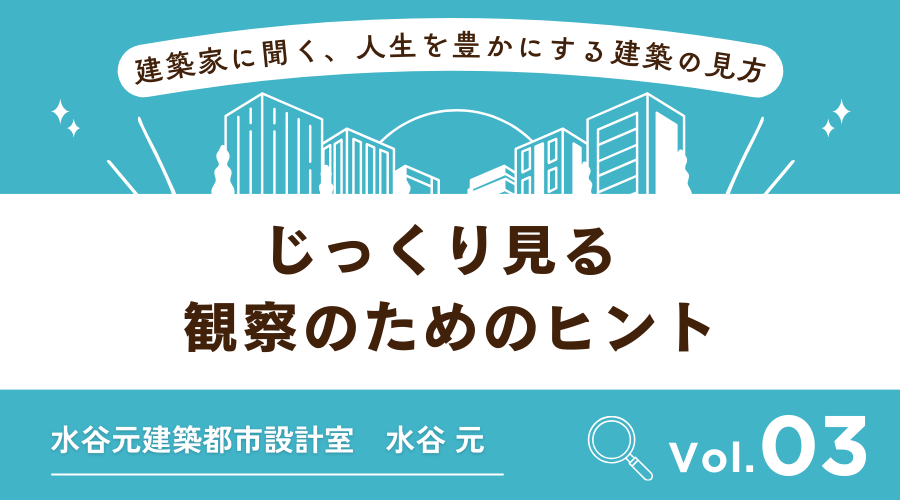

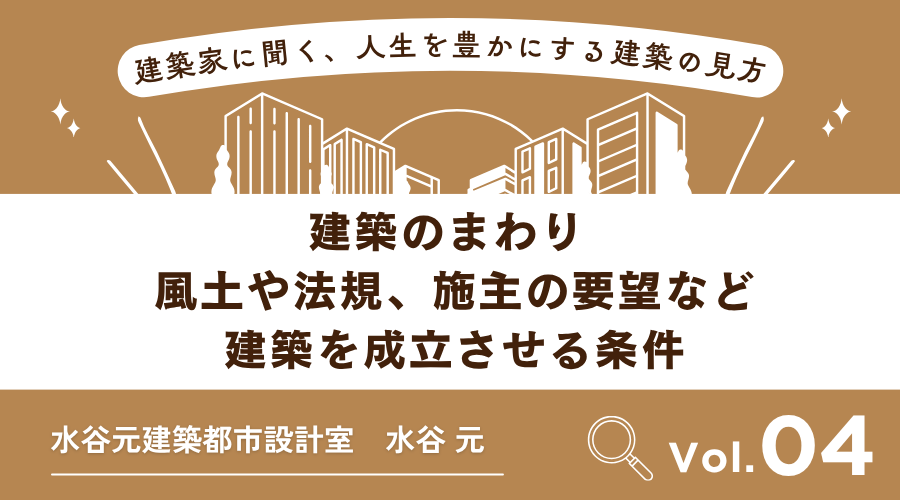
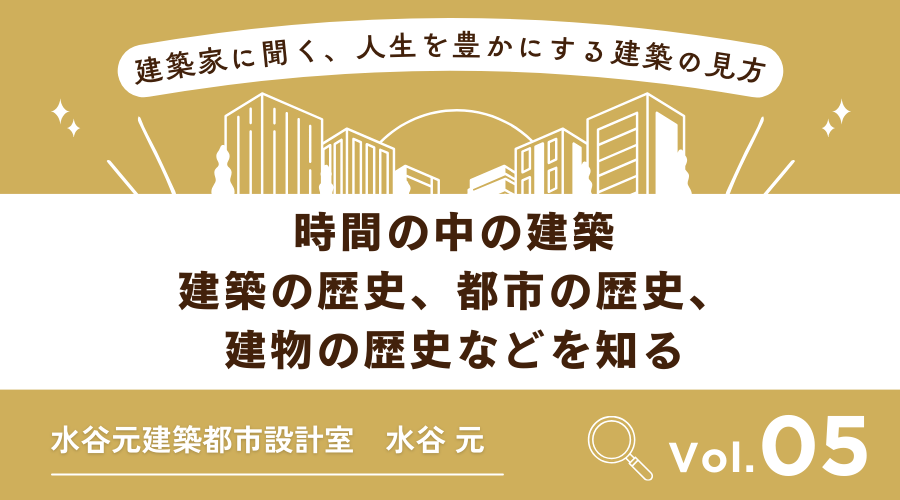
.jpg)