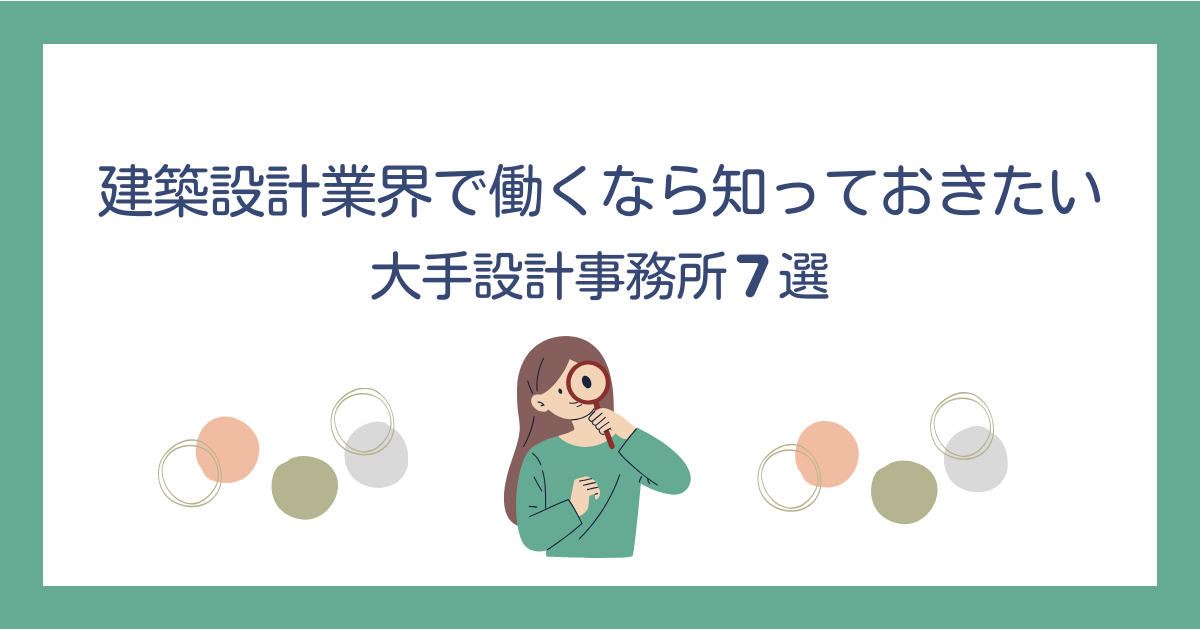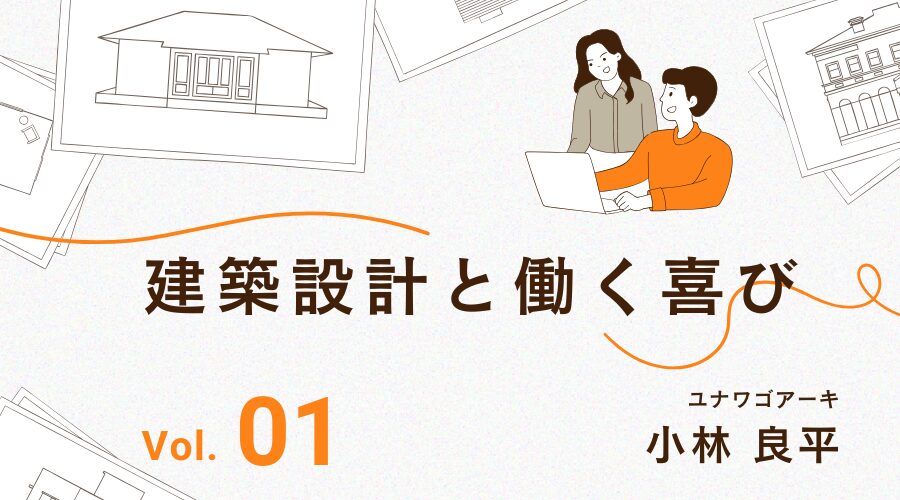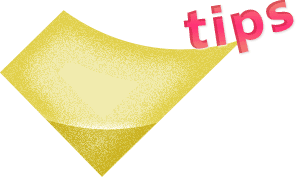
建築業界のリアルな情報や就職・転職活動で役立つ情報を紹介します。
2025.03.11
「建築設計」の仕事とは?3つの種類と就職先、資格を徹底解説!

みなさんは、建築設計の仕事内容をご存知でしょうか?
中には、「建築業界に興味はあるけど、具体的な仕事内容は分からない」という方もいるかもしれません。
そこで、本記事では建築設計の仕事について解説します。
建築設計の業種や就職先、役立つ資格も併せて紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

建築設計の業種は3種類
建築設計とは、建物や設備設計に関係する業務を包括的に表した言葉です。
技術士や建築士、建築事務所の所員などが建築設計に携わる業種となっています。
建築設計の業種は、主に「意匠設計」「構造設計」「設備設計」の3種類です。
1つずつどのような内容なのかを見ていきましょう。
意匠設計
意匠設計は、建築物におけるデザインを決定する仕事です。
具体的には、クライアントから要望を聞き取り、理想的な間取りやデザインを考えます。
意匠設計者が作成した設計図を基に工事が進行するため、重要な役割を果たしているのです。
また、意匠設計者は構造設計者や設備設計者と連携して全体をまとめるリーダー役を担います。
そのため、スケジュール管理能力やリーダーシップも必要になるでしょう。
構造設計
構造設計は、「構造」の観点から建築物の設計に問題がないか確かめる仕事です。
具体的には、構造解析や部材検討、ディテールの検討、計算書の作成、申請業務、着工後の現場対応などが含まれます。
構造設計者は力学的なセンスやコミュニケーション能力を持ち、柔軟にスケジュール調整しながら効率よく仕事を進めなければなりません。
また、問題があった際に解決策を考案する「提案力」も求められます。
設備設計
設備設計は、建物として機能するために必要な電気・空調・音響・給排水設備などを適切に計画・設計する仕事です。
設備設計者は、省エネルギーや快適性を考慮しながら、建物のインフラ整備やデザインと機能の両立を図ります。
また、設備機器の選定時には、コストも考えなければなりません。
クライアントの希望と予算感を両立させるためにも、コスト管理力が求められます。
建築設計ができる就職先とは?
続いて、建築設計ができる就職先を解説します。
・建築設計事務所
・ゼネコンなどの建設会社
・ハウスメーカーや工務店
それぞれの特徴を見ていきましょう。
建築設計事務所
設計事務所では、建築士が建物のデザインや設計を担当しています。
建築士1名とスタッフ数名で運営する事務所から、建築士が多数在籍して総従業員数100名以上の大型事務所まで、規模は様々です。
人員構成によりデザインの要である「意匠設計」「構造設計」は事務所内で行い、「設備設計」は外部に依頼するケースもあります。
設計事務所では設計後の施工は工務店が行い、建築設計士は工事が適正に行われているかを確認する「監理」を担当するのです。
設計事務所に建築を依頼する顧客は、予算や時間よりデザイン性を重視する傾向にあります。
また、ハウスメーカーのように規格がないため、より自由でアーティスティックな建築に携われる職場と言えるでしょう。
住宅以外に公共施設や公園なども手掛けており、建築設計の全ての工程を体験できるので、スキルアップするためには最適な職場です。
一方、デメリットとして「大手企業よりも福利厚生が充実していない」、「建築士のアシスタント的業務が中心になる」などが挙げられます。
設計事務所を選ぶ際には、代表の建築士から何を学びたいかを明確にしておくと安心です。
ゼネコンなどの建設会社
大手ゼネコンは、ショッピングモールやタワーマンション、スタジアム、ミュージアムなど様々な大型建築を手掛けています。
個別の建物だけではなく、住居と商業施設を組み合わせた「街づくり」のプロジェクトもゼネコンの仕事です。
ゼネコンへ入社することで、個人住宅にはない大胆なデザイン建築の設計を担当でき、歴史に名を刻む仕事ができる可能性もあります。
また、スーパーゼネコンと呼ばれる超大手企業では、平均年収1,000万円以上を狙えるので収入面の魅力も大きいです。
しかし、大規模建築は関わる企業や人員が多く、それぞれの立場を尊重しながらも建築設計士としての矜持を貫くのはストレスも大きいというデメリットがあります。
多くの人とコミュニケーションを取り、歴史に残る仕事をしたいと考えている方は、ぜひゼネコンへの就職を検討してみてください。
ハウスメーカーや工務店
ハウスメーカーや工務店は、規格を統一し大量生産することにより、コストを押さえた住宅を販売しています。
建築設計士のオリジナリティを発揮するのが難しい半面、経験が浅くても規格に沿って設計できるのがメリットです。
建売住宅であれば、入社2〜3年目には単独で建築設計を任せられるため、若いうちから実績を重ねていけます。
また、「予算は安く」「早く建てたい」という顧客の要望と、デザイン性を両立させるために提案力も培われるようです。
給与や福利厚生が安定しているため、実績を積みながら一級建築士を目指す環境も整っているのがポイントです。
経験を積むと注文住宅で設計センスをより活かせるチャンスも増え、カフェやクリニックなど店舗併用住宅の設計にも携わり、一般住宅以外の設計スキルも身に付けることができます。
未経験からスキルアップして建築設計士を目指す方は、ハウスメーカーや工務店への就職を検討しましょう。
建築設計に役立つ資格とは?
ここからは、建築設計に役立つ資格を解説します。
・一級建築士
・二級建築士
・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士
・建築CAD検定試験
どの資格も持っていて損はないため、積極的に取得しましょう。
一級建築士
一級建築士は、高層ビルから住宅まで物件規模を問わず設計を担当できます。
施工管理技士など、他の国家資格と比べ、非常に難易度の高い資格で、設計だけでなく施工やデベロッパーなど、幅広い分野で重宝されます。
一級建築士の資格取得は建築系の学校を卒業すれば、実務経験がなくても受験可能です。
合格後に大学卒業者は2年、専門学校卒業者は4年の実務経験を積んだ後に、一級建築士として登録完了し一級建築士を名乗ることができます。
建築系の学校を卒業していない場合は、7年間の実務経験後に二級建築士になれば受験資格を得られ、4年の実務経験後に一級建築士の登録が可能です。
二級建築士
国家資格の二級建築士を取得していると、建築物の設計や工事監理などを担当できます。
一級建築士と比較して、設計できる建物の規模と構造に制限がありますが、二級建築士も建築業界で大変優遇される資格です。
また、二級建築士として4年の実務経験があれば、一級建築士の受験資格が得られるので、建築士としてキャリアアップを目指す場合は、二級建築士資格を取得することをおすすめします。
1級建築施工管理技士
1級建築施工管理技士は、建設業法における施工管理の最高峰資格です。
この資格保持者は、大規模建築工事の施工計画の作成から品質管理、工程管理、安全管理、さらには建設工事施工におけるマネジメント全般を担当できます。
キャリアアップや収入向上に直結する資格であり、建設業界での活躍の幅を大きく広げられます。
2級建築施工管理技士
2級建築施工管理技士は、中小規模の建築工事における施工管理を担当できる資格です。
1級と比較して受験資格のハードルが低く、実務経験も少なくて済むため、若手技術者のキャリアパスとして最初に目指されることが多い資格です。
建築施工の基礎知識と現場での実践力を証明できます。
建築CAD検定試験
建築CAD検定試験は、建築設計においてコンピュータを用いた製図技術を評価する検定です。
准1・2・3・4級があり、各級によって求められるCADスキルのレベルが異なります。
この資格は、建築設計事務所や建設会社での採用において高く評価され、特に近年のBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)の普及に伴い、その重要性が増しているのが特徴です。
実務に即した出題内容が特徴で、建築図面の作成能力だけでなく、建築知識や設計ルールの理解も問われます。
手描き製図からデジタル設計への移行が進む中、必須のスキル証明となっています。
設計事務所へ就職するには建築士の資格が必要?
設計事務所へ就職するには建築士の資格が必要だと考えている方も多いでしょう。
しかし、実際には建築士資格がなくても設計事務所へ就職できます。
建築士資格を持っていると、キャリアパスの幅が広がるのが特徴です。
建築士の資格を取るとできること
建築士の資格を取得すると、建築物の設計や工事監理を行う権限が法的に認められます。
特に一級建築士は、規模や用途に制限なく建築物の設計・工事監理ができ、二級・木造建築士も一定規模までの建築物に対してこれらの業務が可能です。
また、確認申請書への押印権限も持ち、建築基準法に基づく適合性を証明できます。
資格があれば独立して設計事務所を開設することも可能であり、建設業界でのキャリアパスの幅が広がります。
さらに、建築士は専門家としての社会的信頼も得られ、設計コンペへの参加資格や公共事業の入札参加資格なども取得しやすくなります。
設計事務所での設計業務に建築士の資格の有無は関係ない
設計事務所での実務において、建築士の資格がなくても設計業務に携わることは可能です。
実際、多くの設計事務所では資格を持たないスタッフも図面作成やモデリング、プレゼンテーション資料の作成、クライアントとの打ち合わせなど幅広い業務を担当しています。
重要なのは、最終的な設計図書に一級建築士などの資格保持者が押印することであり、その前段階での設計プロセスは無資格者でも参画できます。
特に大規模事務所では分業制をとっていることが多く、専門分野ごとに役割分担しています。
そのため、設計事務所ではスキルや経験が重視され、必ずしも全員が資格保持者である必要はありません。
資格が必要ないなら何が必要?
設計事務所で活躍するためには、資格よりもまず実務スキルが重要です。
具体的には、CADやBIM、3Dモデリングソフトなどのデジタルツールを使いこなす能力、デザインセンス、プレゼンテーション能力が求められます。
また、建築に関する基礎知識(構造、設備、法規など)を理解していることや、クライアントのニーズを適切に把握して設計に反映できるコミュニケーション能力も不可欠です。
さらに、チームでプロジェクトを進める協調性や、納期を守る時間管理能力、問題解決能力なども重視されます。
設計事務所では実績を積み重ねることでキャリアアップできる環境も多く、資格取得はあくまでもその過程での選択肢の1つです。
まとめ
本記事では、建築設計の仕事について解説しました。
建築設計の業種は、主に「意匠設計」「構造設計」「設備設計」の3種類です。
また、建築設計ができる主な就職先は「建築設計事務所」「ゼネコンなどの建設会社」「ハウスメーカーや工務店」となっています。
建築設計に役立つ資格は、以下の通りです。
|
どの資格も持っていて損はないため、興味がある方は積極的に取得しましょう。